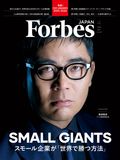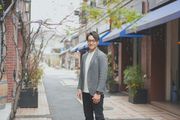多忙な職場と安らげる自宅のあいだに、人生を過ごす場所がもう一つある──肩の力を抜き、人とつながれる「サードプレイス(第3の場所)」だ。サードプレイスは米社会学者レイ・オルデンバーグが概念化したもので、自宅(第1の場所)でも職場(第2の場所)でもない、人が集まっていて帰属意識を覚えられる居場所のことだ。
オルデンバーグは、1989年の著書『サードプレイス――コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』(邦訳:みすず書房)で、この「サードプレイス」という概念を提唱し、カフェやバー、書店といった公共の場が社会的なつながりを促すと強調した。2000年には『Celebrating the Third Place(素晴らしきサードプレイス)』(未邦訳)を出版してこの概念を発展させ、サードプレイスが及ぼす影響について実例を挙げて紹介している。
オルデンバーグは、サードプレイスの主な特徴として次を挙げている。中立的な場であること、すべての人に開かれていること、地位や身分にこだわらないこと、気軽な会話が促されることだ。
米人気ドラマ『フレンズ』に登場するカフェ「セントラル・パーク」を思い浮かべてほしい。登場人物が日々足を運び、コーヒーを飲むだけでなく人とのつながりや安らぎを求め、日常生活から逃避できる場として描かれていた。あれがまさにサードプレイスだ。気兼ねがいらず、人であふれて活気に満ち、プレッシャーやしがらみを感じることがない場所。カフェであれ公園であれ、図書館やスポーツジムであれ、頻繁に足を運び、くつろぎ、エネルギーをチャージできるのがサードプレイスなのだ。
では、サードプレイスをもつことでウェルビーイングにどのような違いが表れるのか、サードプレイスはどうやって見つけたらいいのか、説明していこう。
サードプレイスが人生に与える好影響
1. 孤独を感じにくくなる
サードプレイスは、人と人がつながる場であり、孤独と闘う上でとても有効な手段となる。
多くの人は、サードプレイスがあると帰属意識が生まれる。自分を支えてくれる盤石な社会的つながりをもたない人であればなおさらだ。そうした場で人と交流すると共同体の感覚が得られ、自分は他人に気づいてもらえている、人とつながっている、と感じられるようになる。
『Journal of Service Research』に掲載された研究では、ショッピングセンターや近所の食堂、カフェといったサードプレイスが、他の人と交流したり感情的に支えてもらったりする場となって、孤独感を和らげるのに役立つことが明らかになった。同研究チームによればそうした環境では、客と店舗スタッフのあいだに「商売を介した友情」が生まれることがあるという。それが特に顕著なのは高齢者だ。
また、サードプレイスがあると、友人とのあいだに強い友情を育む上で不可欠なルーティンや習慣が生まれやすくなる。カフェで週に1度会うとか、決まった曜日の午後に公園を一緒に散歩するなど、同じ場所で定期的に会っているうちに、調和と連帯感を感じられるようになるのだ。
そうしたルーティンを通じて友情が規則的に維持され、深まっていくうちに、双方に感情的・社会的なメリットがもたらされる。習慣化したその行動は時間とともに、単に顔を合わせる機会から、感情を支える重要な土台へと変化していき、ウェルビーイング全般が上向き、孤独感が解消されていく。