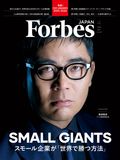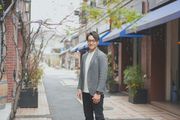2. 衝動的に反応するのではなく、適切に対応できるようになる
あらゆる出来事にすぐに反応する必要はない。しばしば、物事を自分の思うとおりに進めたいという衝動が、苛立ちや軽率な判断、不要なストレスを招く。しかし、「人はそれぞれ自分の選択をする」ことを受け入れることで、感情的な荒波から自由になれる。
たとえば、友人が直前に予定をキャンセルした場合、苛立ちを覚えるかもしれないが、見方を変える余地があるかもしれない。相手にはやむを得ない理由があったのかもしれないし、あるいは思わぬ形で一人の時間をもてるチャンスかもしれない。
受け入れる姿勢をもっていれば、「なぜこうなったのか」と恨むのではなく、自分の平穏を保ったまま状況に柔軟に対応できる。こうした思考プロセスはマインドフルネスや自己認識を育み、起きた出来事とそれに対する自分の対応の間に「ひと呼吸置く」余裕を与える。感情に突き動かされるのではなく、自分の健康や幸福に沿った選択をする余地が生まれるのだ。
『Cognition and Emotion』誌に掲載された研究では、「感情を抑圧する」よりも「受け入れる」ほうが、困難な感情をうまく扱ううえで効果的かどうかを調べている。悲しい動画を見た後に感情を抑圧しようとした人々は、動画直後にはあまり悲しみを感じなかったものの、あとになって「リバウンド効果」により気分がより落ち込んだ。逆に感情を受け入れた人は、最初は悲しみを強く感じたものの、比較的早く回復している。
この研究は、感情を抑圧することが精神エネルギーを多く消費し、フラストレーションをため込みやすくする一因になることを示している。一方で、受け入れる姿勢を取ればその場にしっかりと向き合い、感情を変えようとして泥沼化することなく、回復を早められる可能性がある。
「あるがまま理論」の考え方を取り入れると、出来事と自分の反応の間に余白が生まれ、衝動的ではなく冷静に行動を選択できるようになる。これは自制心を高め、感情の回復を早めることにもつながる。長期的に見ると、自分のウェルビーイングをより良い方向へ導くだろう。
3. 自分のエネルギーを意図的に使えるようになる
他人の行動や思考、あるいはあらゆる出来事の結末をコントロールしようとすることは、精神的にも感情的にも大きな負荷となる。そうしたコントロール欲求から離れ、自分の選択に集中すると、本来なら苛立ちや抵抗で浪費していたエネルギーを節約できる。この新たに生まれた余力を、自己成長や有意義な人間関係、心から楽しめることに振り向けられるのだ。
『European Journal of Social Psychology』誌に掲載された研究によると、自己調整は有限のリソースであり、あるタスクに使うと後のタスクに使える力は減少することが示されている。感情や衝動をコントロールするには精神力が必要で、使い果たすと自己制御が難しくなるという考え方だ。
たとえば、なぜ相手が自分の望むように接してくれないのかを延々と考えるより、自分の境界線をしっかりともち、価値観に合う人間関係を選ぶことに意識を向けるほうが建設的である。外部要因を操作しようとするよりも、自分の行動や判断に注力することで、自分にとって本当に大切なことにエネルギーを注ぎやすくなる。
「あるがまま理論」の考え方を実践すれば、コントロール不能なものに気力を消耗する代わりに、あくまで自分の選択と反応を整えることに力を注げる。この転換によって、より健康的かつ建設的な決断を下しやすくなるだろう。