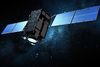「自然界の探検家」は、他の種でも
自然界には、地質学的な力や偶然の出来事に導かれ、類いまれな旅をして海を渡った動物たちの例があふれている。例えば、マダガスカル島の豊かな生物多様性は、同じような「浮島の航海」によるところが大きい。2023年5月に『Biological Reviews』誌で発表された研究によれば、キツネザル、テンレックといったマダガスカル島に生息する陸生脊椎動物の祖先は、はるか昔に、植物でできたいかだに乗って、アフリカ本土からマダガスカル島へ渡ったと見られるという。
同様に、一般に南極やその近辺の極寒の地とのつながりが深いペンギンは、オーストラリア、アフリカ、南アメリカの一部にも見られる。太古のペンギンが、おそらくは海流の変化や気候条件に助けられ、はるか昔にそうした比較的温暖な地域へ移動したことが、化石記録からうかがえる。
ヒメアカタテハのような昆虫も、驚くような移動を成し遂げる。この優美なチョウが数世代がかりの旅を敢行し、ヨーロッパからアフリカまでの数千kmを移動することは昔から知られている。
アフリカの霊長類が大西洋を横断した時期は、大きな環境変化が起きていた時期と一致する。始新世後期から漸新世初期にかけて、南極で氷河が形成されるのに伴って海面が下降し、大陸と大陸を隔てる海が狭くなった。この時期には、海流と嵐も強まっていた。つまり、動物を乗せて長距離を移動できるくらい大きな「天然のいかだ」ができやすかったということだ。
そうした旅を生き延びられる確率はわずかだが、生き延びた者は、チャンスに満ちた陸地に迎えられた。多くの捕食者や競争相手がいない南アメリカは、適応と進化を促す絶好の地だった。そして時とともに、そうした初期のパイオニアたちの貢献により、私たちがいま目にしている生態系がかたちづくられていったのだ。
(forbes.com 原文)