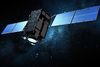歯の化石が、いかだに乗った霊長類の物語を明らかにするまで
この信じがたい旅の証拠は、南アメリカで見つかった歯の化石から得られた。この化石は3つの種のもので、移動が少なくとも3回あったことを表している。具体的には、ペルーピテクス・ウカヤリエンシス(Perupithecus ucayaliensis)、ウカヤリピテクス・ペルディタ(Ucayalipithecus perdita)、そして、最も新しいアシャニンカセブス・シンプソニ(Ashaninkacebus simpsoni)の3種だ。最初に見つかったペルーピテクスの化石は、およそ3600万年前のもので、2015年にペルーで発見された。この歯は、北アフリカで同時代に生息していた霊長類のものと極めてよく似ており、進化上、直接のつながりがあることを示している。
2020年にも、同じ地域でウカヤリピテクス・ペルディタの化石が見つかり、3200万年前ごろに別の航海があったことが示された。さらに最近では、2023年にアシャニンカセブス・シンプソニがブラジルで発見されたことで、そうした太古の航海をめぐる理解がいっそう広がり、果実を食べる小型で適応力の高い霊長類の一群の存在が明らかになった。
新世界ザル(南アメリカを中心に中央アメリカ,熱帯メキシコまで分布する「広鼻猿類」)の化石記録は、以前からアフリカ起源を示唆していたが、最近の発見により、これまでになく明確な証拠が得られている。
ペルーピテクス、ウカヤリピテクス、アシャニンカセブスの臼歯は、アフリカの霊長類の歯と驚くほど似ており、同じ進化系統に属することを裏づけている。
これらの歯に見られる独特な咬頭(こうとう:臼歯上側の尖っている「山」の部分)のパターンは、3000万年以上前に生きていたアフリカの霊長類であるパラピテクス科とエオシミアス科のものと瓜ふたつだ。
この発見をいっそう興味深いものにしているのが、地理的な背景だ。ペルーのユルア川流域のような南アメリカの化石産出地では、年代のわりに保存状態が極めて良い歯が出土している。そうした発見は、アフリカにいた祖先にあたる霊長類と、オマキザル、ホエザル、タマリンといった多種多様な現生の新世界ザルとのギャップを埋めてきた。