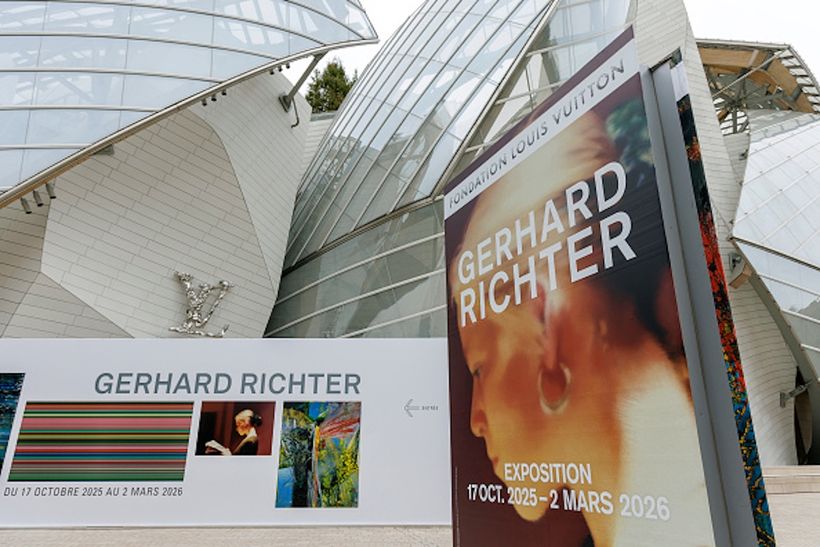その事例は、ブラインドフットボールのように、社会通念上ハンディとされている要素を逆に可能性を広げるチャンスとして扱っています。
日本の伝統織物のなかでも最高級品として扱われる織物、宮古上布(みやこじょうふ)がその事例です。11月に宮古島を訪れ、織り手のひとりでもある新里玲子(しんざと・れいこ)さんの工房を訪ねました。ご自宅の敷地の一部に工房があります。職住一体型の生活のなかから宮古上布は生まれます。
 宮古上布に使われる糸は苧麻(ちょま)。麻の一種です。これを水につけてふやかしてから細かく裂き、糸としてつむいでいきます。非常に手間暇のかかる作業で、伝統的に「島のばあば」と呼ばれる高齢女性が担っています。最終製品は数百万円という高価格で取引されることもありますが、糸をつむぐ女性職人の賃金は高くありません。
宮古上布に使われる糸は苧麻(ちょま)。麻の一種です。これを水につけてふやかしてから細かく裂き、糸としてつむいでいきます。非常に手間暇のかかる作業で、伝統的に「島のばあば」と呼ばれる高齢女性が担っています。最終製品は数百万円という高価格で取引されることもありますが、糸をつむぐ女性職人の賃金は高くありません。職人の高齢化、川上の職人の低賃金、若い人の参入がない産業。こうした状況について、これまで私は、伝統技術の継承にとって「解決すべき社会課題」なのだとすっかり思い込んでいました。今の感覚でいうところの「デザイン+ソーシャルビジネス」という視点をもって何らかの介入を検討されるべき状況なのだと思い込んでいました。
しかし、現場を見て、話を聞いて、私のその発想がたいへんに浅はかなものだったことを思い知らされました。玲子さんのお話は、私の表層的な思い込みを180°覆すものでした。
 玲子さんは太さが異なる数種類の糸を見せてくれました。60代、70代、80代、90代の女性が紡いだ糸です。年齢が高くなるにつれて、糸が太くなります。年とともに指の感覚が鈍くなるので、糸も太くなっていくのだそうです。
玲子さんは太さが異なる数種類の糸を見せてくれました。60代、70代、80代、90代の女性が紡いだ糸です。年齢が高くなるにつれて、糸が太くなります。年とともに指の感覚が鈍くなるので、糸も太くなっていくのだそうです。常識的に考えると、若い人がつむぐ極細の糸の方が当然、上質で高価だと推測するではないですか? ところが、太い糸は帯にふさわしく、稀少性が高いことも手伝って、細い糸より高値で取引されることもあるといいます。
「糸は、60代という若い頃から始めるのが適切で、感覚が鈍くなっていく90代でようやく大成する」というのが宮古上布の世界における考え方なのです。90代になってやっと、糸をやっておいてよかった、と女性たちは言うそうです。「だから、高齢化万歳、と私たちは言っているんですよ」と玲子さんは大笑します。