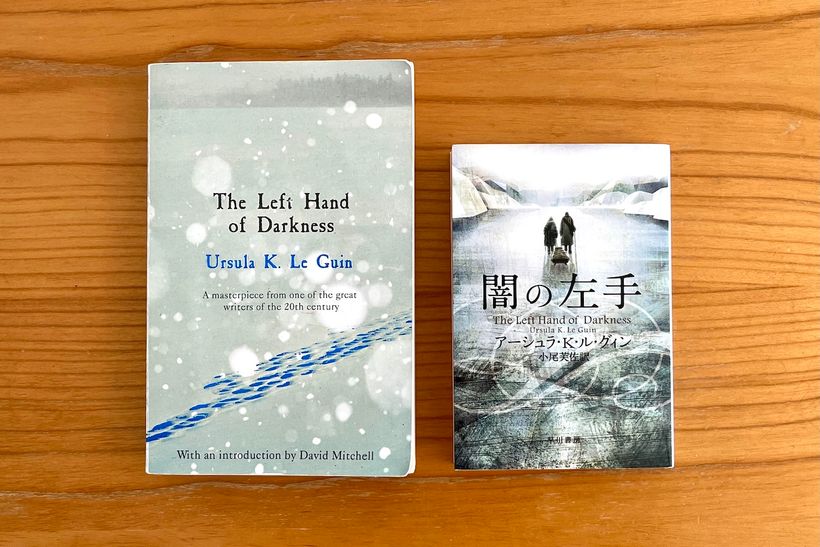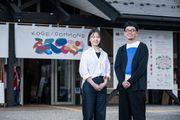「あの人は心が温かい」と言われるのは最大の賛辞ではないか、ということをテーマにします。「熱い」ではなく「温かい」です。まず、二つのエピソードをあげましょう。
一つ目です。
「心が温かい」という表現がとても似合うのが、ぼくがイタリア生活のはじめにトリノでお世話になった人生の師匠ともよぶべき宮川秀之さんです。2年前、「非日常で贅沢な冒険こそが『究極のラグジュアリー』なのか?」でも紹介しました。1960年にバイクでイタリアにたどり着き、トリノのモーターショーでイタリア人の女性に一目ぼれ。2人は恋におち結婚の末、4人の実の子どもの他に韓国、インド、イタリアの子を養子として育てた人です。
実業家として成功をおさめ、日本の自動車業界発展をデザインから側面支援をした功績で「日本自動車殿堂」にも入っています。ビジネス上の成果だけでなく、イタリアやアフリカの困った人たちに手を差し伸べる社会活動を続けてきました。現在はトスカーナでワイナリーを経営しています。
ぼくがトリノで生活をはじめて間もない頃、現地のモーターショー会場で日本から来た人と偶然会いました。自動車雑誌に知的なコラムを連載している、ぼくも憧れていた自動車業界のコンサルタントです。宮川さんのことも良く知るその人と雑談しているなかで、彼は「宮川さんって心の温かい人ですよね」と呟きました。
その時、ぼくの心が満ち足りた感じになった。30年以上を経てそれを思い出し、「そうだ、こんなにも得難い人の傍にいるのだ」と気づいたのでした。「熱い人」はたくさんいるけれど、「温かい人」はあまりいないと思っていたのです。
二つ目のエピソードをあげます。
長くイタリアで生活してきて思うのは、熱さと温かさのバランスの妙が効いている社会であることです。「イタリア人は情熱的」と他国の人だけでなく自国の人も言います。自分の信じるところにエネルギーを集中的に注入するのを厭わない。そういう人と知り合う確率が高いです。しかし、イタリアで生活する、あるいは旅をすれば分かるでしょうが、温かいと感じる経験をすることが少なくありません。
今は20代前半になる子どもが小さな時代、毎年の夏、バカンスをどこで生活するかは大きなテーマでした。できるだけ自然豊かな環境が良いと思い、南仏の海岸やオーストリアのアルプスの麓を最初は選びました。すると、現地で見知らぬ人から受ける子どもへの対応は、ミラノでのそれより非寛容的であると感じました。レストランであれ、宿泊先であったアパートであれ、です。