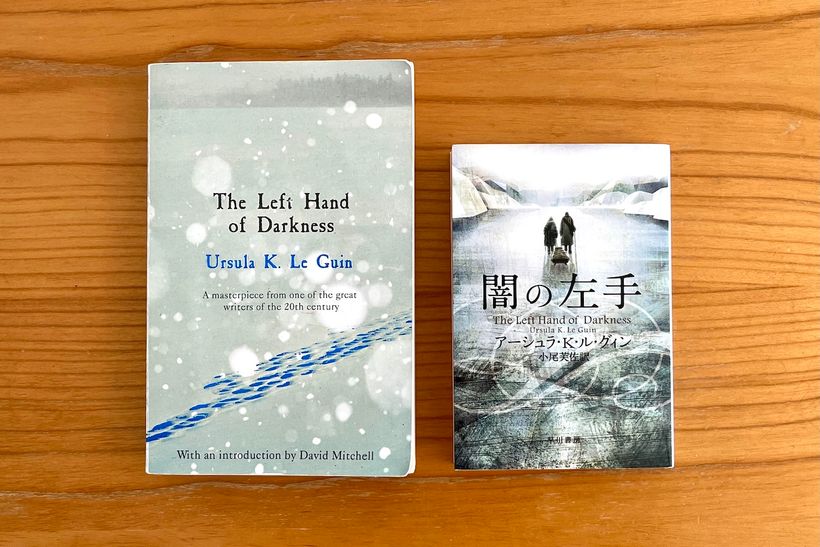しかし、その製品が使われる期間や価値を考えるとバランスが取れるはずで、その視点のものづくりにおいては、「サステナブルな素材かどうか、どれだけプラスチックの使用を減らすかという議論が見当違いである」と続けます。
 ヒーンは現在、自分のデザイン業務の傍ら、インドの現代性と伝統を編み合わせ未来へ向けて提案する家具ブランド「SĀR(サー)」のクリエイティブコンサルティングも行っています。彼らとの関係も、「良くできたもの」をつくるための時間の捉え方を変えたと言います。
ヒーンは現在、自分のデザイン業務の傍ら、インドの現代性と伝統を編み合わせ未来へ向けて提案する家具ブランド「SĀR(サー)」のクリエイティブコンサルティングも行っています。彼らとの関係も、「良くできたもの」をつくるための時間の捉え方を変えたと言います。「インドで家具をつくるとなると、ヨーロッパでは機械が当たり前の作業も手で行われたり、あるいはそもそも存在しないものを一からつくる・教えるといった作業が必要になり、これまで数年でつくれると思っていたものを10年スパンで考えるようなことが多々ある。その中でヨーロッパでは経験できない手仕事の価値や、『即席で創意工夫された解決策』を示すヒンディー語『ジュガード(Jugaad)』のようなインド文化特有の『完璧さへの楽観性』といった新たな視点を得ることができました」
 アメリカ、フランス、イタリア、インドと異文化間の経験が豊富なヒーンに、異文化的経験がどう彼の実践や時間のコンセプトに影響を与えているかを尋ねると、「忍耐強くなることの価値を学んだ」と言います。
アメリカ、フランス、イタリア、インドと異文化間の経験が豊富なヒーンに、異文化的経験がどう彼の実践や時間のコンセプトに影響を与えているかを尋ねると、「忍耐強くなることの価値を学んだ」と言います。若いうちは、早くプロジェクトを達成すること、製品を世に出すことに躍起になっていた。しかし、スチールケースでの長期スパンでのものづくり、グルチッチでの最善が見つかるまで何百案も繰り返し練られるデザイン作業、そしてインドでのまったく異なる時間感覚での構想などを経て、品質と象徴を兼ね備えた製品をつくるためには忍耐強い繰り返しの作業が必要であり、そのために信頼関係を築くことが不可欠であると気付いたそうです。