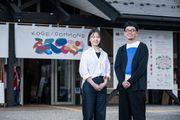破壊的イノベーションがNGな医療分野で取るべきアプローチ
アイリスが目指す世界を実現するには何が必要なのだろうか? ここからはIBMで医療分野のデジタル化を促進する金子達哉氏も含めて会話に参加してもらい、金子氏が捉える医療×テクノロジーの現状、事例を紹介してもらう。また、沖山氏は医療分野では破壊的イノベーションを起こしてはいけないと述べる。その理由は何か? また、医療分野でイノベーションを推進していくために大事なことはなんなのだろうか?金子:「医療分野を2016年から担当しておりますがしておりますが、”便利”だけではなかなかスケールしないことを実感しています。何かしらの仕組みに組むこみそれがない、ある意味、強制力が無いと普及率が上げられない。その両輪が必要だと最近感じています。と、同時に必要性を理解していただけると使っていただける事例も出始めています。たとえば、IBMが順天堂大学と組んで作っている医療メタバースですが、豊島区高齢者クラブ連合会からのリクエストで、約300名に使っていただき新たな医療の可能性を体感してもらえました。病院に行く手間が省ける上に、病院とのコミュニケーションも今までと違う形で取れることに喜び、メタバース内で病院関係者と老人会の方がハイタッチをするシーンなども見受けられました。また、ご自宅の様子を生成AIを使用して把握するようなトライアルも始めています。病院での診察をおえて、次の診察までの間の様子などを生成AIが「お体いかがでしょうか?」とコミュニケーションを取り状態を記憶する。そのコミュニケーション上で副作用の症状の可能性が検知されればさらに質問をしてそれをAIが医師か看護師に伝える。医師が家庭での状況も把握できるようになると、次の問診の際に患者がいちいち前回の診察からの家庭での変化などを記載しなくても、適切な診察を行うことができるようになる。そういうことがテクノロジーを組み合わせて医療の現場でも可能になってきているので、必要ならば使っていただくというアプローチも大事かと考えております。
そして、この取り組みは、まさに沖山さんの起業の原体験の話しにもつながります。東京や大阪以外の専門医がそこまでいない環境でも、このようなアプリが地域にも展開されれば、医療のアンバランスを解消してくれると思います。IBMでは、このような取り組みを、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪国際がんセンター等と連携して現在進めています。今は高度化する医療の中で、説明する時間のとれない医師の負担を軽減するため、そして診察以外の時間でも患者さんに質問していただけるようにして医療行為の満足度をあげてもらうための生成AIアプリケーションですが、将来は、必ずしも病院にいって病気を治すのではなく、自宅で治す世界が広がっているかもしれません。