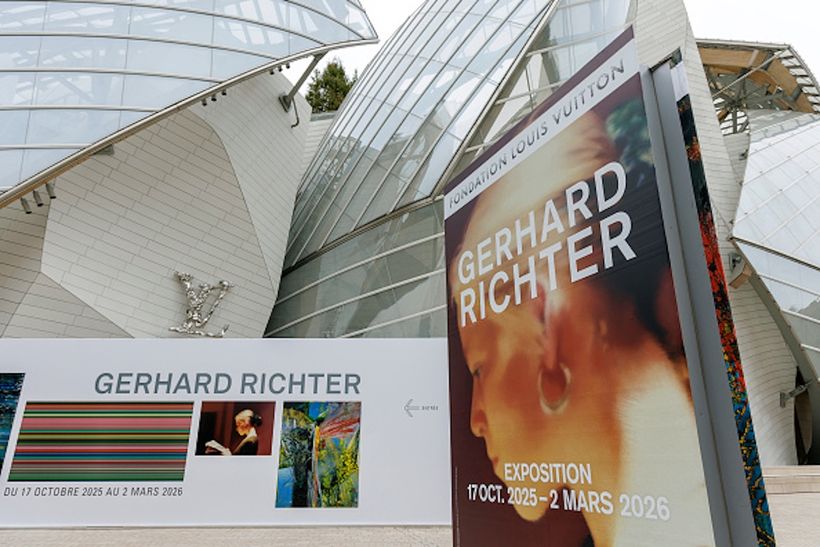ビューティーサロンからストリートフードの厨房、あるいは料理教室と外から見られるのを意識した場所は数多くあります。建築事務所で設計作業の様子を「公開」しているところさえあります。あるいはイベントで機織りや木工などの作業を聴衆に見てもらうことはよくある手段です。観光地であれば、陶芸の工程の可視化に驚きません。しかし、冒頭の例は観光地区ではない街中です。

これらの多くはマーケティング手法の一つと見なされてきたように思います。いや、見なされていたというよりも、当事者もそういうつもりであったと表現すべきでしょう。狭い作業現場も「もう、あれこれ取り繕うよりも外に見せるしかしないか!」という言い訳を含めて。
工程をガラス張りにするのが循環経済を実現するうえで必須だ、というロジックのうえにのっている場合が今の潮流でしょう。どの材料をどこの誰がつくり、それを誰が使い廃棄したのか? これが可視化されるのが循環経済の基盤になります。ただ、前澤さんの言葉を使えば「義務」の重さを感じます。
でも、そのプロセスが実は軽みがあって美しいとさえ思えてくるタイミングにきているようです。よって、プロセスの可視化が美しいと評価され、それがラグジュアリーの価値を引っ張る。この見込みを否定する材料を、ぼくは何も持っていません。
肯定する材料はさらにあります。対象の動きを表すために撮影した結果、一部ぼやけた写真がそのままインスタに投稿されているのも証のひとつです。
静的であることや閉じたことに美しさがありますが、動的で開かれたことに美しさをみたいという衝動のようなものもあるでしょう。完成され過ぎたものへの満腹感がプロセスの可視化をより後押しするかもしれませんが、理性的な動機もあると思います。あらゆることは直線的ではなく螺旋状に進むという認識の広がり、未完であることの大切さといった思考パターンや作業プロセスの範疇の話です。