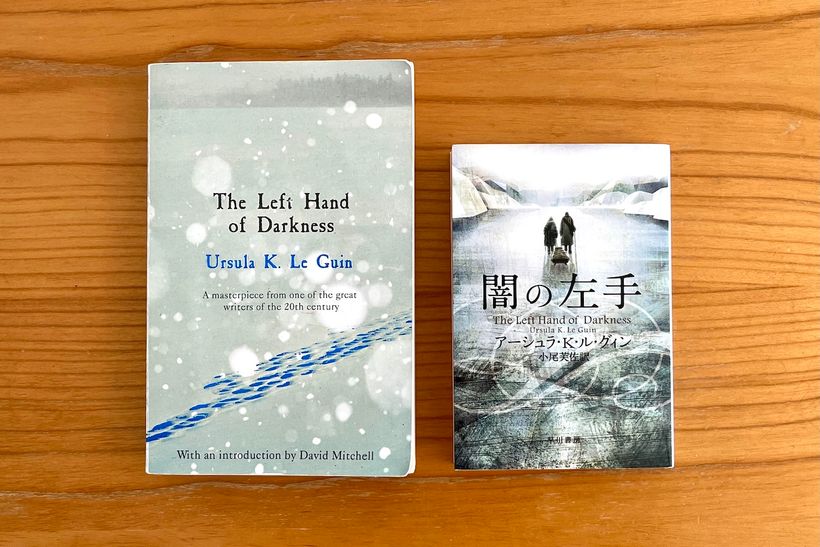その道筋を照らすキーワードとして「世代」と「relatability(関連や共感のしやすさ)」を提案したいです。今回はそのアイデアをくれた1冊の本をご紹介します。
それは、本連載の執筆を始めるにあたり、大学時代の恩師・長澤忠徳先生にすすめられた、ピーター・ドーマーの『The Meanings of Modern Design(モダンデザインの意味)』(1990年)です。ドーマーは英インデペンデント紙が追悼記事で「最も特異で闘争的な現代作家の1人」と評した作家で、20世紀のデザインと応用美術の社会的影響に常に関心を持っていました。
本書では、デザイナーと消費者の複雑な関係や20世紀以降のデザインの象徴性・道徳性といった側面を考察しています。特に独創的なところは、技術の進歩によってデザイナーがスタイリストを担うようになったという主張を「above the line / below the line」という区別で説明していく点です。簡単に訳すとしたら「表面化 / 水面下」となりますが、ドーマーはキッチンスケールを例に挙げます。
人が手で2つのものの重さを比べる行為が直接反映され、道具が何をするかがカタチから理解できた昔のスケールに比べ、現在のスケールは、機械部分を小さくする技術やプラスチックという強固な新素材の登場で、外見からは「滑らかで平らなケースに入ったもの」になりました。機能がわかる部分が水面下になったことで、表面化では、道具の個性よりも、その製品のスタイルが時代の建築や生活様式に「合っていること」を主張するような表現が見られるようになった。
彼はこのような事例を次々とあげ、スタイルがエンジニアリングと分かれるようになったことで、デザイナーは製品における「どこに親近感を向けるか」の意思表示を視覚的に操作する役割を持つようになった、という見解を展開していきます。
ドーマーはスタイリングを「文化が仕事、余暇、制度といった生産的なパターンにうまく秩序づけられていることを示す視覚的な言語」と定義し、「秩序を保つことは、文化を継続させるだけでなく、文化が拡大し進歩することを保証する」と主張します。つまり、スタイリングが時代の変化に沿った表現で文化を発信する手助けをし、それによって文化がつながれ、発展していくと言うのです。