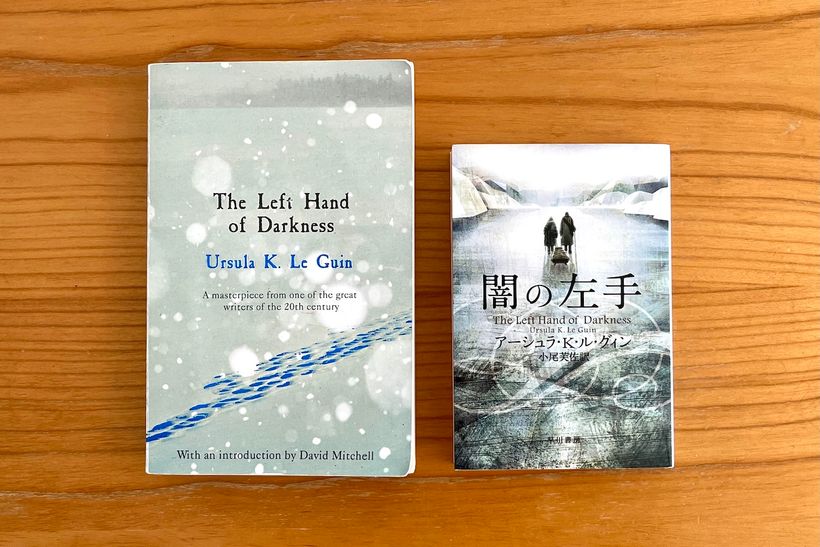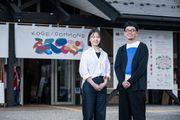世界の仕組みを一瞬にして悟った気になりました。政治、宗教、経済の各領域の権威的な位置を占める場を自由自在に動き回っているのだな、と。「動き回れる」と表現した方が的確かもしれません。
世界の仕組みを一瞬にして悟った気になりました。政治、宗教、経済の各領域の権威的な位置を占める場を自由自在に動き回っているのだな、と。「動き回れる」と表現した方が的確かもしれません。しかし、権威的なステイタスがなくても日常性の次元を自在に「動ける」ことを強調したのが、中野さんが触れている民藝であったのではないかと思います。もともと19世紀後半、英国でウィリアム・モリスが主導したアーツアンドクラフツ運動が遠く日本に伝播して民藝運動というかたちになったことも勘案すると、「日常性」は鍵となる言葉になるでしょう。
そして、審美性や社会的な包摂を求めたウイリアム・モリスを新しいラグジュアリーのモデルとして『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』のなかで紹介しているので、ラグジュアリーと民藝のつながりを探るのは的を射ていると考えられます。
そこで、ふと思い至ります。
フランスのラグジュアリーは、18-19世紀の産業革命で生まれた新興ブルジュアが貴族的なスタイタスを欲しがるとの需要が動機として語られます。他方、イタリアは20世紀半ば以降、「日々の生活」にあるものがラグジュアリーになっています。
このイタリアのラグジュアリーの性格は今に至っても続いており、ファッションメーカーのブルネロ・クチネリがパーティーのための服よりも、日常生活で着る服にウエイトをおいてきたのも一例でしょう。しかも、ブルネロ・クチネリは新しいラグジュアリーの旗手です。また、フランス料理のフォーマルさとイタリア料理のカジュアルさの対比にもその違いは表れています。