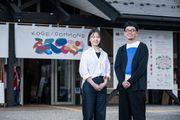シイタケ原木用運搬車には、なんと「大分県専用」まである。ベースとなる機体は約30種類だが、それぞれに仕様が異なるバージョンが存在するため、型番ベースでは200種類を超える。それでも対応しきれない顧客の要望も基本的に断らず、カスタマイズで対応していく。
「こだわりのある農家さんこそ、私たちの大事なお客様です。もともと汎用的な製品が売り上げの80%程度を占めていましたが、最近は6割前後に。年々、カスタマイズ品が増えてロングテールのしっぽが長くなっています」

市場ニーズに合わせて柔軟にピボット
顧客ニーズに柔軟に対応する姿勢は、包行家の歴史とも関係している。ルーツは刀鍛冶。昭和初期は軍刀をつくっていたが、戦後は需要が消滅する。包行の祖父は包行農具製作所を立ち上げ、鍛冶の技術で鎌や鋤などを製造販売した。
しかし、農機具も機械の時代に入り、鎌や鋤は売れなくなっていく。一方、農家とのつながりから次のニーズは見えていた。耕運機(ティラー)の普及により、ティラーにつないで引っ張るトレーラーの需要が拡大。
その製造を始めたことをきっかけに、トラクター用トレーラー、そして自走型トレーラー、つまり運搬車の製造へと発展していく。
「1980年代に運搬車のなかでも稲わら用の需要が高まり、ピークの90年には年間2万5000台売れました。しかし、コンバインの登場で、稲わら用運搬車は需要が急速に縮小します。
落ち込みをカバーするため、父の均が93年に乗用草刈機事業をスタート。運搬車はさまざまな用途に特化することで下げ止まる一方、乗用草刈機は『草刈機まさお』がヒットしました。現在は台数ベースで半々。単価は乗用草刈機のほうが高く、売り上げベースでは乗用草刈機が6割を占めていて、会社の経営を支えています」
キャニコムの歴史は、自社のシーズにこだわって事業展開するのではなく、その時代の市場に合わせて柔軟にピボットしてきた歴史だった。その姿勢が、現在の個々の商品開発にも表れているというわけだ。
地方の中小企業をニッチトップの座に導いたのは、現会長の父、均の功績だ。現在は息子の良光もローカル発であることに誇りをもっているが、幼少期はむしろ地元から離れたかったという。
「父はファンキー。商品の名前は奇抜だし、営業は赤いジャケットが制服でした。当然、地元では注目の的です。運搬車『ピンクレディ』が売れたので、道を歩くと『ピンクレディの息子』と指をさされる。居心地が悪かったですね」
願いが通じたのか、中学高校は遠く離れた全寮制の学校へ。大学も東京に進学した。ホームセンターに内定が決まっていたものの、卒業判定で不合格になり、フリーターに。地元に戻って家業を継ぐ気はさらさらなかった。