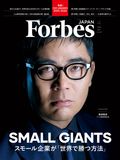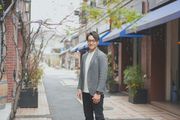にもかかわらず、フォボスは特に不可解だ。
チュクによると、フォボスの公転速度は火星の自転速度より速いため、西から昇って東に沈む。そのため、フォボス自体の重力で火星の表面がわずかに変形することにより、徐々にフォボスの軌道が減衰し、火星の表面により近づくことになるという。
問題は、フォボスが内向きに移動している期間はどれくらいか、どの場所からなのか、そしていつ形成されたのかだ。
チュクによると、これに関しては2つの異なる説がある。1つは、フォボスが数十億年前にダイモスの比較的近くで形成されたとする説で、もう1つは、火星では衛星が破壊されてできた環から新たに衛星が形成されるサイクルを繰り返しているとする説だ。
繰り返されるサイクル?
チュクによると、フォボスは現在、火星に向けて螺旋を描いて降下しつつあり、やがて火星の重力によって粉々になり、数千万年以内にデブリの環になる。
このプロセスは何度も繰り返される可能性がある。前世代の螺旋降下する衛星が崩壊するごとに、新たなデブリの環が生じ、そこからまた新たな衛星が形成されるわけだ。これは、フォボスとその前世代の衛星はそれぞれ比較的寿命が短いことを意味する可能性が高いと思われる。
寿命の最終期にあるフォボスを捉えたように思われる理由はこれで説明できるだろうと、チュクは述べている。
まとめ
チュクによると、フォボスとダイモスの現在の軌道だけに基づくと、フォボスの年齢や、フォボスの軌道が時間とともにどのくらい変化したかについてはわからない。ダイモスの年齢が数十億年なのはほぼ間違いないが、フォボスの年齢は、40数億年以上か、または約1億~2億年のどちらかだという。どちらのシナリオもあり得ると、チュクは指摘した。
科学的により興味深いのは、どちらの衛星だろうか。
チュクなら、ダイモスの方を選ぶという。フォボスとは違って、それほど移動していないだけでなく、ダイモスの軌道傾斜角が、過去に火星に別の衛星が存在していた唯一の証拠である可能性があるからだ。

だが、チュクが指摘しているように、最初により多くのことが解明されるのはフォボスの方である可能性が高い。なぜなら、2026年に日本の火星衛星探査計画MMX(Martian Moons eXploration)の探査機が打ち上げられるからだ。MMXが成功すれば、NASAが火星表面のサンプルを地球に持ち帰るよりもおそらく数十年先立って、フォボスのサンプルを地球に帰還させることになる。