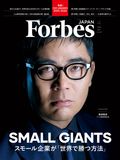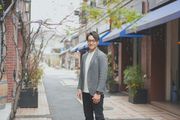またパートナーや子どもの有無にかかわらず、女性は男性よりも頻繁に「感情労働」──つまり、クライアントや同僚・同業者に対し、上記のようなコミュニケーションにおいて「潤滑油」になること──を求められるのである。英国では、クリエイティブな分野で学位をとった女性はフルタイムの仕事を確保しやすい一方で、賃金は男性より安いことが多い。また、キャリアの発展や成功に不可欠なリソース、機会、ネットワークへのアクセスに、女性だからという理由で苦労をすることもある。
音楽産業から見る、クリエイティブ労働をめぐる課題
このような問題はクリエイティブ産業の至るところで顕在化している。音楽産業を例にとってみよう。音楽産業界は、アーティストに加え、制作、配信、出版、広告、舞台芸術などさまざまなクリエイティブな仕事によって構成されている。そしてすでに指摘されているように、そのアクターたちは多くがフリーランスとして仕事に従事しており、労働環境は不安定なものが多い。音楽ライター、サウンドエンジニア、舞台照明、ラジオ番組のディレクターなど、さまざまな音楽界のクリエイティブ労働に関わる人々の多くはその立場は不安定であり、前述のような、やりがいはあるがリスクと拘束をともなう仕事の関係において、なんとか「声がけリスト」に入るために自らの創造性を磨き、それを「うまく」掲げていかなければならない(繰り返すようだが、「声がけリスト」は多くの場合ジェンダー化されている。子どものいる女性ミュージシャンがイベントのセットリストや、「遠征」に声がかからない、という話は頻繁に聞く)。
ここで、前述したような自己責任という概念は、労働権に関する知識の欠如によって強固なものとなる。音楽界におけるエスノグラフィーの研究のなかで、中根多恵は、音楽業界のアクターたちは自分たちの「芸術家」としての地位と、労働者としての地位を切り離す傾向があると指摘している。
そこには、「労働」が経済的成果、つまりお金を伴うものとする考え方がまずあり、そして芸術がそのような価値観でとらえられてはいけないという美学があるのかもしれない。その結果、中根が指摘するように、「労働者の権利」や「労働者の動員」という概念がこれらのアクターの心に響かない状況を生んでいる可能性もある。
余談だが、実はこの状況は研究者にもあてはまる。クリエイティブ労働とはみなされていない研究活動だが、前述のような過酷な状況は現代の、大学などのパーマネントのポストに就いていない研究者たちもまさに直面している環境なのだ。