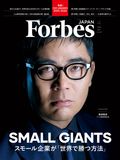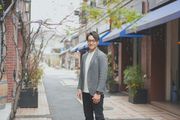これらクリエイティブ労働をめぐる状況の根底にあるのは、雇用者、クライアント、同僚、そしてヒエラルキーの上部にいる「お世話になっている先輩」たちとの、市場と古びた慣習を巡る支配-被支配の権力構造である。
代替策はあるのか──フランスの例──
このような状況を改善する方法はあるのだろうか。もちろん、すでにさまざまな法人や非営利団体がクリエイターやアーティスト、研究者の活動をサポートすべく数々のプロジェクトを立ち上げている。また、近年日本の政府も芸術振興政策の枠組みを強化し、60億円の資金を投入してクリエイティブ活動を3年間支援する政策などを掲げている。しかしながら、公的な政策に特化すると、例えば政府は民間団体に比べより巨額の資金や制度を投入できる機関であるにもかかわらず、クリエイティブな活動支援には力を入れる一方で、クリエイターやアーティストが安心して生活できるような環境づくり、つまりかれらの労働者としての権利を保障するよう働きかけるまでには至っていない。ここで、他国のケースに目を向けてみたい。例えば筆者が在住しているフランスでは、アンテルミッタン・ デュ・ スペクタクル(Intermittent du spectacle)という公的な雇用保障制度がある。この制度は、舞台芸術や視聴覚芸術の世界においてプロジェクトごとに雇用されるアーティストや技術者が、プロジェクトの待機期間、つまり報酬が発生しない期間に失業手当を受けることができるように設けられている。対象者は舞台芸術または視聴覚部門で、アーティスト(俳優、ミュージシャン、ダンサーなど)または技術者(舞台監督、音響技師、照明技師など)であることが条件だ。
この制度は、舞台芸術の分野において仕事がプロジェクトベースであり、アーティストや技術者は一定期間のみしか雇用されない状況が一般的であるために設けられた。その目的は、公演や制作が行われない期間でも生計を立てる手段が必要であるアーティストや技術者の生活の権利を保障することである。