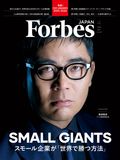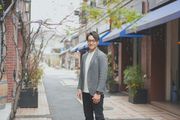公園をイメージしたオープンで明るいスペースは、老いのネガティブなイメージを払拭する。
公園をイメージしたオープンで明るいスペースは、老いのネガティブなイメージを払拭する。 科学コミュニケーター園山由希江さん。
科学コミュニケーター園山由希江さん。老いパークの企画・調査を担当した、科学コミュニケーター園山由希江さんは、企画経緯を次のように話す。
「一般的に科学館が取り上げる未来というと、AIや宇宙開発などスケールの大きな科学技術をイメージすると思います。でも30年後や50年後といった未来では、私たち個人の身体も変化している。その過程を科学館として取り上げることは、重要な未来の“自分ごと化”です。
さまざまな議論を経て、新たなビジョンと共に改めて未来を考え、一人ひとりの足元に必ずある未来として、老いを取り上げることが決まりました」
 入り口正面には、「老いを体験しよう!」とマップが設置されている。これほどPOPな老いの提案を未だかつて見たことがない。
入り口正面には、「老いを体験しよう!」とマップが設置されている。これほどPOPな老いの提案を未だかつて見たことがない。科学館における老いをテーマとした常設展示は、日本ではほとんど例がないと言っていい。展示を設計するにあたり意識したのは、老いを悲観・敬遠するのではなく、楽しみながら能動的に学べるようにすることだ。
「科学の視点で言えば、老いは経年変化です。良いものだとか悪いものだとか決めつけるものではありません。老いを考える場所の名称として、老いパークというストレートなネーミングにしたのは、固定概念に捉われず、老いについてオープンに考える場所にしたかったからです」
 カラフルで多幸感があり、どれから体験しようかと迷ってしまうほどワクワクする。ここはまるでテーマパークだ。
カラフルで多幸感があり、どれから体験しようかと迷ってしまうほどワクワクする。ここはまるでテーマパークだ。老化現象を擬似体験する、と文字だけで見るとふと恐ろしく感じるかもしれない。しかし実際に体験してみると、見て聞いて触って、楽しい感情とともに体験することができ、訪れる前に抱いていた老いへの恐怖を忘れていた。取材日には小学生が団体で訪れていたが、彼らと並んで老いを体験するのはとても新鮮なひとときだった。
 「サトウの達人」は、受付窓口で「サトウさん」と呼ばれたときだけボタンを押すゲーム。高音域の子音(サとカなど)の聞き分けにくさから、耳の老化を体験する。
「サトウの達人」は、受付窓口で「サトウさん」と呼ばれたときだけボタンを押すゲーム。高音域の子音(サとカなど)の聞き分けにくさから、耳の老化を体験する。 近場のスーパーまで歩いていくシミュレーターで、運動器の老化を疑似体験する「スーパーへGO!」も盛り上がっていた。足首に重りをつけた状態でシルバーカーを押していくが、なかなか思うように進めない。
近場のスーパーまで歩いていくシミュレーターで、運動器の老化を疑似体験する「スーパーへGO!」も盛り上がっていた。足首に重りをつけた状態でシルバーカーを押していくが、なかなか思うように進めない。