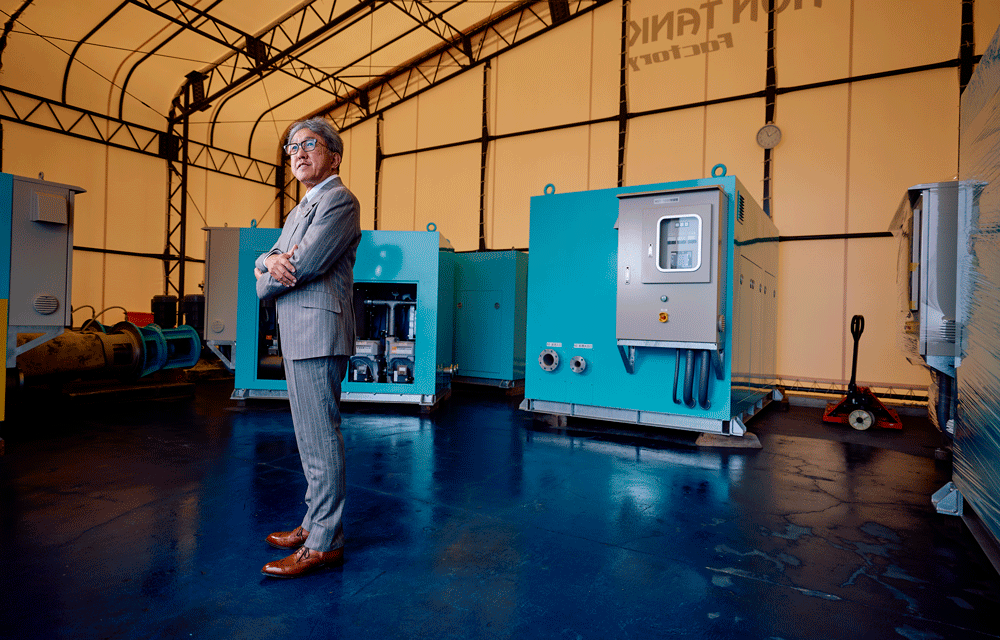「レディ・プレイヤー1」は、基本的には仮想空間で繰り広げられる宝探しの物語だ。眩いばかりのCG映像で展開されるVRのシーンも見どころだが、この作品を観賞するうえでのもうひとつの楽しみは、次々と登場する映画やアニメやゲームのキャラクターたちだ。
この映画の原作は、アーネスト・クラインが2011年に発表したSF小説「ゲームウォーズ(日本ではこのタイトルで2014年に刊行。原題は「READY PLAYER ONE」)」。 作品中に実在の映像やアニメの登場人物やアイテムが多数登場するため、権利取得の煩雑さから映画化は困難なのではないかと言われていた。
事実、クライン自身が映画化のために最初に書いたシナリオは、単なるゲーム内での宝探しになっていたという。そこで登場したのが、巨匠スピルバーグだ。実は、原作小説のなかではスピルバーグの映画や彼自身も取り上げられており、重要な役割を占めている。クラインの小説はスピルバーグに対するリスペクトに満ち溢れており、それをスピルバーグ自身が監督するのは自然の成り行きだったにたがいない。
ただ、映画化にあたっては、自分にまつわるものは「バック・トゥ・ザ・フューチャ」に登場する車「デロリアン」以外は極力削り、小説に登場するさまざまなキャラクターを取り入れ、さらに新たに追加もして、100個を数えるほど登場させている。
例えば、キングコングやアイアン・ジャイアントなどのアメリカ生まれのものはもちろん、ガンダムやメカゴジラ、「AKIRA」の金田のバイクからハローキティまで、おなじみの日本製キャラクターも作中に現れる。
筆者的には中盤で登場するスタンリー・キューブリックの「シャイニング」の再現場面に惹きつけられた。映画のなかでは、主人公たちに提示される謎解きの単なる「引っ掛け」として登場するのだが、かなり趣向も凝らされており、物語の本筋ではないのに、キューブリックに対するオマージュなのか、いちばんの時間が割かれていたように思う。
映像は現実と仮想現実が交互に入り交じるかたちで描かれているため、観ていて多少の混乱を引き起こすかもしれないが、そのあたりの整合性はあまり気にせず、この「キャラクター大行進」を楽しむのが、この作品の観方として適切なのかもしれない。
ゲームのなかで進む宝探しの物語はけっして複雑なものではない。人々が「オアシス」に向かわざるを得ない社会的背景も、ナレーションによる説明だけで、ほとんど描かれることはない。仮想現実とは、つまりは人々の心のなかで起こっていることであるのに、肝心の登場人物たちの内面もあまりうかがい知ることはできない。
難を言えばいろいろあるのだが、それらを補って余りある見事なCGと、次から次へと登場する多彩なキャラクターに、スクリーンから目を逸らすことはできない。そう、もしかしたら、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオのアトラクションを楽しむように観ればよいのかもしれない。
原作小説のなかでは重要な役割で登場するウルトラマンが、海外版権の訴訟問題(24日に判決が出た)もあり、許諾が得られず、その勇姿を見ることができなかったのはやや残念でならない。聞くところによれば、スピルバーグ監督は「もし続編がつくられるようなら、ぜひウルトラマンは登場させたい」と言っているという。シュワッチ。
映画と小説の間を往還する編集者による「シネマ未来鏡」
過去記事はこちら>>