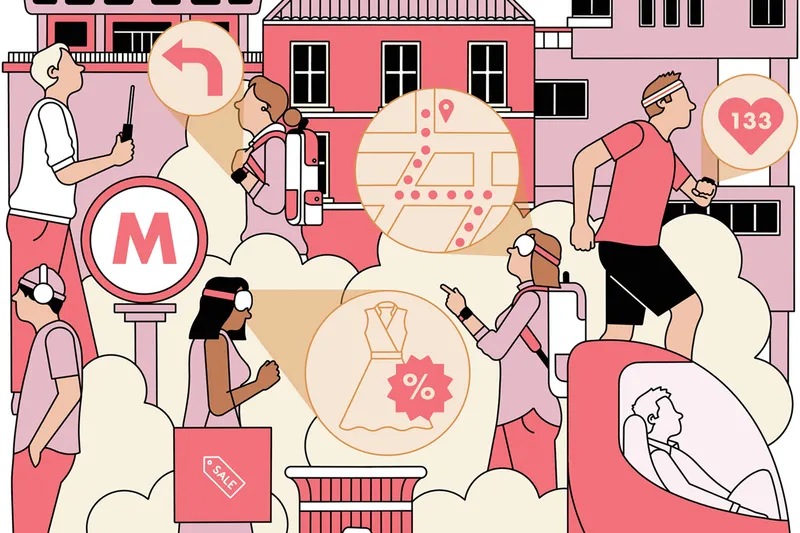例えば昭和から続くレトロな喫茶店やスナックは、地元の人だからこそ知るストーリーを話しながら案内することで、ツアーに参加した人は感動し、街に愛着をもってくれます。案内役の地元の人はその反応がうれしくてどんどんと語るようになり、ツアーを通じて熱海の魅力を再認識し、自信を取り戻していきます。この好循環によって、観光客でも地元の祭りに参加できるようになるなど、どんどんと街はひらかれていく。そして多様性と寛容性が高まることによって名物の祭りも継続できるのです。
武邑:ベルリンから北へ1時間ほど車を走らせたところに廃村があるのですが、不思議なことに、そこを再興したのは日本人コミュニティでした。地元民の高齢者比率が非常に高く、あたりに何もない廃村でしたが、どことなく日本的なギャラリーやカフェがつくられたことで、いまではベルリンから人が集まり、ヴィム・ヴェンダースもやってくるほどの注目度を誇ります。ベルリン在住のふたりの日本人女性は、地元の人々と親交を深め、意見をくんだうえで、手探りながらも2年で施設の原型をつくったといいます。
その日本人コミュニティは、何もない村だからこそさまざまな可能性を見いだし、新しいコラボレーションや祭りを生み出すことができたのではないでしょうか。「祭り」という日本語に、“停滞した「間」を「つる」”という語源があるように、日本人は古くから人々は間をつる(祭る)ことで何もないところやたるんだところに緊張を生み出し、持続的にコミュニティの結束を高めてきました。この国民性は、人と人・人と場をつなぐ場づくりに長けているのではないかと思うのです。
花井:土地の文脈を守りながら寛容性を生んでいるポルトガルの事例、定住性に特化したソロメオ村と石見の事例、さらにはマレビトによって街が再生した熱海とベルリンの事例。昨今、個人の時代として分散型自律の働き方も推奨されていますが、どの事例を取ってみても、誰かと顔を突き合わせての対話の連なりが人生を左右することには変わりないことがわかります。リアリティが溶け出してしまうビッグ・フラット・ナウ時代では、これまで以上に人間主義的な組織や地域活性の重要性が高まっていくのでしょう。