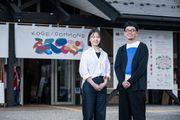伊藤 : 皮肉なのは、トランプが、そうした不満や怒れる人々を結集することで勝ったにもかかわらず、その政策綱領が彼らにマイナスに働くという点だ。
スティグリッツ : グローバル化で失業した人々を支援すべきだと言ってきたのは民主党であって、共和党は反対してきた。だが、トランプは、ある意味で聡明だった。彼らの不満をすくい上げ、その声に耳を傾けた。「真実」にとらわれることなく、実現できようができまいが、構わず言いたいことを言った。まるで、お金が天から降ってくるかのように。結果的に、そうしたやり方が選挙では奏功した。
伊藤 : 米メディアは、事実関係をチェックし、批判するという使命を果たしたが、有権者にはその声が届かなかった。なぜなのか。
スティグリッツ : 理由は3つ。まず、米国の教育レベルの低さ、そして、独特な見解を流す(保守派の報道番組)フォックス・ニュースの影響だ。3つ目が、トランプのようなデマゴーグ(扇動政治家)を生み出してきた米政治の伝統である。
世界経済の歪みは「政策の結果」
高野 : 次に、今後の話に移りたいと思います。世界経済では、低金利や格差、反グローバル主義などの問題が挙げられますが、利上げの可能性や格差について、ご意見をお聞かせください。
スティグリッツ : まず、そうしたものは、どれも米国の政策の結果であって、不可抗力ではないと言っておきたい。これほどの低金利が続いているのも、一つには、財政政策という選択肢を放棄しているからだ。もっと財政出動を行っていれば、金融政策への依存度が減っていた。インフラ投資プログラムを行い、金利を引き上げるのも一考だろう。低金利が経済をゆがめるという批判には賛成だ。
低金利は、雇用が伸びないままの景気回復を招くという懸念もある。企業が、資本集約型であるテクノロジーに投資する(ことで、労働分配率が下がる)からだ。より財政政策型のポリシーミックス(政策の組み合わせ)を取り入れるほうが健全だ。
伊藤 : だが、(ベストセラー『21世紀の資本』の著者で仏経済学者のトマ・)ピケティは、金利が経済成長率を上回ると富裕層にプラスに働くと主張している。高金利下では、お金持ちが得をすると。
スティグリッツ : ピケティの主張は若干単純化されすぎている。彼が提案するのは、大胆な累進資本課税制度だ。富裕層の税引き収益率が経済成長率を下回れば、(格差という)問題は解決する、と。共和党が上下両院を制する米国で実現できるとは思えない。
また、資本と労働をめぐる単純なモデルでは現代の経済に対応しきれない点も指摘したい。同じ資産家でも、米短期国債の保有者と、株式を保有する富裕層では事情が違う。低金利下では国債利回りはゼロだが、株式投資のリターンは高くなる。利上げは格差解消に役立つ。
伊藤 : 08〜09年の株式市場の暴落は、貧富の差の解消に一役買ったということか。
スティグリッツ : いや、違う。たとえば、大半の米国人にとって主な資産は持ち家であるため、不動産の暴落は大打撃となった。だが、彼らの多くは株価の下落にパニックし、持ち家を底値で売ってしまった。富裕層は、持ち家の市場価値が下がってもさほど気にしないが。その意味で、(金融危機は)格差を生んだといえる。状況は好転したが、全体のダイナミクスに照らせば、非常に由々しき事態だ。