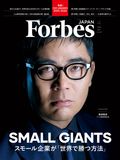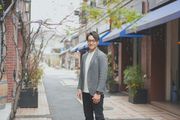自然には、予想だにしない場所で過去を保存する方法が備わっており、さまざまなところに太古の「死の落とし穴」が存在する。要するに、生物たちを丸ごと飲みこみ、悠久の時を越えてそのまま閉じこめる天然の罠だ。
なかには、膨大な数の動物の墓場になった死の落とし穴もあり、そこに残る化石化した謎が科学者を魅了し続けている。ねばねばしたアスファルトの墓場から恐竜を飲みこむ流砂まで、そうした死の落とし穴は、ときに自然が罠を仕掛け、生物が(大きな集団として)最期を遂げることをあらわにしている。
1. 米国の「ラ・ブレア・タールピット」:氷河期のねばつく罠
カリフォルニア州ロサンゼルス中心部にある世界屈指の氷河期の化石産地は、かつてありふれた光景のなかに隠されていた。
ラ・ブレア・タールピットは、更新世をのぞく窓だ。その時代にはマンモスやサーベルタイガー、ダイアウルフ(約1万3000年前に生息したイヌ科最大のオオカミ)などが北アメリカを歩きまわっていた。ラ・ブレアにはタールピットが100程度ある。タールピッド群の特別なところは、膨大な数の化石(これまでに350万個超が見つかっている)だけでなく、そうした太古の動物たちが完全に近い状態で保存されていることにある。
この場所では、数万年にわたって天然アスファルトが地表にしみだし、見かけはしっかりした地面のようだが実はそうではないプールをつくっていた。そうしたタールの罠は、捕食者たちに破滅をもたらした。
例えばマンモスのような大型の植物食動物がうっかり穴にはまり、身動きがとれなくなると、ダイアウルフやサーベルタイガーのような肉食動物を引き寄せ、今度はその肉食動物たちが罠にはまった。現在のタールピット群で得られる化石記録は、草食動物よりも肉食動物の方が多い。
ラ・ブレアの化石は、みごとな骨格が保存されているだけでなく、氷河期の捕食者たちが気候変動にどう適応していたのかに関する手がかりを科学者に与えている。『Palaeontologica Electronica』誌で2014年4月に発表されたラ・ブレアのダイアウルフの化石に関する研究により、氷河期が終わりに向かう頃にダイアウルフの大きさが縮小していたことが明らかになった。おそらくは、温暖化する世界で小型化する獲物を狩るように適応したのだろう。
一方、サーベルタイガーは大型化し、壮健になった。これは、環境の変化に伴ってさまざまなタイプの獲物を狩るように適応したことを示唆している。
だがその後、奇妙なことが起きた。1万1000年前頃に、そうした大型肉食動物の多くが姿を消したのだ。それについては、気候変動がなんらかの影響を及ぼしたと考える科学者もいるが、人類の到来により新たな競争と圧力が生じ、それが氷河期の巨獣たちの運命を決めたと考える科学者たちもいる。