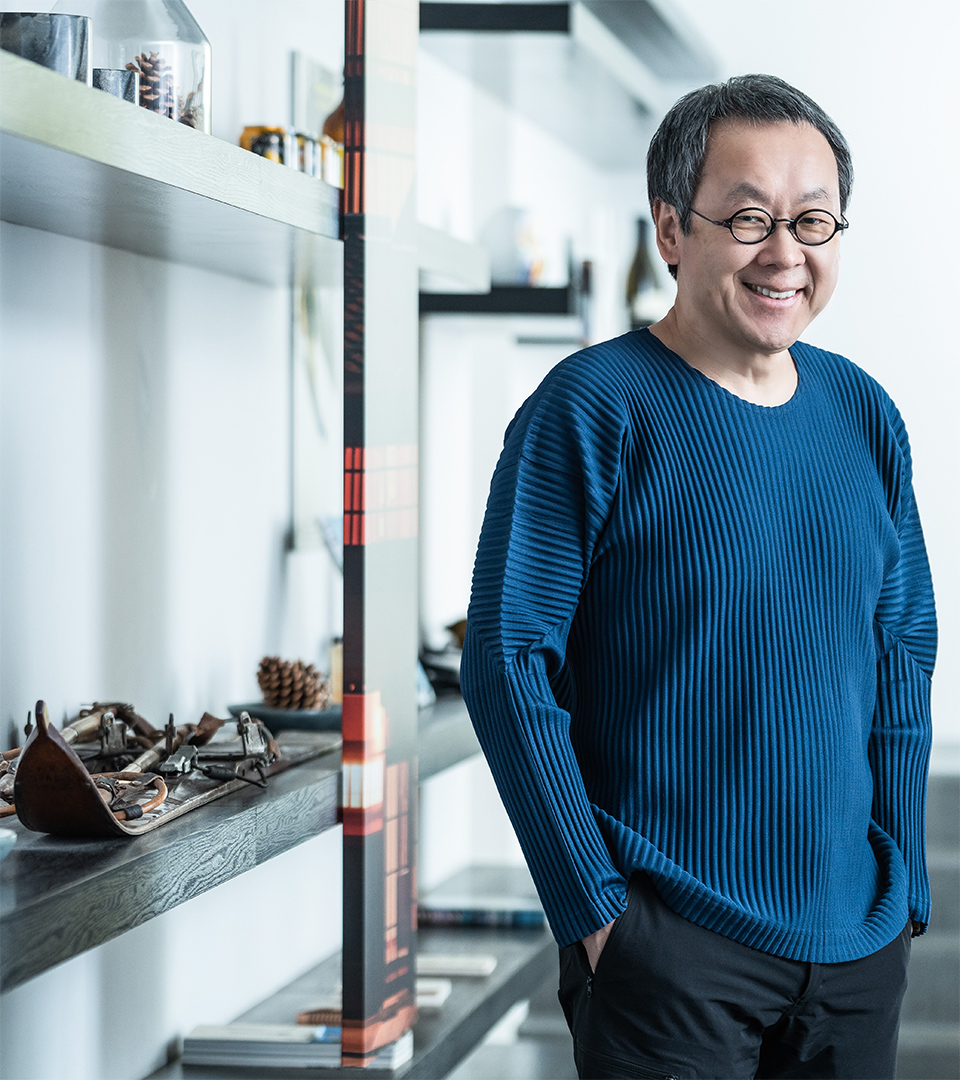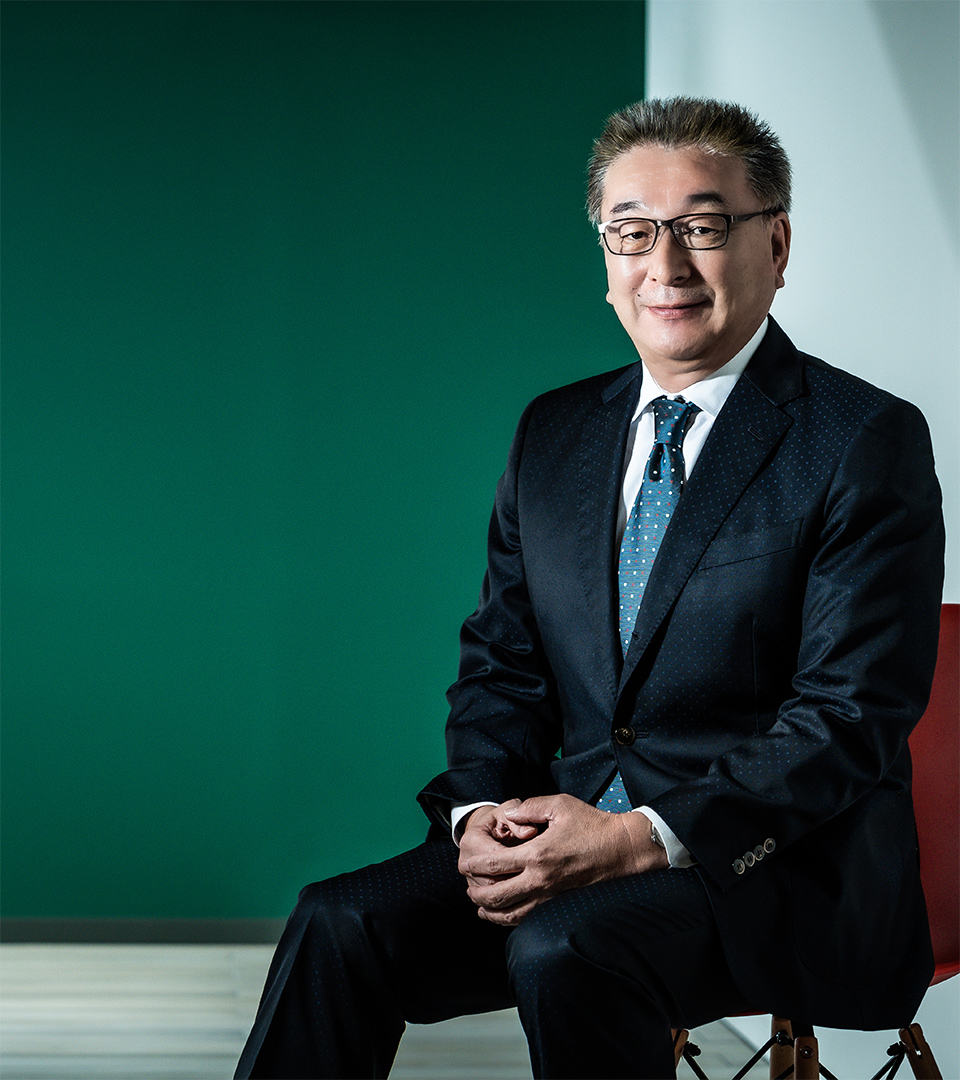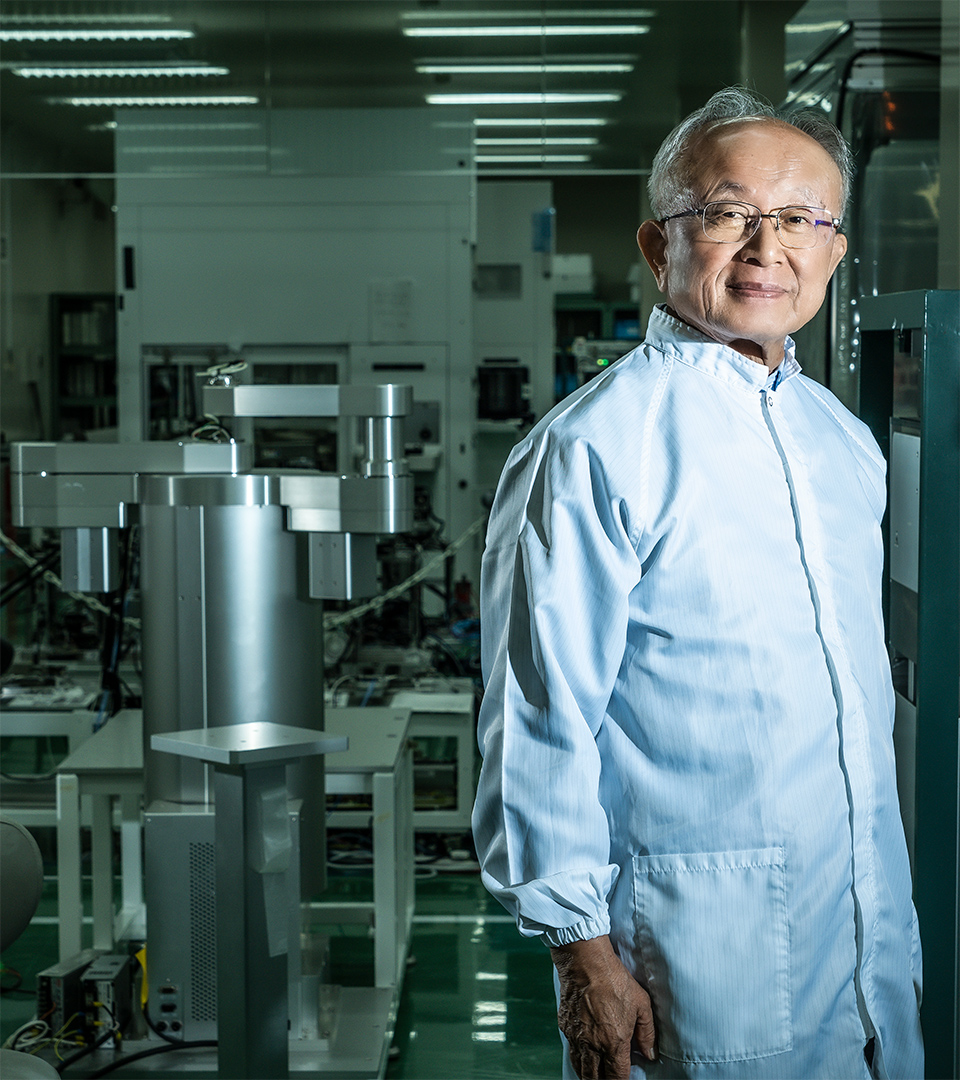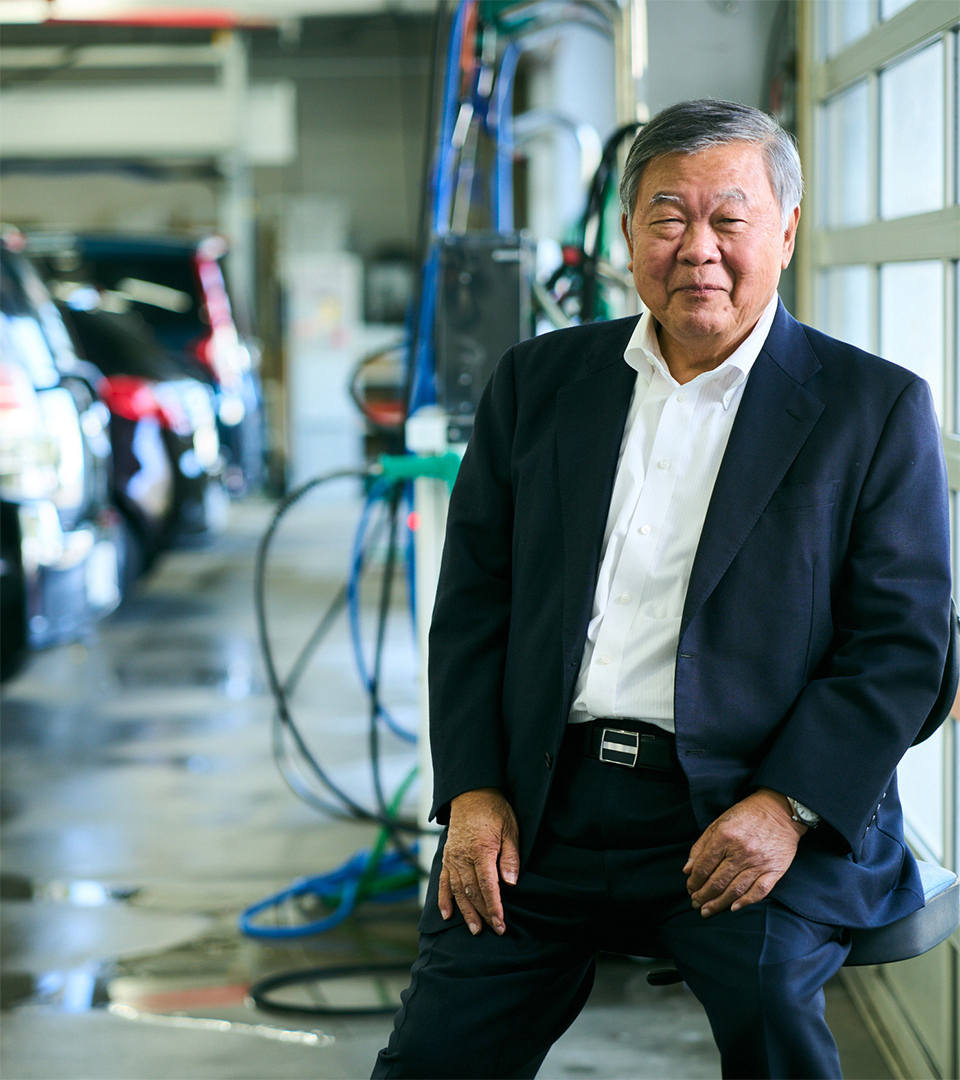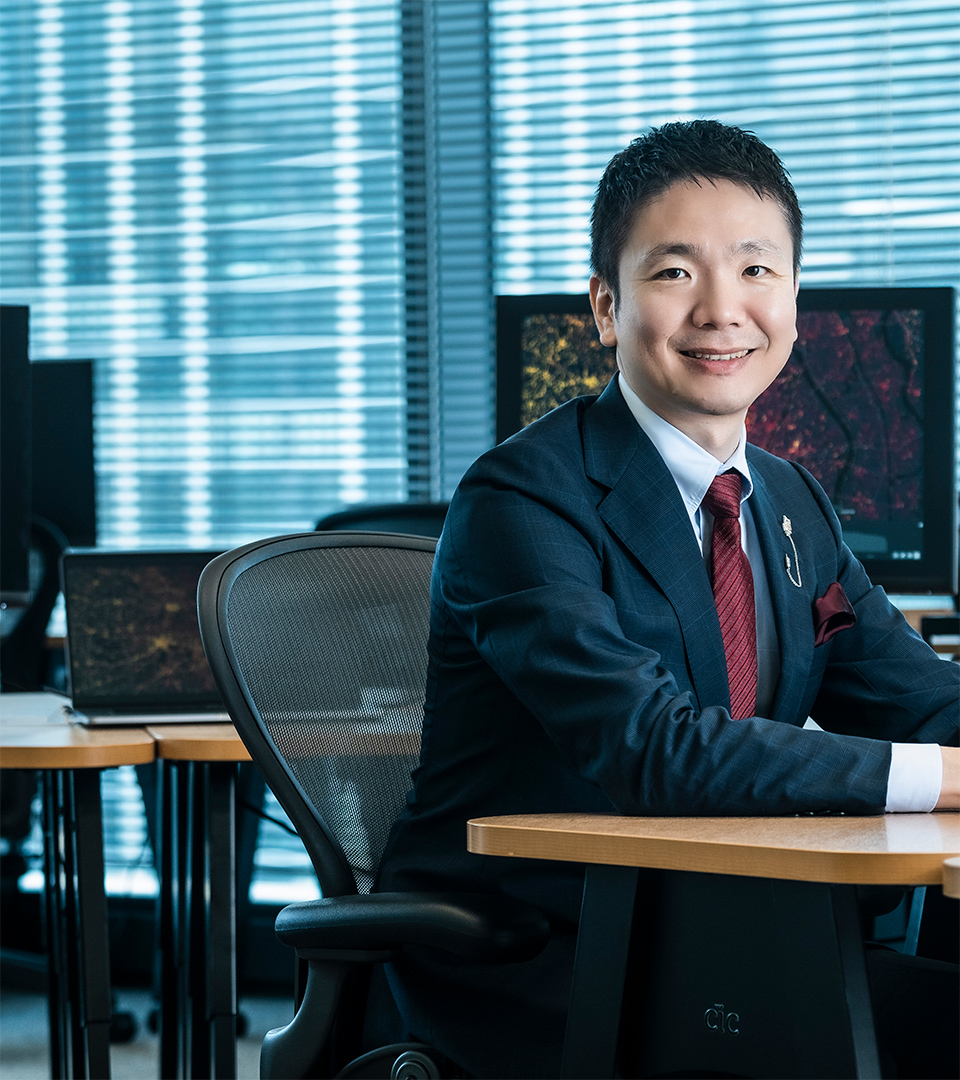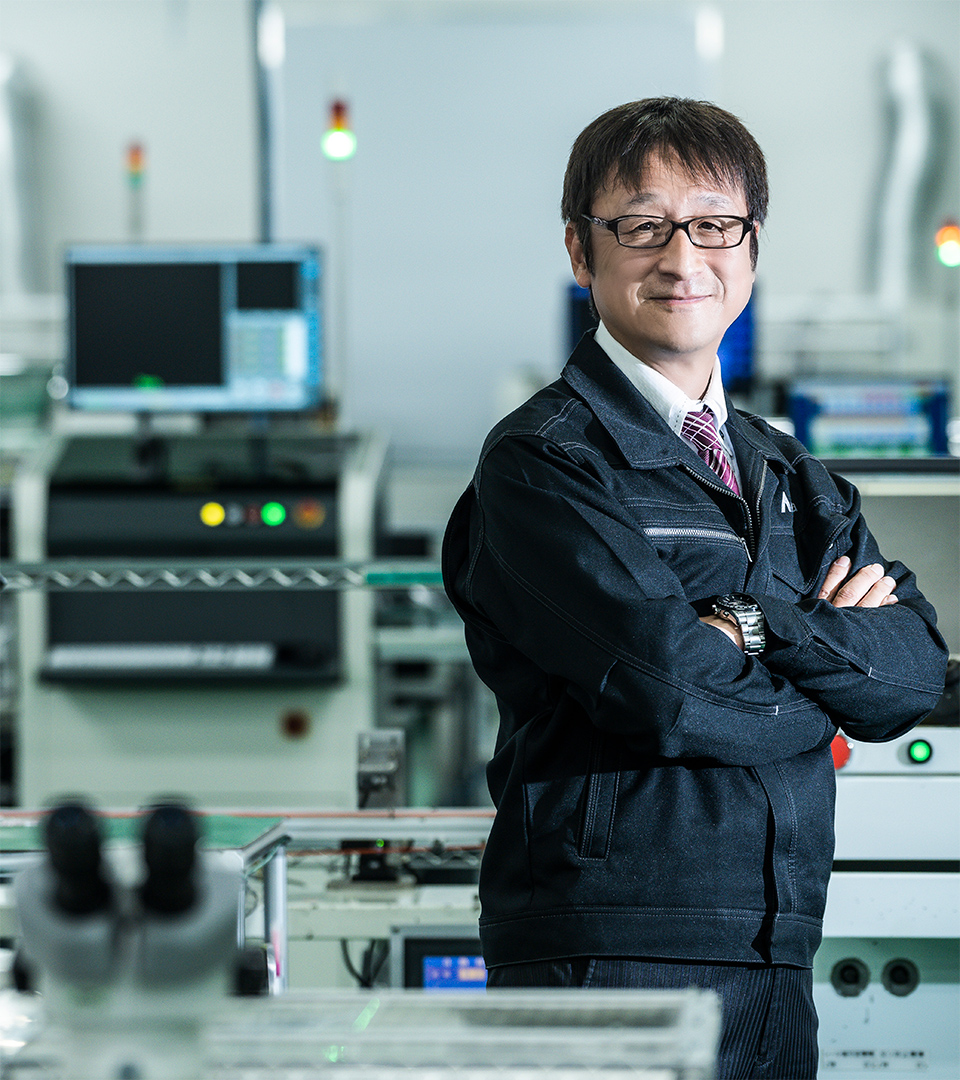EY Entrepreneur
Of The Year™ 2022
Finalist Interview
Finalist
Interview
アントレプレナーたちの熱源
マザーハウス
代表取締役兼チーフデザイナー
山口 絵理子
#04
「マザーハウス」という社名は、マザー・テレサに由来する。コルカタ(旧カルカッタ)で学校や孤児院、死を間近にした人のためのホスピスを開設した彼女は、次の言葉を遺している。
「貧困とは、ただ食べ物も服も家もないことだと考えがちです。ですが、必要とされず、愛されず、気にかけてもらえないことが最大の貧困です。この種の貧困を改善するために、私たち一人ひとりが心を開放する必要があるのです」
バングラデシュに単身で乗り込んで起業を決意
「私は大学のゼミで開発学と出会い、途上国は先進国のように豊かになるまで発展するものだという経済成長理論を信じていました。『国際機関で働き、発展途上国の開発の手助けをしたい』との想いで、4年時には米州開発銀行のワシントン本部で働くという経験もしました」
社会を変えることが自分の存在意義。山口絵理子のピュアな想いは、やがて自分の身体を途上国へと送り込むことにつながっていく。
「ワシントンで一緒に働いていた、経済学で博士号をもっている同僚は『途上国には行ったことがない』と言いました。私もそうです。次第に私は『現場を知らずに理論だけで途上国支援の政策をつくっていていいのだろうか』と思うようになりました。実際に現場ではどのような問題が起きているのか。援助は本当に役に立っているのか。そうしたことを自分の目で確認しないことには何も始まらないと考えたのです」
ワシントンでの短期雇用契約が切れる直前のことだった。事務所にあるパソコンで「アジア 最貧国」と検索したところ、画面に映し出されてきたのは「バングラデシュ」だった。山口は、バングラデシュ行きのチケットを取った。
彼女の行動力は、すさまじかった。2週間の滞在期間中にバングラデシュの首都・ダッカにある大学院の試験を受けて合格し、現地で学び・暮らすという道を選択する。
「バングラデシュでは、ものすごい憤りと圧倒的な無力感の連続となりました。このふたつを濃縮した日々です。正義や努力が日の目を見ない社会。私は、どんなに変えたくても変えられない現実があることを思い知りました。そのなかで、現地の人々は自分の生きる道を懸命に切り開き、力強く生きていたのです」
運命の歯車が大きく回転する日は突然に訪れる。山口は大学院に通いながら、三井物産のダッカ事務所でインターンとして働いていた。ある日、地元企業が集まる展示会でジュートと出会うことになったのだ。
「ジュートは、バングラデシュが世界の輸出量の約90%を占める天然繊維です。コーヒー豆を入れる袋などに使われています。展示会のブースには、ジュートを使ったシンプルなトートバッグが置かれていました。しかし、それは先進国に輸出しても『安さ』や『社会貢献』という切り口以外の商品競争力はゼロに近いものでした。もっとかわいいバッグをつくれたら……。『途上国から世界に通用するブランドをつくる』というマザーハウスの挑戦は、このときのひらめきからスタートしました」
「かわいそう」ではなく、「かわいい! 欲しい!」と思って手にして、大事に使ってもらえるものをつくる。NGOによる援助や生産者支援の慈善活動といった文脈ではなく、品質管理やデザインを徹底して一流のビジネス商材として勝負していく。
2005年5月、たったひとりで起業すると決めたときに山口は23歳だった。
騙され、裏切られてきた先に見た光景とは
もっと早く、もっと安く、もっと大量に。先進国の企業が発展途上国の工場に求めてきたのは、資本主義社会の熾烈さを極めた先の非人間的な荒野だった。13年4月24日にはダッカから北西約20キロのサバールで縫製工場が入居するビルが崩壊し、死者1,100人以上、負傷者2,500人以上、行方不明者500人以上という大惨事が起きている。
富める国に生きる者の欲望が、貧しい国に生きる者の命を搾取していく。そうした流れが加速していく時代のなかで、山口は闘ってきた。
「『もっと早く!』と怒鳴り散らす欧米のバイヤーがいて、うつむきながら黙々と作業している工場のスタッフがいました。現地の工場において、まるで王様と奴隷のような構図を見たときには、何とも言えない屈辱感みたいなものを覚えましたね。変えていかないといけない。強い使命感を抱いて、私はマザーハウスの創業を決意しました」
自分がバングラデシュという国の政治や社会システムそのものを変えていくのは難しい。しかし、目の前のうつむいている人々のためにできることがあるはずだ。山口を動かしていたのは、やはりここでもピュアな想いだった。
しかし、ファッション業界どころかビジネスの経験そのものが皆無という23歳の日本人女性がバングラデシュでデザイン・クオリティともにハイレベルなバッグの生産をしていくことの過酷さは想像に難くない。さらに山口は、見たくない光景と対面することにもなってしまう。
「最初の工場を探し出すまでには、半年もかかりました。そこから本当に大変な想いをしながら、マザーハウスとして初めてのバッグ160個を生み出しています。しかし、工場内で私のパスポートが失くなるということがあって信頼関係が壊れ、その工場とのつきあいは終わりを迎えました。そして、次に取引を始めた工場はある日、もぬけの殻になっていたのです。その光景は、生涯忘れることがないでしょう」
バングラデシュで騙され、裏切られてきたことは、一度や二度ではない。それまでは、どんなに辛いことがあっても「この空は日本とつながっているんだ」と思えた。だが、涙をこらえようとして無意識に空を見上げたそのときだけは違った。
「いいように現地の人に騙されている自分がおかしくて、気がつくと涙を流しながら笑っていました。もう信頼できない。世界が違う。貧しいとは、こういうことなんだと思い知らされました」
そして、涙の累積がマザーハウスを押し上げた
しかし、山口は信頼することをやめなかった。だから、いまがある。
「それは、『いま、私がここであきらめたら、いったい誰がこの国に光を灯すんだ』という想いからです。貧困という巨大な怪物にアプローチできる何か。それは、私が見つけたビジネスを通じた方法で、工場のみんなに希望やプライドをもってもらうことでした」
厚い信頼関係を構築するために山口はバングラデシュに現地法人を立ち上げ、工場で働く人々と雇用関係を結んだ。自社工場をスタートさせたのだ。いま、生産国はバングラデシュだけではなくなった。ネパールでストール、インドネシア・スリランカ・ミャンマーでジュエリー、インドでアパレルを生産している。それぞれの国で、それぞれの素材と職人技を存分に活かした商材が生まれている。
「18年にはマザーハウスのアイテムを手がけてくれている5カ国の職人を初めて日本に呼びました。東京や大阪のデパートの催事として、ものづくりの実演をしてもらったのです。お客さまにマザーハウスのつくり手たちの想いを知ってもらうことが、彼らに日本に来てもらった目的でした。ですが、イベントは次第に5カ国の職人たちの交流の場、切磋琢磨の場にもなっていきました。最終日の夜、イベント終了後に会場の奥から聞こえてきたのは『マザーハウス! マザーハウス!』という掛け声でした。初日にはよそよそしく別々にランチを食べていた5カ国の職人たちが、円陣を組みながら大きな掛け声を連呼していたのです。それを見た私は、大爆笑しながら大号泣していました」
山口が裏切られ、06年に突如として工場がもぬけの殻になっていたことは、この世界の真実である。一方で、18年に見た5カ国の職人たちによる円陣もまた、紛れもなくこの世界の真実である。ふたつの真実に到達することができたアントレプレナーの涙。その涙が山口のアントレプレナーシップを磨いてきた。
「マザーハウスのカルチャーを象徴する言葉があります。これはバングラデシュの工場長の口ぐせでもあるのですが、『Let me try!』という言葉です。私たちはこれまで、常に変化をいとわず、挑戦を続けてきました」
「挑戦させてほしい」
かつては山口ひとりのものだった挑戦が、いまでは社員800名による大きな円陣に通底するカルチャーにまで育っている。
そして、これまでの涙の累積は、山口のクリエイションを輝かしいもの、唯一無二のものへと押し上げている。18 年にはアパレルブランド「E.」を立ち上げ、22年には新ライン「ERIKO YAMAGUCHI」を発表。『途上国から世界に通用するブランドをつくる』という挑戦は、着実にステージを上げている。
「私は起業家、経営者であると同時にデザイナーです。私がデザイナーとしてもっとも大事にしてきたのは、『素材との対話』です。途上国のチカラは、素材に宿っています。それを引き出すのがデザイナーとしての私の役割です。逆に自分の個性で素材のチカラをつぶしてしまわないようにと考えてきました。素材のチカラを引き出すということはすなわち、その国の職人たちの成長や可能性を信じて引き出すことと同義です。そうした同義性を根底の部分で大切にしながら、『ERIKO YAMAGUCHI』では新たな挑戦を始めています。それは、私らしさを思いきって表現していくことです。強い覚悟を決めて、私のフルネームをコレクションの名前にしました。この洋服やバッグ、ジュエリーのコレクションでは、すごく正直に、真っ直ぐに自分を表現していきます」
まさに創業者が自ら、「Let me try!」を体現しているのだ。
22年9月期にマザーハウスは、コロナ禍にありながら過去最高の売上を記録し、起業した初年度との比較では160倍の伸びとなった。いま、バングラデシュでは「最高の労働環境をつくろう」との想いのもと、学校や病院を併設した1,000人規模(これまでは250人規模)の工場「グリーンファクトリー」を建設する計画が鋭意進行中だ。

山口 絵理子
1981年、埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。ワシントンの国際機関でのインターンを経て、バングラデシュBRAC大学院開発学部修士課程に留学。2006年3月9日、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションに掲げてマザーハウスを設立し、代表取締役兼チーフデザイナーに就任。
マザーハウス
本社/東京都台東区台東1-10-7
URL/http://www.mother-house.jp
従業員/800人(2022年11月時点)
Promoted by EY Japantext by Kiyoto Kuniryophotographs by Masahiro Mikiedit by Yasumasa Akashi