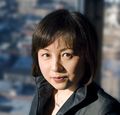──あなたの新著は、時代や思想、心理、職業など、あらゆる側面から仕事を新しい発想で捉えた400ページ超の大作です。ご自身のキャリアも含め、着想に至った経緯を教えてください。
出版まで6年かかった。「仕事」というのは実に面白いテーマだから、多面的に掘り下げようと思った。
私は教授としてジャーナリズムを教えているが、『Cheap』(『価格戦争は暴走する』筑摩書房)など、経済をテーマにした著書がある一方、科学ものも執筆する。『価格戦争は暴走する』は、低価格の「外部性」について書いた本だ(注:外部性とは、低価格競争などの経済活動が取引当事者以外の主体に対し、格差拡大や賃下げなどの影響をもたらすこと)。同書の執筆を通し、低価格が労働にとって何を意味するのか、仕事や労働に何が起こっているのかという疑問が浮かんだ。それで、『The Job』の執筆を思いついた。
──新著では、テクノロジーやグローバル化による中流層の縮小やアメリカンドリームの衰退に懸念を示されています。
米国人が、仕事や仕事の未来について案じていることに大きな懸念を抱いている。彼らは、減りゆく収入や低下する職場での地位を憂いているが、(政治家など)権力者の取り組みは不十分だ。仕事をめぐる認識には多くの神話や誤解があり、それに真っ向から誠実に向き合うことが民主主義にとって重要だと考えた。これが執筆の理由だ。
私は、ボストン大学で科学ジャーナリズム・プログラムの共同責任者を務めていることもあり、証拠とデータの力を信じている。だから、科学で用いられるような綿密な分析で仕事に関する考えを理解し、代替案を提示することにした。
──新著の取材執筆を通して見いだした最も興味深い発見は何ですか。
まず、社会通念や常識(の不正確さ)だ。例えば、米国人は21世紀の仕事をこなせるだけのスキルがないという「スキルギャップ」説が流布しているが、これは正しくない。だが、業界や業界寄りの政治家は米国人に即戦力を求め、企業は以前ほど社内研修に乗り気でない。物事が目まぐるしく変わる中、必要な研修なしに即戦力を期待することに無理がある。企業がどのように人々を教育し、21世紀の働き方に向けて準備させるべきかなどを新著で示した。
──「米国人は、仕事を神聖なものと信じるよう育てられる」と書かれています。
多くの米国人は、頭脳だけでなく、精神的エネルギーも大いに仕事に注ぎ込むよう教育されている。それが問題なのだ。米国では雇用の保証や労働保護がないからだ。解雇も降格も賃金カットも合法だ。仕事に心血を注ぐと、自分の立場が脆弱化する。
失業は、離婚と同程度の心理的影響を及ぼす。特に男性にとっては壊滅的だ。仕事に精を出すべきだとは思うが、仕事は人生のポートフォリオの一つにすぎないのだから、すべてを注ぎ込むべきではない。
新著で紹介したが、オックスフォード大学の心理学者が、ケガで仕事を失った音楽家やダンサーについて調べた研究がある。それによると、仕事との情緒的つながりが少ない人のほうが、感情面で入れ込んでいた人より、喪失感をはるかにうまく克服できたという。だが、自分を組織と一体化させているダンサーは壊滅的な打撃を受け、自殺すら考えたケースもあった。一方、踊りというスキルに自分のアイデンティティーを置き、踊ることに情熱を注いでいるダンサーは、バレー団での仕事以外の方法で自己表現できる。