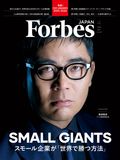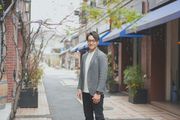このようにユニークなシグネチャー・カクテルが各店にあるので、バー巡りに飽きることがない。インド独自の原料に加えて、インド産ウィスキーやラム、ジン、テキーラ等もあるため、インドならではのユニークな原酒も手に入る。この無限のミクソロジーの可能性が、インドのカクテル文化を支えているのだろう。
富裕層には輸入ワインが人気
これだけカクテルが楽しいと、気になるのがワイン事情だ。2016年にはインド初のマスター・オブ・ワインが誕生し、インドにソムリエ協会も設立されたのも記憶に新しい。ワインの消費は、ビール、スピリッツ、ウィスキー、RTDに続き4位だが、ユーロモニターの調べによるとワイン消費量は2020年の2920万リットルから2025年までに5550万リットルに増える見込みだという。中間層の拡大や消費行動の多様化が進むムンバイやデリー、バンガロールなど都市部では、ワインは「富の象徴」として市民権を獲得しつつある。
 ネックとなるのがワインの価格だ。
ネックとなるのがワインの価格だ。実はインドは輸入ワインの基本関税が150%と、べらぼうに高い(オーストラリアのように貿易協定を結び、15ドル以上のワインは75%に引き下げられた国もある)。その上、高級レストランではメニュー価格にVAT(付加価値税)20%※(※州やレストランの業態によって異なる)とサービス税も課税される。例えば、とある5つ星ホテルでは、日本でボトル千円前後で買えるジェイコブス・クリークのシャルドネがグラスで約2000円(税込・サービス料抜)だった。
そのため国内のワイン販売で輸入ワインが占める割合は3割に留まるが、インドの富裕層は輸入ワインを好む傾向にある。海外でワインを購入し自宅で楽しんだりワイン会を開いたりする富裕層も多く、なかには数千本のワインを保有するコレクターもいるという。