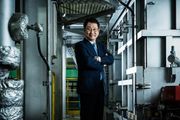中国の浙江省はいまやハイテク産業の前線基地として知られているが、『青春』の舞台は、その最先端の省にあるとはにわかには思えない、湖州市織里という子供服をメインとする家族経営のアパレル工場が集積している地区だ。
そこで働く「農民工」、すなわち安徽省や河南省といった内陸の農村出身の若い労働者たちの日常を追った内容で、主に2010年代半ばに撮影されたものだという。
主人公らしき人物はいるものの、数多くの無名の若者たちが次々と登場する。ミシン工場と彼らが寝起きする1人に1つのベッドだけがあてがわれた共同宿所、その狭小な空間で繰り広げられる、現代中国の若者群像が描かれている。
なにしろ大半が10代から20代にかけての共同生活をする男女。彼らは仕事をしながら、とてつもない大音響で音楽を聴いたり、取っ組み合いの喧嘩をしたり、たどたどしくも、また思いがけずロマンチックな「恋バナ」をしたりもする。
さらには集団で老板(ラオバン=経営者)のもとに押しかけ、「賃金交渉」を始めたりするなど、王兵監督の作品でなければ見られない、演出とは無縁の赤裸々な映像がスクリーンには映し出される。
農民工の実態と日本の集団就職
この作品を観る際、筆者は2005年のアメリカ映画『女工哀歌(原題「China Blue」)』のことを思い出していた。スイス生まれ、イスラエル育ちのドキュメンタリー作家であるミカ・X・ペレド監督の作品だ。 『女工哀歌』は、中国が「世界の工場」として好意的に迎え入れられ、もてはやされていた2000年代前半の広東省のジーンズ工場が舞台で、そこで働く四川省出身の16歳の少女ジャスミンの日常を描いたものだ。
『女工哀歌』は、中国が「世界の工場」として好意的に迎え入れられ、もてはやされていた2000年代前半の広東省のジーンズ工場が舞台で、そこで働く四川省出身の16歳の少女ジャスミンの日常を描いたものだ。中国がWTOに正式加盟した2001年以降の「グローバリゼーション」の時代、その到来とともに顕在化していく「労働搾取」という新しい現実を、世界の観客に気づかせることを企図した理知的な内容ではあったが、ずいぶんスマートな描き方をしていたと思う。
というのも、この作品を象徴する1つのシーンに、こんなエピソードがあるからだ。毎日ミシンで縫い上げるジーンズのポケットに、ジャスミンは自分という女工の存在を伝える手紙をこっそり忍ばせる。
彼女は日々労働に追われる生活を送りながら、「私たちが毎日つくるジーンズは、誰がはいているのだろう?」と考える。そして、ラストではそのジーンズを購入することになる海外の人物と彼女の映像が重ねられるというものだった。
こうしたどこかメルヘンのような2000年代の広東省の女工物語と2010年代の長江下流域の物語である『青春』は、作品の趣もそうだが、リアリズムの質感がずいぶん違っている。
もちろん、両者の置かれた環境には変わらないところもある。今日の中国農民工の存在には、日本の1950年代から60年代にかけての高度経済成長期の「集団就職」と似たようなものがあると言えなくはないからだ。