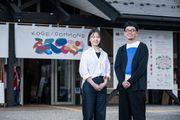(3)KPI評価に基づいた課題設定と対策 ─シーズンを通した成長を!
ビジネスの世界では目標数値として扱われることが多いKPIですが、我々のプロジェクトでは「評価基準値」と位置付けている面が大きいのも特徴です。これは、試合数の多さや次の試合までの期間が短いために評価する頻度が高く、より短期間で次のサイクルに入っていかなければいけないというスポーツアナリティクス特有の性質によるものだと考えています。
リーグ1位の強豪チームと対戦した3日後に最下位のチームと対戦、といったことがままあり、そのようなスケジュールの中で目標値を達成することだけを目指していては、60試合通して成長することができません。
KPIを評価基準値として捉え、達成できなかった時に、対戦相手の強さによる影響なのか、自分達の力を発揮できなかったことが原因なのかを深掘りすることで、60試合の中で解決すべき課題をより明確にし、向き合っていくことができるのです。
例えば、我々は昨シーズン(2022-23)、23勝37敗で地区6位(8クラブ中)に終わりましたが、これを勝率だけで見ても課題はわかりません。
独自のKPI表で見ると課題は、
●3P%(3ポイントシュートの成功率)
●3PA%(3ポイントシュートの試投割合=3Pを打つ割合)
●TO%(ターンオーバーの割合=ミスの割合)
の3つであり、さらにこれらの項目は特にTop10のチームとの対戦において低くなる傾向が明確になりました。
この分析を受けてオフシーズン中に、戦略・編成(どのような選手メンバーを集めるか)・プレイヤーディプロップメント(どこを成長させるべきか)の各分野において対策を講じ、今シーズン(4/20現在)「3P%:リーグ4位」「3PA%:リーグ2位」「TO%:リーグ4位」となっています。

(4)2と3の循環
今シーズンからは(2)KPIの設定と(3)KPI評価に基づいた課題設定・対策をサイクルとして回すことで、より具体的かつタイムリーに課題の抽出を行なうというフェーズに入っています。3Pシュートについて更に詳しく言うと、11月の時点では「3PA%(3Pを打つ割合)がリーグ2位」「3P%(3Pの成功率)はリーグ18位」で、前述のようにオフシーズンから改善に取り組んできた中で、打つ本数は増えているが、成功率が向上していないという状況でした。
2P%はリーグ5位でした。そこで、2Pを増やすべきか、もしくは3Pの確率を上げるべきなのかを検証するための分析を行なうことにしました。

分析の結果は後者でした。一見、効率の悪いシュートを多く打っていると結論づけられそうですが、TO(ターンオーバー)やOR(オフェンスリバウンド)など他の要因と共に分析し、チームが採用している戦略全体をシステムとして捉えた時に、3PAは負の循環ではなく、正の循環に寄与していることがわかったのです。
このように、チームスタイルを変更して2Pを増やすのではなく、チームスタイルを維持していくほうが全体的な成長が見込めるという結論を出し、Judd氏によって3P%を上げていくための課題がいくつか提示されて(ここも内緒で...)、前述の「3P%:リーグ4位」(4/20現在)に至っています。
ちなみにJudd氏による指摘の一つに「平均への回帰」がありました。簡単に言うと、ある時点での3P%が低くても、いずれは平均値に回帰していくという経済学者らしい、先を見据えた予想でもありました。