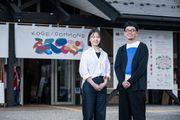日本バスケ界の常識を疑え! 地区優勝へのロードマップと独自のKPIモデルを作成
そして、実際にプロジェクトを進めていくにあたり、詳細なロードマップを作成しました。まとめると以下のような流れです。
(1)Bリーグにおける勝利の条件を知る
(2)KPIの設定
(3)KPI評価に基づいた課題設定と対策
(4)2と3の循環

(1)Bリーグにおける勝利の条件を知る
最初に着手したのは「Bリーグにおける勝利の条件(Winning Factor)」を知ることです。あえて「Bリーグにおける」としたのは、Judd氏がいち早く指摘した「アメリカの手法が正しい」とされてきた日本バスケットボール界の風潮に対する課題意識からでした。
我々はそんな固定観念から生まれている日本バスケ界の常識をまずは疑ってみることから始めました。
そこから導きだされた解の一つが、オフェンス・リバウンド(Offense Rebound=OR)です。
NBAではORを取りに行くことで相手のカウンターを受け、簡単に得点を与えてしまうリスクを鑑み、ORを取りに行かないという戦略が一般的です。しかし、このプロジェクトでBリーグを対象に分析をしたところ、BリーグにおいてはORを取りに行くことによるカウンターのリスクよりも、ORを取得することで得られる恩恵のほうが高いことがわかったのです。
この分析結果を新たな戦略立案に繋げ、今や三遠はORの取得数が多いチームとなっています。
また、この他にも2つのWinning Factorをコーチや選手に提示しています。が、あとの2つは... 我々の勝利のキーとして、内緒にさせてください。

(2)KPIの設定 ─粒度がカギ!
次に(1)で得たWinning Factorを基に、勝つことをKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)として、KSF(Key Success Factor:重要成功要因)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の設定をまとめて行ないました。最初にまとめたKSFとKPI1まではバスケ界に既存する「4Factor理論」* とほぼ同じ指標となりましたが、我々はこれらをKPI2、KPI3と細分化し、三遠独自のKPIモデルを構築しました。
この細分化は「数値化するものにはより具体性が必要」という大野HCの考えをベースに今現在も続けられており、その具体性の粒度は「努力と意識で改善できるもの」を基準としています。
* 米スポーツ統計学者のディーン・オリバー氏が提唱した、バスケで勝利するためには「シュート確率/ターンオーバー率/リバウンド獲得率/フリースロー獲得率」の4つの要因が重要であるという理論