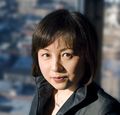医療テクノロジーが日々進化するなか、「死」とは何か、「人間性」とは何かという問いかけへの答えが、今ほど求められている時代はない。
「人工心臓」の登場で、「自然な死」と「人工的な死」の線引きは曖昧さを増している。患者が寿命を迎え、他の臓器が機能停止に陥ったとき、植え込み式除細動器(ICD)から送られる電気ショックで苦しむ患者を前に、医者はICDの停止を決断すべきなのか。医療テクノロジーの進歩は実にエキサイティングだが、極めて複雑な問題を生み出している。
現在、米シンカーディア・システムズ社製の「全置換型人工心臓」を体内に埋め込んだ患者は、世界で1700人近くに上る。2016年に出版した『Beyond Human』(邦訳『Beyond Human 超人類の時代へ』佐藤やえ=訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)の執筆当時は1200人だったことを考えると、非常に速いペースで増えていることがわかる。
世界には、臓器移植が必要な心臓病患者が2600万人ほどいるが、供給が足りないため、移植までのつなぎとして、人工心臓が開発された。だが、人工心臓で5年近く生きているトルコ在住の男性を見てもわかるように、つなぎ以上の機能を発揮する例が増えている。人工心臓を移植した患者の多くは、「安心で安全」だと感じており、早急な心臓移植の必要性を感じていないという。
40代でシンカーディア製の70ccの人工心臓を植え込み、その後、心臓移植を受けた米国人女性によれば、人工心臓は、自分の心臓より調子がよかったという。1分につき9.5リットルの血液が体内を循環し、他の臓器も機能を回復することで、患者は元気になる。その効果は劇的だ。永続的な使用の可能性を探る50ccの人工心臓もすでに開発され、食品医薬品局(FDA)の認可も下りている。
米国でも高齢化が進むなか、心臓移植が必要な患者は着実に増えている。将来、人工心臓が、心臓移植の供給数と患者数のギャップを埋められるようになるのではないか、という大きな期待がある。
だが、問題もなくはない。患者がICDの移植手術を受けている場合、死の過程が複雑化することだ。心臓や他の臓器の機能を支える植え込み式デバイスは、患者の心機能が終末期に入ると、心臓に強烈な電気ショックを与え、患者の死を防ごうとする。そのため、患者は穏やかな死を迎えられず、遺族も、家族が苦しみながら息を引き取る姿を目にしなければならない。しかし、大半の人々は、ICDが臨終を「苦痛にあふれた」ものにしてしまうことを認識していない。
一方、医者は、人工心臓やICDデバイスをいつ停止するかという問題について、自らの責任で決断を下したくないと考えている。この問題を患者や家族と話し合うことをしようとすらしない。患者にも、臨終の際にどうしたいのか、自分の意思を医者に伝えておく責任があるが、そうした理解が乏しい。
米国では、「植物状態として生きたくない」などといった遺言を医者や家族に残すのがトレンドになっているが、知識不足のせいか、遺言を残さない人のほうが依然として多い。
人工心臓が問う医療倫理
また、「患者の命をできるだけ長くつなぎ留めるために、あらゆる手段を尽くす」という、偏った米医療文化の影響もある。デバイスの停止を「殺人」になぞらえる医者もいるほどだ。患者のなかにも、停止を「自殺」と考え、肯定的にみない人がいる。
専門家の見解も真っ向から分かれている。まず、「人工デバイスは、患者という生身の人間の一部ではなく、テクノロジーなのだから、自分の意思で停止できてしかるべきだ」という意見だ。それに対し、「デバイスは体と一体化し、命を支えているのだから、患者の一部だ」というのが、反対派の言い分だ。