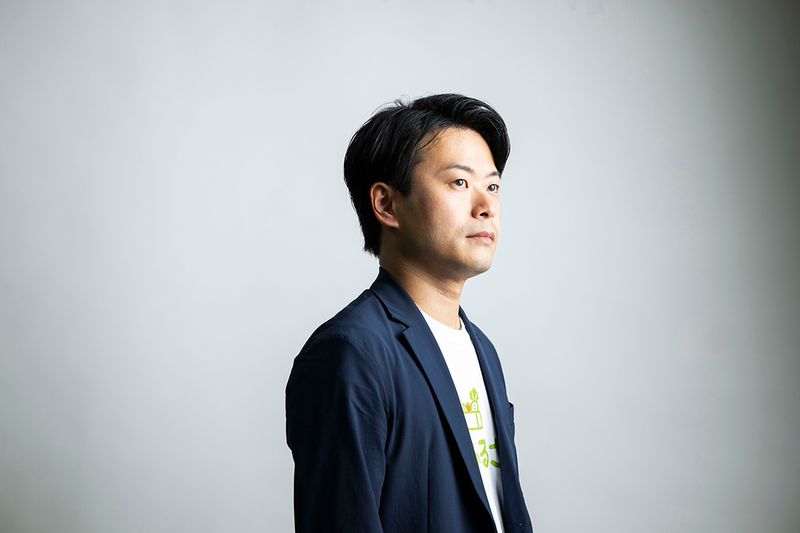ふるさと納税日本一の自治体も参画、広がる連携の輪
12月4日に本格ローンチを迎えた「こどもふるさと便」は、既存のふるさと納税制度を応用して設計されている。支援者が「こどもふるさと便」のポータルサイトを通じて提携自治体に寄付を行うと、その寄付金は自治体の予算となる。自治体はその予算で、地元農家や漁師から米・野菜・肉・魚などを適正価格で買い上げ、支援を必要とする子育て世帯へ配送する仕組みだ。
なぜ、あえて「地元産品」を買い上げるのか。ここに木戸の戦略がある。
自治体において鍵を握るのは、「事業原課」と呼ばれる事業を管轄する部門だ。どの部署が原課となるかによって、予算の使い方が変わる。「こどもふるさと便」の場合、事業原課は農政課などの経済部門。彼らのミッションは「地域産業の振興」であり、福祉施策の実施とは異なる。単に「こどもを支援したい」というだけでは、継続的な予算措置を引き出すことは難しい。そこで木戸は、自治体が「こどもふるさと便」に取り組む意義を「地域産業への経済波及効果」として定義し直した。
「この仕組みを使えば、寄付金という外貨で地元の米や魚が購入されます。つまり、こども支援がそのまま地域産業の売上になるのです。さらに、その特産品によって支援するこどもは、地域の枠を超えて全国を対象にできる」(木戸)
支援の安定化・広域化という目的から逆算し、「経済合理性」という解を導き出したことで、福祉の枠を超えた強力なパートナーシップが実現することになる。
その成果は、今回参画を表明した自治体の顔ぶれに表れている。プロジェクトには、北海道旭川市、北海道音更町、石川県能登町、長崎県壱岐市、長崎県対馬市、宮崎県都城市の計6自治体が名を連ねた。
特筆すべきは、ふるさと納税の受入額で何度も日本一に輝き、「肉の都城」として知られる宮崎県都城市の参画だ。返礼品競争の象徴とも言える同市が、こども支援という「使いみち」に共感し、パートナーとして参画したことは、同モデルの有効性を強く裏付けているとも言える。
また、震災復興の途上にある石川県能登町においては、販路を求めている地元の魚を買い支えることが、そのまま復興支援とこども支援の両立になるという側面も持つ。
さらに長崎県壱岐市では、食料などの「モノ」だけでなく、豊かな環境を生かした「自然体験」を特産品として提供する。支援の形は、すでに食料の枠を超えて多様化し始めているのだ。
こうした自治体から預かった特産品を、確実にこどもたちへ届けるための連携体制も盤石だ。パートナーには、こども食堂支援の「むすびえ」や、教育支援を行う「チャンス・フォー・チルドレン」をはじめ、「キープ・スマイリング」「D×P」「I&Others」「WeSupport Family」といった実績あるNPO・支援団体が名を連ねており、ラストワンマイルの支援を支えている。