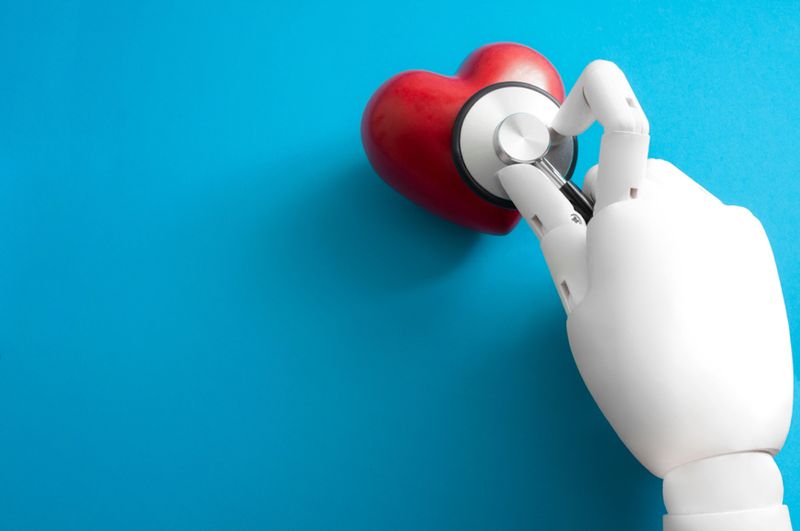医師の仕事はすぐにはAIに置き換わらない
しかし、放射線科や皮膚科、病理学といった分野でさえ、AIが完全に医師に取って代わることはない。
メイヨー・クリニックでは、AIは放射線科医を代替するためではなく、ルーチン業務の自動化や、病気の予測精度を高める異常所見の検出に使われている。放射線科医の仕事は画像の読影だけではない。彼らは他の医師と連携し、患者と対話し、画像を使って位置を確認しながら行う組織の採取や、脳卒中・感染症の治療といった処置も行っている。
また、皮膚科医は生検を実施し、診療所で皮膚疾患の治療を行っている。病理医は、亡くなった人の体を調べて死因などを確認する検査(剖検)を行い、複雑な症例に対して専門的な見解を提供する。こうした手作業は、いずれもAIに委ねることができない。
では外科医はどうか? 研究によれば、AIは精密さを支援することはできても、自律的に手術を行うことはできない。実際に手を使って行う医療行為が中心の外科においては、AIが中核的な業務を代替する可能性はほとんどない。
さらに、一部の患者はAIによる医療を受けるための心の準備ができていない。2023年の調査では、64%の患者がAIによる診断を人間の医師による診断よりも信頼すると答えたが、その信頼度は症状が複雑になるほど低下する傾向にあった。
ただし、AIが一部の業務において安全であるか、あるいは人間より優れていることを示すデータが今後さらに蓄積されていけば、AIの医療における役割に対する人々の考え方は変わる可能性がある。
それでもなお、医師と患者の関係における核心的な要素である「共感」は、AIでは代替できない。米国救急医学会の公式誌、アカデミック・メディスン誌に2011年に発表された研究によると、より共感的な医師の患者のほうが糖尿病のコントロール状態が良好だった。つまり、医師との人間的なつながりが健康に直結するということだ。
AIは医師の「賢い副操縦士」になる
医療分野のAIは、医師を代替するのではなく強力な「副操縦士」としての役割を担いつつある。医療機関がAIの診療プロセスへの導入をさらに進め、医師たちが活用を広げることで、AIは多くの雑務から医師を解放し、より複雑な思考や微妙な判断、患者との関係に集中できるようにする可能性がある。
実際に現在、AIが副操縦士として効果を発揮しつつある例としては、医師が考えられる病気をいくつか挙げて、どれが当てはまるかを絞り込むときにAIツールを利用するケースが増えている。たとえば小児の希少疾患においては、特徴的な症状の組み合わせを特定するためにAIが有効に働き、診断を絞り込む助けとなる。
また、「OpenEvidence」のような特定のAIプラットフォーム(これは全米医師番号を持つ医師のみが利用できる)は、困難な医療の問いに対して、最新の研究やエビデンスに基づく回答に素早くアクセスするための手助けをしてくれる。
AIが貢献している有望な分野のひとつに、医師の記録作成作業の自動化がある。現在、医師は業務時間の約半分をデータ入力に費やしているが、一部の診療科、特に外来医療の分野では、音声対応のAIアシスタントがその負担を軽減し、時間を節約できるようになっている。
これらはいずれも医師を代替するのではなく、支援することを目的としたAIツールだ。