三越伊勢丹HDの社長を経て、空港を拠点とした地方創生に力をいれる羽田未来総合研究所で代表取締役社長執行役員を務める大西 洋と、「日本創再生」を掲げ、地方で宿泊、飲食の展開も多いバルニバービ代表取締役の佐藤裕久は、漁から帰ってきた漁師から魚を直接買い求めることができるユニークさを絶賛。特に大西は「サプライチェーンの短さ、シンプルさは他にない」と高く評価する。

同じく、広島県生口島の瀬戸田で築140年の廻船問屋の屋敷をホテルとして運営するStaple代表取締役の岡雄大は、魚種の豊富さと、火山灰を使って干物にする「灰干し」加工や県内の発酵文化を含めた食の技術、海沿いの遊歩道や狭い路地など、歩きたくなる街の3つを両地区の魅力に挙げた。

地域の課題解決を「妄想」で進める
問題は、獲れたて、新鮮な魚介類を購入できても、この地区で捌いて食べられる飲食店の数が限られていること。休憩する施設も少ない。魅力はあるものの、そのポテンシャルを活かされていないため、それをどう解決していくのか、仮に事業化されたとして、その点をいかに線や面にして、まちの活性化につなげていくか、が大事であるため、まずは事業を行う起点をテーマに話し合うことになった。
地元である和歌山で空間プロデュースから飲食店まで展開する源じろう代表取締役の半田雅義によれば、新たな事業を起こすときの最初のアクションは、「どこのエリアで、どんな空間を使って、何をするのか」の徹底だという。その半田流の方法が「もし街や建物がしゃべれたら、何をしてくれ、どう動いてくれと言うだろうかという“妄想”」だという。半田の「妄想」というキーワードに識者たちは皆、激しく首肯する。
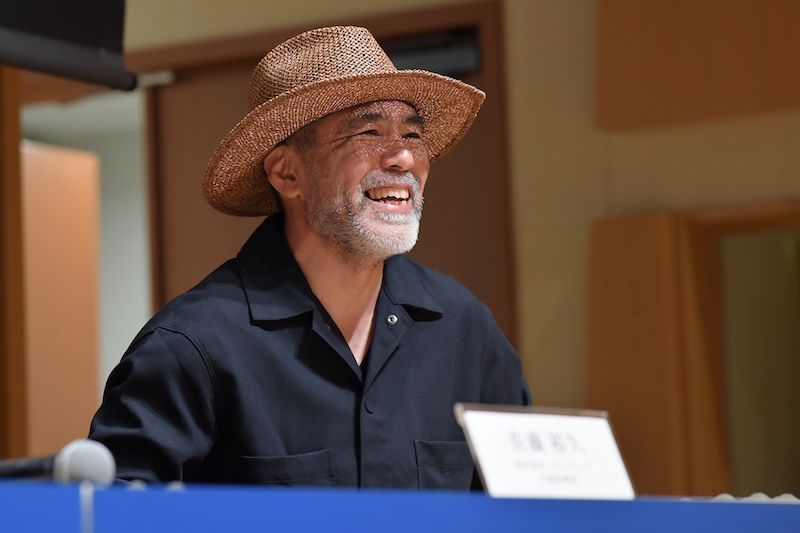
淡路島や出雲で飲食や宿泊の事業を行う佐藤も「私も妄想派で、自分の妄想を具現化できるほどまで高めなければ、誰も納得しない」といい、妄想を自分の頭のなかで映像にすることが、最初の一歩だと語る。日本共創プラットフォーム代表取締役会長の冨山和彦も「南紀白浜空港のコンセッションに手を上げる際も、妄想と言われていましたけど、僕らはその妄想に主観的なロジックがあったので、確信を持っていた」と語る。
和歌山市の冬の恒例イベントとなった光のフェスティバル「フェスタ・ルーチェ」を仕掛けるタカショーデジテック代表取締役社長の古澤良佑も同様だ。9年前に始めた時を思い返し、「真剣にヒアリングをしたら止めていたと思うんです。冬の寒い真っ暗な海沿いでライトアップをやっても、人は来ないと言われたでしょう。でも、自分のなかの妄想では和歌山の人が楽しんでくれる光景が浮かんでいました。結果的に1年目から8万人が訪れ、9年続いている」と話す。妄想ながら緻密でロジカルなものが雑賀崎、田野地区のまちづくりでも重要な一歩目となるのではないだろうか。




















































