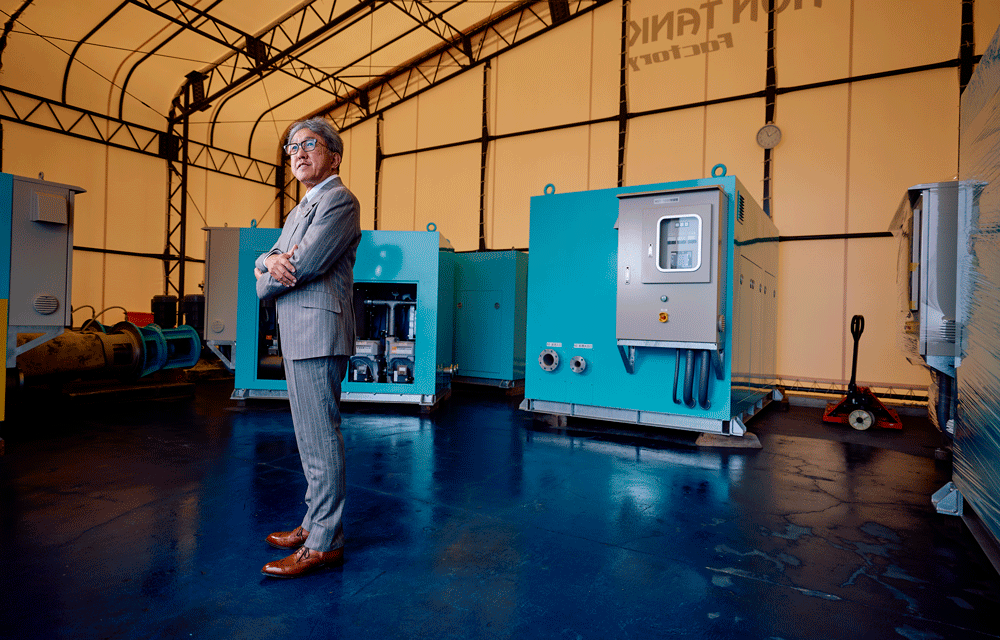山崎:それこそエンタメ漬けになって、何が面白いのか、何が受けるのかっていうことを突き詰めていく。皆現場ではオン・ザ・ジョブ・トレーニングなんですよね。迷ってると仕事に放り込まれていく。才能があればいいけど、自分に与えられた仕事を消化することでトレーニングしているので、振り落とされてしまう人もたくさんいる。
庵野:そうだよね。山崎くんが、塾やればいいのに。山崎塾。松本で。国にお金出してもらって。
山崎:えー、いやいやいや。でも映画の学校ってどうしてもアートに行ってしまう人が多い気がする。
——人材育成の話が出ましたが、おふたりは自身のキャリアを振り返って、どのような環境が最も自分を成長させたと思いますか? また、今の若手にその環境はありますか?
庵野:僕は地方出身なので、情報に対する「飢え」は大きかったです。好きな作品があって、ベースとなる情報はテレビと漫画雑誌と単行本があるんですが、その先を追求しようと、さっき観た「宇宙戦艦ヤマト」の第2話をもう一度観たいと思っても、観られない。再放送がある何年か先まで待たなくてはならない。放送が始まる4時半にはテレビの前に座っていないといけないので、クラブ活動なんかも一切なし。間に合わないときは学校から近い友達の家で観せてもらった。一期一会の感覚なので、一回で観る「気がい」みたいなのが全然違うんです。情報を手にいれるための努力が大きかった。その渇望感がオタクとしてのエネルギーをつくっていた。物事に対しての意欲みたいなものと直結している気がします。今の日本では難しいかもしれませんが。むしろ海外ならそういう人が出てくる可能性があるのかな、と思います。
山崎:「飢え」は僕もありました。ビデオも何もない時代があって、体験としては相当貴重な思い出。今思えば田舎に生まれてラッキーだったのかもしれませんが、当時はつらかったですよね。映画も東京で公開されて劇場は並んでいる、情報もどんどん入ってくるのに、自分の地元ではあと1カ月たたないと始まらない、とか。
庵野:タイムラグもあったし、すぐ終わっちゃった。
山崎:最悪、やって来なかったり。
庵野:東京や大阪などの都会と田舎の情報格差は大きかったですよね。東京だとオールナイトで怪獣映画を毎週やっていて、キネマ旬報を見るとそのプログラムが広告に出ていて、東京羨ましいって。
山崎:僕の場合は、洋画志向だったので、そもそも「何で日本に生まれてしまったんだ」って(笑)。(東京には)日本に絶対来ないような洋画を上映してくれる喫茶店なんかもあった。
とにかくあのころの映画に参加したかった。
あとは、若いころは取り憑かれたように仕事をしたい、と思いましたね。今の言葉で言うと、セルフブラック企業です。「お前帰れ」って言われているのに会社に残って隠れて仕事をしていたり。それはもうやっぱり好きだったので、仕方がない。今の働き方からすると決してよろしくないのかもしれないけれど、ある時期には生活一切を犠牲にして仕事に注ぎ込む、ということも大事なのかもしれない。