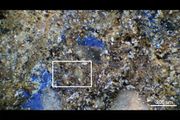パンにほんの少しのカビが生えているだけでも、低濃度の抗菌化合物が発生する。これが傷に定着して感染するはずだった微生物に対して使用された場合、治癒に有利に働くのに十分だった可能性がある。古代の医師は恐らく正確な投与量に関する知識や滅菌された道具を持っていなかったが、カビの生えたパンを継続的に使用していたことから、有益な結果を観察していたであろうことが分かる。
それは本当に「抗生物質」だったのか? 現代の生物学者の見解
学術誌「応用微生物学の進歩」に掲載された別の論文によれば、現代医学で使われる抗生物質は「微生物によって産生される物質で、細菌やその他の微生物の増殖を抑制し、それらを死滅させる能力を有する」ものと定義されている。この定義に従えば、古代エジプト人のカビの生えたパンによる処置は、多少不完全ではあっても技術的には抗生物質の要件を満たしている。
精製されたペニシリンとは異なり、カビの生えたパンは治療薬としての効力が一定ではなかっただろう。これはパンに存在していたカビの種類や保管されていた期間、環境条件(温度や湿度など)によって大きく異なる。しかし生物学的な観点から見れば、古代エジプト人が原始的な抗生物質療法を実践していたと推測するのは妥当だ。
とはいえ、1928年にフレミングがペニシリンを発見したことは、恐らく現代医学の礎として今なお揺るぎない地位を保っている。青カビがシャーレ上の細菌の増殖を防ぐという、綿密に調査され記録されたフレミングの観察結果は革命のきっかけとなった。しかし歴史的に見れば、フレミングは数世紀にわたる民間伝承の知恵を単に証明したに過ぎないと言えるかもしれない。
実際、フレミングはカビの抗菌作用の可能性を認識した最初の科学者ではなかった。1897年、23歳のフランス人医師エルネスト・デュシェーヌは既に、特定の青カビが体内で細菌に拮抗(きっこう)する仕組みを記録していた。だが、この観察結果が注目を浴びることはなかった。フレミングらが行ったのは、民間療法を信頼できる医薬品へと変えるため、カビ由来の化合物を分離、精製し、大量生産を可能にすることだった。この飛躍こそが、現代医学で最大の変革をもたらしたのだ。
しかし現代の生物学者にとって、古代エジプトのカビの生えたパンは、単なる歴史的な好奇心以上の存在だ。これは、顕微鏡や細菌説が登場するはるか以前から、生物学的な仕組みが人間の創意工夫とどのように結び付いてきたかを示す決定的な証拠だ。
4000年前のエジプト人医師の仕事を幼稚なものとして見なす向きもあるかもしれないが、そこには確かな生物学が働いていた。これらの初期の医師たちは、細胞や細菌、抗菌剤について現代のような理解を持っていなかったかもしれない。それでも古代の医師は観察し、実験を重ね、やがて抗生物質革命の前兆となる伝統を後世に伝えたのだ。