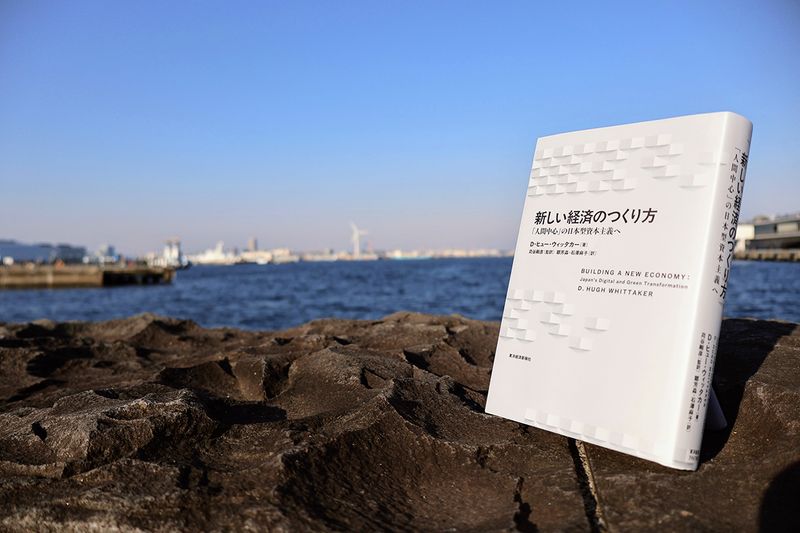――ご著書では、デジタル化を中核としたDX(デジタル・トランスフォーメーション)と、エコロジーと持続可能性を意識したGX(グリーン・トランスフォーメーション)を日本経済再生のキーワードに据えています。前者に関して言えば、2010年代前半から日本でもクラウドコンピューティングが社会に浸透し始め、企業もSaaS(サービスとしてのソフトウェア)製品を使い始めました。こうした製品やサービスを活用したDXの日本における進み具合をどうお考えでしょうか。
ウィッタカー:友人のボブ・コール(米カリフォルニア大学バークレー校 ハース・スクール・オブ・ビジネスのロバート・コール名誉教授)が、日本におけるソフトウェアに関する論文を書いたことがあります。企業レベルでの関心の欠如、エンジニアのトレーニング不足、キャリア展望の乏しさなど、製造業重視の裏返しとしてソフトウェアが軽視されているという内容です。
経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、専門知識の欠如、開発の外部委託、レガシーシステムへの依存といった危険性、いわゆる「2025年の崖」が警告されました。その後コロナ禍が訪れ、デジタル庁や行政のオンライン化の難しさについて議論が起こります。コロナ禍の給付金では、オンラインでアクセスできず行列ができるなどアクセスが極めて困難で、多くの不満の声が上がりました。政府は企業のDXについて語っていましたが、政府自体が変わる必要があったのです。
DXに関する本も多く出ましたが、その内容は主に、DXを単なるシステム導入に留めず、ビジネスモデル変革の文脈でどう活用するか、というものでした。つまり、経営層がDXを戦略的に考える必要性が指摘されていたのです。ただ私には、それが「アメリカははるか先に進んでいて、我々はひどく遅れている」という文脈にあるように思えました。これは「デジタル敗戦」を避ける最後のチャンスだ、という当時の大臣の発言のように、DXは常にネガティブな文脈で語られていたのです。
その背景には、ソフトウェアへの価値観の欠如と、「ものづくり」こそが日本の強みであり固執すべきだ、という考え方があるのでしょう。その裏返しが「これが最後のチャンスだ」といった議論です。だからこそ、DXやデジタルガバナンス・コードと、グリーン変革(GX)との間には興味深い対照があるように思えました。石炭への依存は批判されたものの、GXについては、ずっと前向きなトーンだったのです。
DXをめぐる物語は「失われた数十年」の延長線上にあるように見えました。一方でGXの物語は、イノベーション政策が社会的ニーズへ移行するという、Society 5.0や人間中心といった可能性と共鳴しているように思えたのです。近年はデータセンターのエネルギー消費問題などで論調も変わりましたが、当時は両立可能と見られていました。