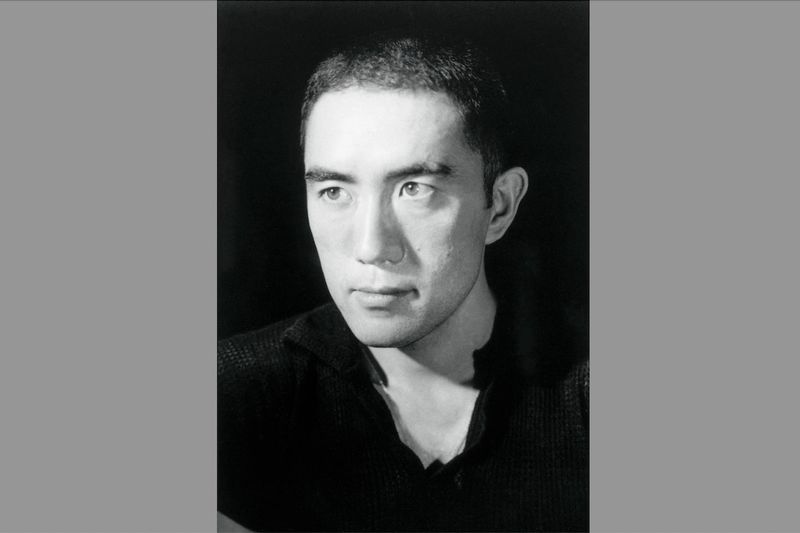なので、三島にとっては、戦後民主主義の象徴天皇制は語義矛盾であり、受け入れるわけにはいかなかった。むろん戦前の軍部に利用された大元帥としての天皇とも異なる。それを、滅びざるを得ないみずからの肉体を無にすることで、国体としての天皇制を打ち立てるための憲法改正であり、自衛隊蹶起だったが、三島の脳髄に結末は見えていたはずだ。
最後に付け加えたいのは、こうした言葉と行動の矛盾の高次的解決(アウフヘーベン)を三島特有の合理的思考だけで遂行できたとはどうしても思えないことだ。
ひとは論理だけでは生きられない。膨大な作品群をながめていると、三島はどこかで感情の源泉、つまり「海」に還ろうとしていたのではないか?
三島の作品にはよく海が出てくる。『潮騒』しかり、『午後の曳航』しかり。遺作の題名を『豊饒の海』としたのは、アポロ計画で人類が到達した月の表側にある盆地名に由来する。当然に水も空気もない岩石だけの場所と、豊饒(ほうじょう)という言葉のギャップに作意を込めたはずで、自裁決行当日に脱稿した演出も、現実の死(=行動)を前にした言葉(=観念)との交錯を感じさせる。
「海」は、三島があこがれたギリシャの語法では女性名詞になる。一方、日本語には文法上名詞に性別はないが、常用字解(白川静著)によると、海のつくりの「毎」は、「多くの髪飾りをつけた女の姿」とある。
三つ子の魂、百まで━━たとい癇癪持ちの祖母に息子公威を奪われていたとしても、母平岡倭文重(しずえ)が息子に注いだ愛情を感じない三島ではなかったはずだ。
海=言語的表象としての母への追慕を、三島由紀夫はずっと精神の奥底に隠し持っていたのではないか━━。