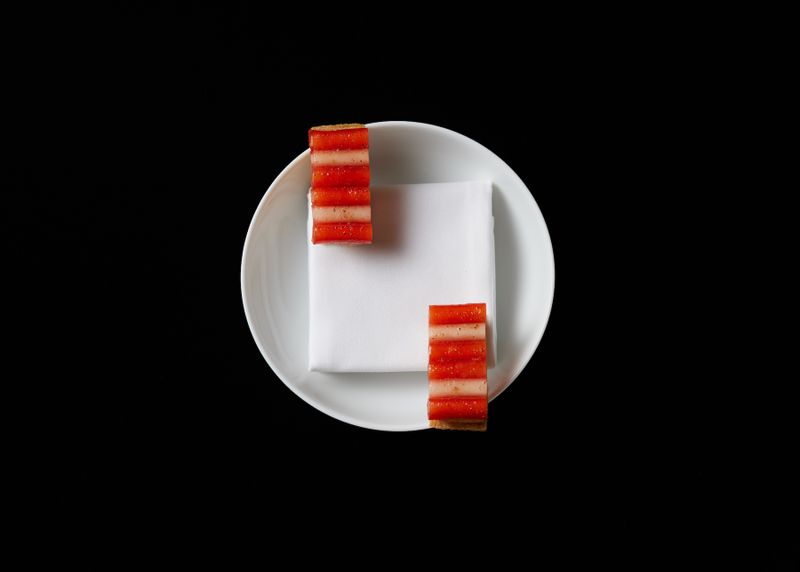荒井氏自身は1年間過ごしただけなので、フランスでの実体験があるわけではない。けれど、「修業を始めたのがちょうどバブル期で、それ以前のフランスの料理をそのままコピーするのがよしとされた時代でもあり、ギリギリ、本場の料理を学ぶことができました」と振り返る。
「過去のレガシーを学び、毎年海外に出て、今のフレンチを体感する。また本などで勉強し、フランス料理の時間軸を俯瞰し、合体させるようにしています」
料理をするうえで一番大切にしていることを聞くと、しばらく考えたのち「こだわり過ぎないことかな」と、意外とも思える答えが返ってきた。
とはいえ、もちろんそれは手を抜くという意味ではない。たとえば、素材には習慣のように塩、こしょうをするけれども、それは本当に必要なプロセスなのか突き詰めて考え、結論を出す。そうした根幹にかかわる部分は考え抜くけれど、料理を仕上げるにあたっては、こねくりまわしすぎない。あくまでストンとシンプルに自然に見えるように仕上げることを表している。

その姿勢は素材選びにもあらわれている。仕入れは豊洲と生産者からの直送の両方だが、生産者は顔の見える人としか取引しない。しかも何十年と付き合いのある生産者には、すっかりまかせている。
「とにかく一番のものを持ってきて」という姿勢でもない。気候などの影響で例年の60%しかポテンシャルのない素材であったとしても、それを責めるわけではなく、残りの40%をどうするかが自分たち料理人の仕事、そのように考えるのだという。そうしたところもこだわり過ぎないという言葉とともに、素材と真摯に向き合う覚悟がにじむ。
一方、労働環境の話になると、荒井氏は一転して豪快に笑う。「ブラック大賛成ですよ」と。でなければ、身につけなければいけないことも身みにつかないというのだ。
「人間一生の中で一時期は、寝食忘れて没頭し、数をこなさなければ、本当の意味で体にしみ込まない。数が質を凌駕する瞬間があるのですよ。例えばフードロスのようなことに関しても同様です。だからこそ、がんばりたいスタッフにはやらせるようにする。その時期はグチや文句をいっても構わないと思っています。ただ、それが本人の糧になればということは真剣に考えていますね。後進に何かを残してあげたいと」。この言葉からは、厳しさの中にある愛情が透けて見える。