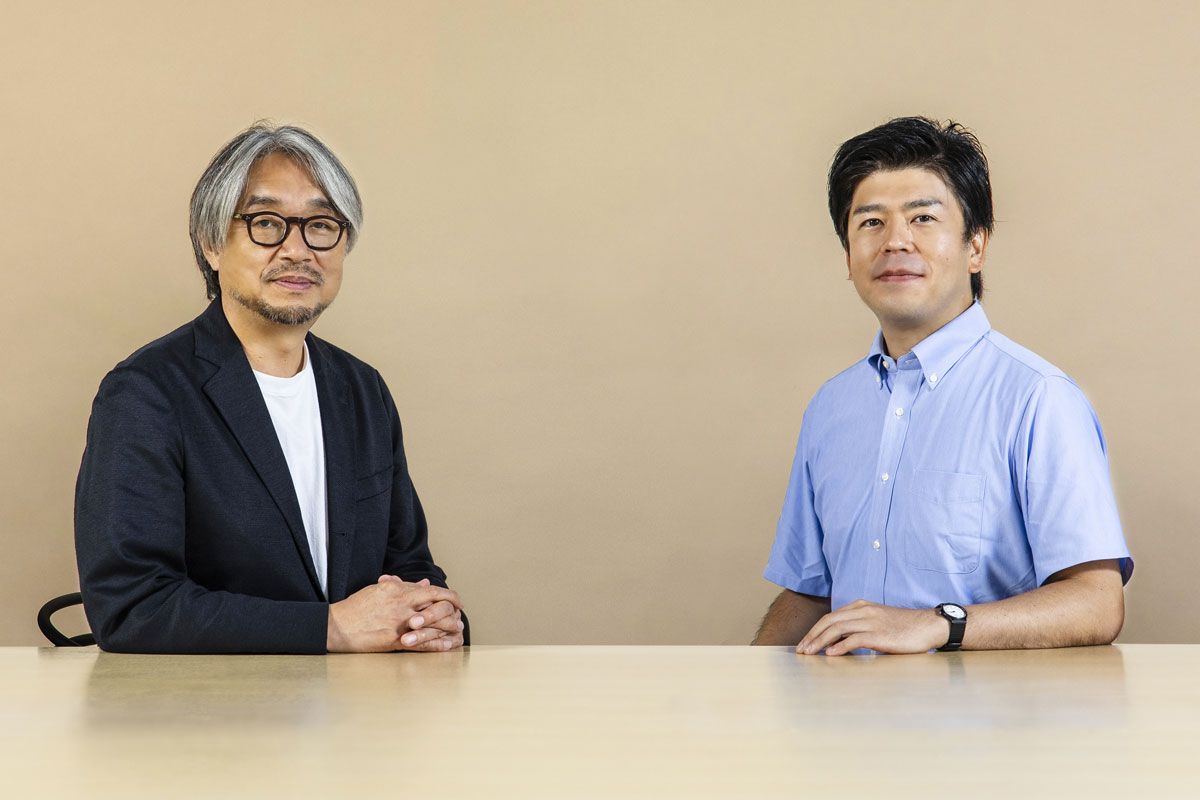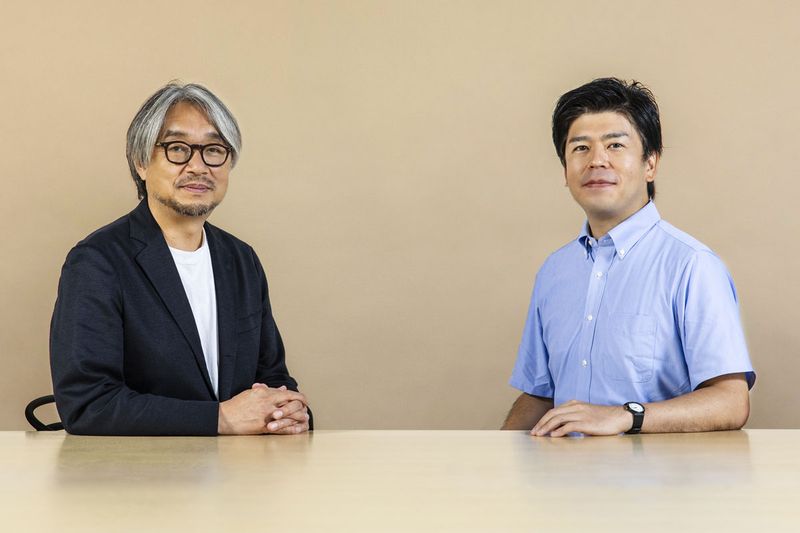「食を通じて、いのちを考える」を掲げる大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」と Forbes JAPANが連動し、食の未来を輝かせる25人を選出した。生産者、料理人、起業家、研究者……。本誌 11月号では、豊かな未来をつくる多様なプレイヤーを紹介する。
食物連鎖というが、“食べられる”ことについてどれほど考えたことがあるだろうか。 万博プロデューサーと食の倫理学者が閉ざされたテーマについて語り合う。
太田和彦:先日、EARTH MARTを拝見しました。食の倫理は「食べる・食べられる・食べさせる」の組み合わせでフードシステムを考えるのですが、一般的には「食べる・食べられる」だけが語られがちです。展示では生産や流通、調理といった「食べさせる」側に光が当てられていたのが印象的でした。卵のシャンデリアや家畜の写真など、あれらはどんな思いから実現されたのでしょうか?

小山薫堂:僕は脚本家の倉本聰さんが好きで、大学の卒業制作で北海道に滞在し、ソーセージ職人の平林英明さんのドキュメンタリーをつくりました。時を経て、憧れの倉本さんとも親しくなり、二人の旅番組で平林さんの元へ。そこで、そのころには養豚もされていた平林さんに、豚の出荷時に罪悪感を感じないかと尋ねました。すると、「まったくない。自分がつくらなければ存在しない命を、できるだけ良い環境で育て、ご苦労様という気持ちで送り出している」と。その誇りに感激して。家畜はとかく屠殺シーンが訴えられがちですが、自分たちのために生まれてくる命に心を寄せるほうが豊かだと思い、家畜写真家のタキミアカリさんに撮影いただきました。
太田:すごく良かったです。あの会場では、私たちの日々がどれほど多くの食べ物と人々の働きに支えられているかが直感的に伝わってきました。
小山:先生の研究はどこに向かうのですか?
太田:「大加速」後の食について考えています。食の倫理が必要になったのは、1950年代以降、人が膨大な食べ物を“選べる”ようになってから。だから議論は「何を食べるべきか」に偏りがちですが、それでは循環の全体像が見失われます。そこで私は「食べられる」側としての人間の語られ方に着目しています。例えば藤子・F・不二雄作の「ミノタウロスの皿」という漫画では、人類が家畜となる星で「食べられることは最高の誉」というその星の価値観に混乱する主人公の話を描いています。