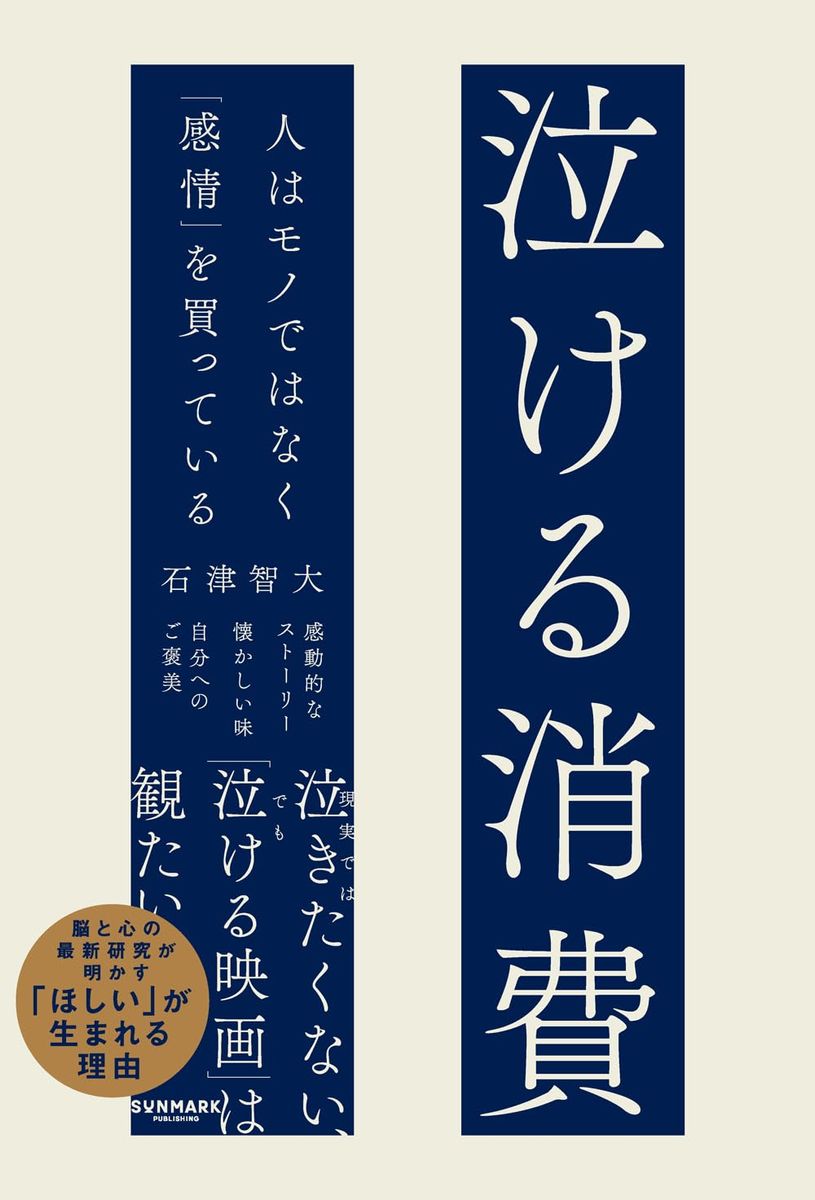また、「壁」は物理的なものとも限りません。
「これは物語ですよ」「演出ですよ」と受け取れる表現、ビジュアル、語り口が壁になることもあります。
たとえば、スタジオジブリのアニメーションは現実ではあり得ない世界を描きながらも、深い感情を呼び起こします。
あるいは、『君の名は。』のようなアニメーション映画が実写よりも多くの涙を誘ったり、『この世界の片隅に』のような戦争アニメが実写の戦争映画より深い共感を呼んだりするのも同じ理由です。
「嘘っぽさ」や「非現実性」は、むしろ安心して「感情を全開で体験できる」ための装置なのです。
リアルすぎる広告は届かない
この「感情の安全地帯」をどう設計するかは、広告やマーケティングにもそのまま応用できます。
感情に訴えかける広告を打ったり、マーケティングをしたりするには「リアルすぎてはいけない」のです。広告やブランド映像が過度にリアルな感情を描くと、消費者は防衛本能から心を閉ざしてしまうことも考えられます。
結果として、本来伝えたかったメッセージが届かなくなってしまうことがあるのです。
たとえばYouTubeを観ていると表示される広告の中に、「苦手な広告がある」と話す人がいました。それは貧困家庭を支援する団体の広告で、「給食がない日は食べるものがなくて、おなかを空かせている子どもがいます」というようなメッセージが流れるものでした。
広告を出す目的は一般の人の問題意識を喚起して共感してもらい、最終的にはその支援活動をしている団体に寄付してもらうことのはずです。
ところがその人が言うには、「広告があまりにも生々しすぎて、観たくないという気持ちが先だってしまう」のだそうです。
YouTubeの広告は始まってから5秒経つとスキップできるので、その広告が流れるといつも最後まで観ることなく即座にスキップする。だから寄付にまで至らないそうです。
いくら真剣なテーマであっても、視聴者が「向き合えない」と感じてしまえば、そのメッセージは届きません。
だからこそ、広告の世界では「どこまで現実を見せるか」「どこから虚構としてデザインするか」のバランスが問われます。
たとえば、実際に貧困に苦しむ子どもの表情や生活が映し出され、ナレーションが「貧しくて今夜のご飯にも困っている子どもが、家族を支えながら必死に働いている」と語りかけるようなストレートな表現は、たとえ事実であっても、観る人の心に負担をかけてしまいます。
一方で、画面に映すのは本人ではなくイラストにして、「もし、今この瞬間にも、あなたの知らない場所で、誰かが明日の食事を心配しているかもしれない」と、少し距離をとって語りかけると、より受け手に届きやすくなるかもしれません。
とはいえ、あまりに遠回しな表現では、普段から他者への関心が薄い人や、「貧困は自己責任だ」と思っている人の心には届かないかもしれません。
だからこそ、広告においても、「リアルさ」と「フィクション性」の境界をどこに引くかが問われます。
感情を動かすには、その表現を受け取る人の心が安全であるための設計が欠かせない。
エンタメと同じように、広告にも感情の安全地帯が必要なのです。