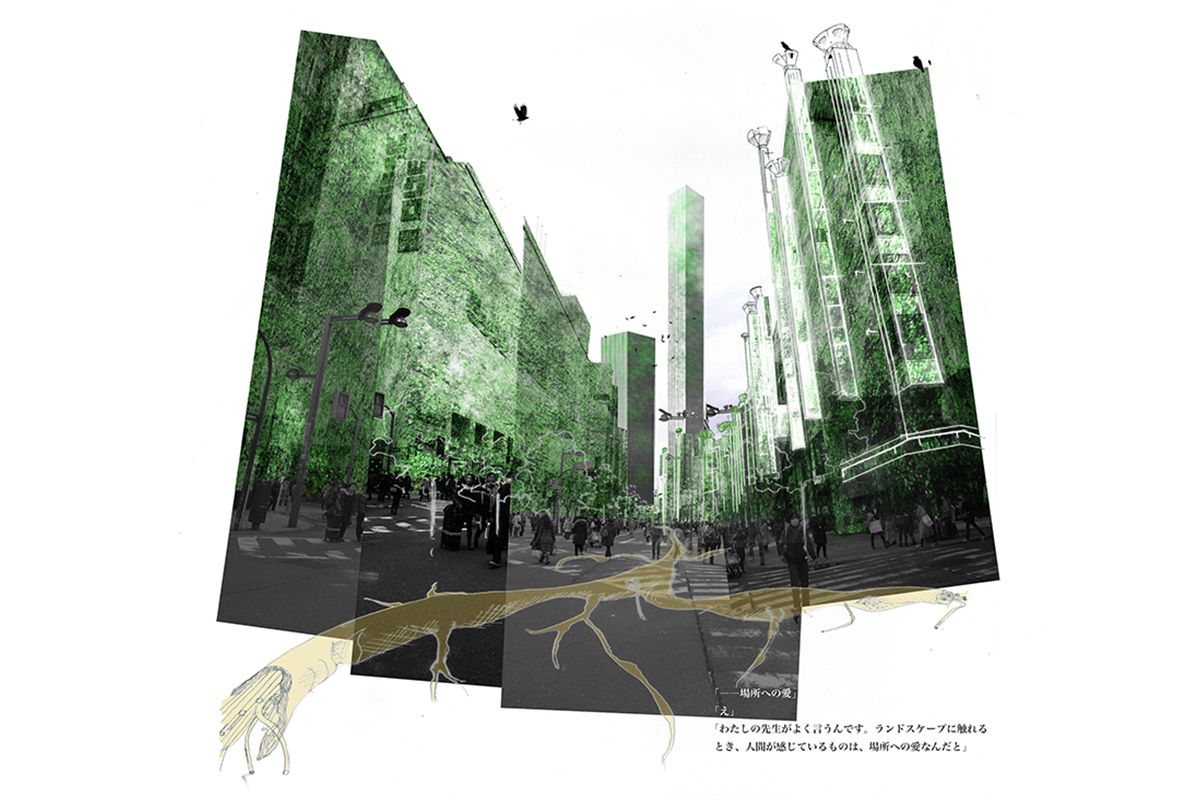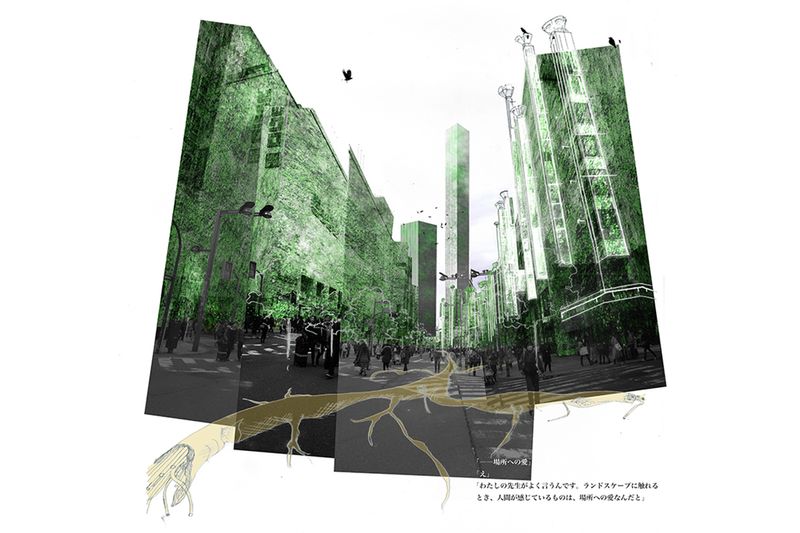AIが未来を語り、アルゴリズムが意思決定を支援する今、企業のビジョン策定や事業構想には、「人間にしかもち得ない想像力」が不可欠です。前回の記事では、まだ存在しない未来を仮想のデザインとして提示し、新しい可能性を示す「スペキュラティブデザイン」を通じて、未来を想像する方法に焦点を当てました。今回はその探求を深めるため、SF作家の津久井五月(つくいいつき)氏にお話を伺いました。
津久井氏は東京大学・同大学院で建築学を専攻する傍ら、テクノロジーによる人間や社会の変容に焦点を当てたSF小説を執筆しはじめ、『天使と重力』で日経「星新一賞」学生部門準グランプリを受賞。さらに『コルヌトピア』ではハヤカワSFコンテスト大賞を獲得、2021年の『Forbes 30 Under 30』にも選出された新進気鋭の作家です。企業や行政と協働で、SFをベースに未来のシナリオを描き、そこから逆算して課題解決の道筋を探るSFプロトタイピングにも取り組まれています。
SFは、物語という形式を通じて世界をとらえ直すとともに、非連続な未来を構想し、社会に問いを投げかけるアートの一形態とも言える表現。現実とフィクションの狭間から、未来を照らす想像力の源泉はどこにあるのか。AIの時代にこそ生きる、人間ならではの想像力とは何か。その核心に迫りました。
雨から臓器売買へ、始まりは日常の小さな好奇心
平岡:未来を想像するときやSFを創作するとき、どのようなスタンスで臨まれていますか。
津久井:僕は、これまでに誰も見たことがないような未来を提示したいとは思っていません。そういうモチベーションだと、作品が空回りすることが多くて。未来は、現在を見つめ直すための架空の舞台として使うほうがうまくいく。
そして世界を丸ごと変えず、「違う要素はひとつだけ」という創作ルールが自分の中にあります。それにより、読者も「もしそれが現実だったら?」と想像を膨らませ、現在を新たな視点でとらえることができるんです。
例えば、現時点では遺体の臓器を取り出して他者に臓器提供できる時間は非常に限られているのですが、遺体の細胞を保存する技術が生まれ、臓器移植のタイムリミットを大幅に延長できる社会を仮定してみる。そしてそれが臓器移植や臓器売買を含めて、人間関係や犯罪にどんな影響を与えるのか。そうした波及を描くことで、今の社会のあり方が見えてきます。
平岡:実際、どのようにして未来や物語を発想されているのでしょうか。
津久井:ある日、雨がザーザーと降っている様子を見て、ふと、何か雨って面白いなと思ったんです。そこから「特殊な力をもった雨が、身体に染み込んだらどうなる?」と連想が始まって。さらに身体の話になり、臓器や生死の話につながって……。気がつけば「臓器保存技術の進化によって、死後も臓器を長期間流通させる世界」の物語に発展していました。最初から臓器売買を書こうと思っていたら、できなかったかもしれない。
平岡:面白いですね。身近でリアルな感覚からスタートして、連想の果てにたまたま社会的テーマへと行き着く。
津久井:自分がリアルに感じられる世界って、せいぜい半径50kmくらいの話だと思っていて。メディアで知る情報より、日常で触れる風景や人間関係の方が、圧倒的に実感がある。だからこそ、身の回りの手触りの中で自分が感じたことを出発点にして書いています。
平岡:五感や実体験に基づく感覚、これは人間ならではだと思います。