AI技術の進化が加速するなか、製造業では、点在したデータや経験といった資産を、いかに活用できるようにするかが問われている。AIと共に価値を生み出していくために、企業が備えるべき視点とは何か。早稲田大学GCS研究機構の速水悟(以下、速水)と、ビジネスジャーナリスト・経済キャスターの瀧口友里奈(以下、瀧口)が語り合う。
AI活用が日本の製造業の優位性を最大化させる
瀧口:今回は「製造業はAIをどう活用すべきか」というテーマでお話を伺いたいと思います。速水先生は、日本の製造業の現状をどのように見ていらっしゃいますか。
速水:メディアでは日本企業は、否定的に語られることが多いのですが、日本の製造業はそのようなことはありません。技術力やブランド力は依然として高く、世界と戦える力があると考えています。人工知能分野では日本は後れをとってしまいましたが、応用となるとまだこれからで、日本の製造業には大きなチャンスがあると見ています。日本でAI活用がなかなか進まないのは、技術の問題ではなく、意思決定のスピードが遅いことに起因しているのだと考えています。
瀧口:そのような状況の日本の製造業にとって、AIを活用する価値とはどのようなものなのでしょうか。
速水:業務にまつわる“暗黙知”や属人化したノウハウが多い製造業において、AI活用のメリットは非常に大きいと考えています。瀧口さんの編著による『東大教授が語り合う10の未来予測』(大和書房)でも語られていた「人間の能力をテクノロジーによって増強・拡張させる」という未来像は、まさに製造業におけるAI活用の可能性を示していると思います。知識やノウハウ、つまり“暗黙知”をAIに学習させることで、“形式知”として蓄積・共有し、新たな価値を生み出すようなサイクルを回せるようになるはずです。
瀧口:AIが知識やノウハウの橋渡しをしてくれるようなイメージですね。
速水:そのような“暗黙知”を活用できる基盤を構築することが重要になってきます。過去の設計データや改善履歴、トラブル対処法などを体系化し、活用できる仕組みがあれば、若手技術者の成長スピードは格段に上がるでしょう。これは技術の継承だけでなく、企業全体の競争力強化にもつながります。
さらに、データ基盤によってバリューチェーンをつなぎ、各工程でデータの活用を行うことができれば、過去のデータをもとに設計段階でリスクを回避したり、手戻りを減らしてリードタイムを短縮することが可能になるはずです。結果として、品質の向上と開発スピードの加速の両立が実現できるのです。
瀧口:とはいえ、他の業種に比べると製造業におけるAIの活用はまださほど進んでいないように見受けられます。
速水:現状ではまだ潜在的なレベルにとどまっているといえますね。外観検査や予防保全といった領域でのAI活用は進んでいますが、コアとなる領域では十分に使いこなされていません。とりわけ設計工程は、ベテラン技術者の専門的な知識と経験に頼る部分が大きい。これを属人化させたままでは、次の製品開発に時間もコストもかかってしまいます。
現場に散在する情報をAIで活用可能に
速水:データ基盤を構築してAIを活用するにしても、現場に散在する設計図面や報告書、トラブル事例、試作記録といった多様な情報を、AIが処理できるように整理する必要があります。つまり、非構造化データを構造化データに変換しなければなりません。非構造化データが多い現場では、情報の価値を活かしきれず、「同じ失敗の繰り返し」や「ノウハウの属人化」を招く原因になります。これは非常にもったいないことだと思います。
瀧口:情報がいくら蓄積されていても、現場で活用されないまま埋もれてしまっては意味がありませんね。
速水:今ではAIの力を借りれば、比較的簡単な処理で非構造化データを構造化データに変換することが可能になっています。従来は単なる“記録”に過ぎなかったものが、AIの活用によって“資産”へと生まれ変わるのです。
製造業が長年にわたって築いてきた知見や記録は、それ自体がかけがえのない競争力の源泉です。AIの力を借りることで、そうした積み重ねが未来に活きる戦略的な資源へと転換され、新たな価値につながっていくのです。
瀧口:まさに、データを未来に活かす視点が必要ということですね。
速水:その通りです。データは蓄積するだけでは意味がありません。過去の知見を活用し、再利用できるようにすることが重要です。大切なのは「価値を生み出す」だけでなく、「価値を獲得する」ことです。
例えば、これまで現場に蓄積されてきた記録や知見をAIで整理・活用することで、再現性のある設計プロセスを構築したり、次の開発への応用につなげたりすることが可能になります。見過ごされがちだった知の蓄積に新たな視点を与え、そこに埋もれていた価値を見出していく姿勢が、これからの製造業に求められているのです。
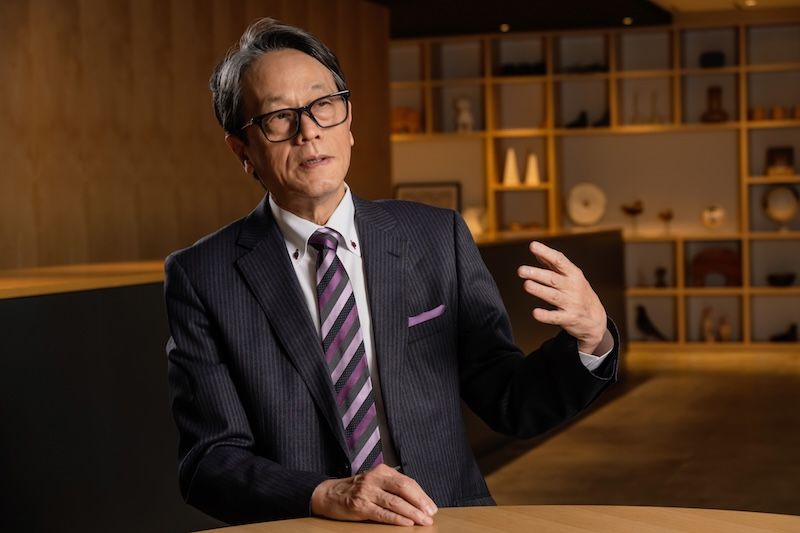
瀧口:最近では「AI導入」自体が目的化してしまうケースも見られますね。
速水:AIは「導入」ではなく「活用」が本質です。ツールを導入しただけでは意味がなく、使いこなす人材がいて初めて価値が生まれるということです。AIの活用には、ツールだけでなくAIを活用できる人材の育成が重要であるといえます。
人材を育てるAI共創──スタートアップとの協業が未来をつくる
瀧口:最近ではDXやAI活用を支援するスタートアップ企業も増えていますが、こうした企業のサービスについてはどのようにお考えですか。
速水:多くの経営層はAIの進化を理解していても、「自社ではどう活用できるか」をイメージできていないのが実情です。それが「自分たちには関係ない」と思ってしまう要因になっています。だからこそ、外部企業との連携が鍵になります。まずはAIを「使ってみる」というマインドが大事だと考えています。
瀧口:ベンダーと連携する際、取り組みをスムーズに進めるためには、どのような視点が必要だとお考えですか。
速水:ベンダーとユーザーという関係にとどまらず、共に学び、価値を共創する姿勢が重要です。ただし注意すべきは、相手に製造業の知見があるかどうかです。AIの知識だけではなく、業界への深い知見がなければ実装はうまくいきません。いくら優れたソリューションでも、現場で使われなければ絵に描いた餅になってしまいます。さらに言えば、ソリューション構築では内製に固執せず、利用可能なサービスは積極的に取り入れるべきです。AIの進化は非常に速いため、技術的なキャッチアップでは外部の支援を得ながら、自社のコア領域にリソースを集中させることが、競争優位につながります。
瀧口:AI活用の価値を最大化するには、自社内でAI人材を育成することも欠かせません。同時に非連続的に成長するAIに対して、AIの知見とスピード感をもっているスタートアップとの協業もその一助になりそうですね。
私は以前、製造業の変革を推進するスタートアップ、キャディの代表取締役 加藤勇志郎さんにインタビューしたことがあるのですが、同社は、祖業である加工品の受発注を行うプラットフォームでのモノづくりの実体験と、AIやテクノロジーに関する知見を活かして、現在はAIネイティブなプロダクト、「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を提供しています。こうした業界に精通した企業の力を借りることも、製造業におけるAI活用の浸透を促すきっかけになりそうですね。

速水:ドメインナレッジを持っているというのは、ものすごく価値がありますね。AIスタートアップ企業は、ITやAIの技術に長けていても、現場のことを知らない場合が多いのではないかと思います。製造業とAIの両方を理解している人材は貴重といえます。さらに言えば、AIソリューションを外部パートナーと一緒に使っていく取り組みこそが、AI人材が育つ土壌の醸成につながると思います。人材育成は時間がかかるものです。だからこそ、今から準備を始める必要があると私は考えています。
例えば生成AIも個人の生産性を高めるツールとして使われ始めていますが、製造業ではまだまだこれからといった状況です。ただし、活用が本格化した際に出遅れないよう、非構造化データの構造化と並行して、人材育成に取り組んでいくべきです。
瀧口:製造業が本質的に変わるためには、現場だけでなく、経営層の視座や判断にも変化が求められていると思います。AI時代を迎えるいま、経営層にはどのような意識転換が必要なのでしょうか。
速水:大切なのは「長期的視点」を持つこと、そして、AIの活用をROIだけで評価しないことです。なぜならAI活用はAI人材を育成する取り組みにほかならないからです。もう1つ付け加えるなら、若手社員をAI人材として育てる際、送り出す上司やリーダーには、自チームの戦力ダウンととらえるのではなく、長期的な視点で学びを支援してほしいと思います。
瀧口:企業の変革に貢献するような若手社員を見出し鼓舞することが重要だと思います。新しい挑戦をチームにも後押ししてもらえると心強いでしょうね。
ドメインナレッジとAIで製造業の変革を目指すキャディとは

キャディは「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を目指すスタートアップ企業だ。
プロダクトの「製造業AIデータプラットフォームCADDi」は、加工品の受発注のプラットフォームとしてモノづくりを行ってきた経験と製造業に特化したAIで、非構造化データを構造化。社内に点在するデータを統合し、文脈を持つデータ基盤を構築する。アプリケーションによって部門を超えたデータ活用を実現し、生産性向上・脱属人化・QCD最適化といった経営課題を解決に導く。 現在は、「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウドCADDi Quote」 という2つのアプリケーションを提供し、今後も様々なアプリケーションを開発・提供しながら、製造業の構造改革に挑戦していく。
はやみず・さとる◎早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム(GCS)研究機構。東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻修士課程を1981年に修了後、通商産業省工業技術院電子技術総合研究所、岐阜大学教授として活躍。2021年4月よりGCS研究機構。著書『製造業向け人工知能講義』(日経BP)
たきぐち・ゆりな◎ビジネスジャーナリスト、経済キャスター、東京大学工学部アドバイザリーボードメンバー。東京大学卒。現在「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」(日本テレビ系列)全国生放送のコメンテーターや経済キャスターのほか、SBI新生銀行社外取締役、グローブエイトCEOを務める。書籍「東大教授が語り合う10の未来予測」を編著。新メディア・アカデミアコミュニケーションプラットフォーム「アカデミアクロス」を立ち上げ、<映像×出版×イベント>を通してアカデミアと社会を繋げている。世界経済フォーラム ヤング・グローバル・リーダーズ2024(YGL)に、日本人のアナウンサー・キャスターとして史上初めて選出される。












