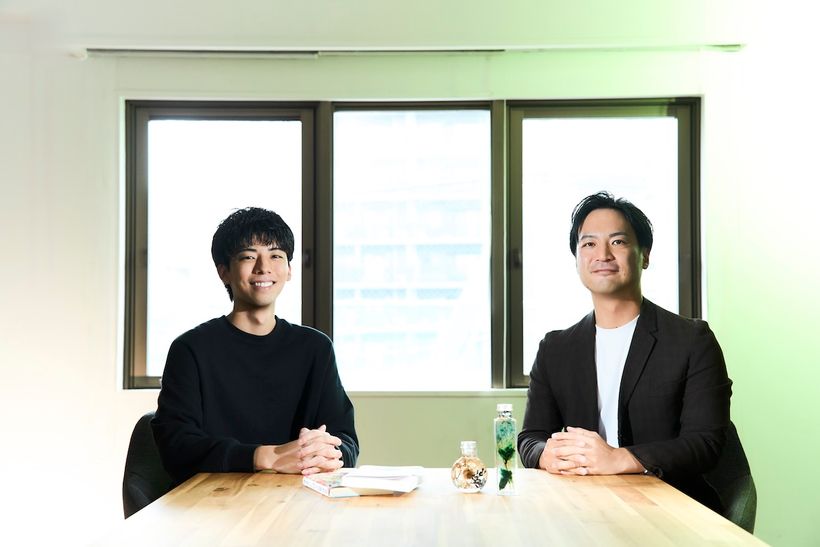「持続可能性(社会的インパクト)」と「成長(経済的リターン)」の両立を目指す社会起業家やスタートアップなどと自治体・大企業等との共創を促進し、社会課題解決を図るプロジェクト「TOKYO Co-cial IMPACT」が、昨年度に続き、本年度も実施される。
今回の記事では、北九州市の介護施設の夜間医療体制をスタートアップのサービスによって解決した実証事業の事例を紹介する。
社会課題解決と官民共創を両立させたこの事例はどのようにして成功をおさめたのか。自治体とスタートアップの接点を「逆プロポ」によって創出したソーシャル・エックス代表取締役の伊藤大貴、実際に実証事業に取り組んだドクターメイト代表の青柳直樹に、自治体とスタートアップとの共創における課題や成功のポイントを聞いた。
行政とスタートアップに根付く「思い込み」をなくす
伊藤が代表取締役を務めるソーシャル・エックスでは、社会課題解決を目的とした新規事業開発へのさまざまなアプローチを展開している。なかでもここ数年注目されているのは、「逆プロポ」の企画・運営だ。「逆プロポ」とはその名の通り、従来の公募プロポーザルの流れを逆転させたもの。企業が関心のある社会課題を提示し、それに対して自治体が課題解決のための企画やアイデアを提案することで、マッチングを図る仕組みだ。
「社会的インパクトと経済的リターンの両立の実現に官民共創は重要な役割を果たしますが、課題も少なからず存在している」と伊藤は語る。
「社会的インパクトと経済的リターンは、そもそも相反する性質のもの。企業からすると、インパクトを重視すればビジネスとして成り立ちにくいという難しさがあります。一方、行政は社会的な意義も重視して協業先を判断します。それだけでなく、官民それぞれに両者に対する“思い込み”があり、それが歩み寄りを難しくしているのです」(伊藤)
官民両者それぞれの「思い込み」は、日本の商習慣に長らく根付く、受発注の関係性が大きく影響している。端的に表現すれば、「行政は予算を出す側」で、「企業はその予算で何かをする側」という固定観念が両者に存在し、それが官民共創の本質を阻害しているという。
「そうした固定観念を打破するために、私たちは『官民共創』ではなく、『行政と企業のオープンイノベーション』という言葉を使っています。企業にとって行政は『ビジネスの成長に足りないものを提供してくれる存在』、行政にとって企業は『地域が抱える社会課題をB to BやB to Cという形で解決してくれる存在』というように、オープンイノベーション的な発想に切り替えるのです。すると、課題の本質がより浮き彫りとなり、金銭以外の部分でのコミュニケーションがより活発化し、共創の可能性は大きく広がります」(伊藤)
ソーシャル・エックスが打ち出している逆プロポはまさに、「行政と企業のオープンイノベーション」を形にした新規事業開発のプラットフォームだ。お互いの強みを活かし、シナジーを生み出すことを促進する。
「受発注の構造だと、やり取りに入札や予算といった要素が介入するため、両者の公平性が担保されず、できることが限られてしまう場合が少なくありません。一方、逆プロポなら、いろいろな企業や自治体がフラットな立場で出会え、同じ目線で自由にアイデアを出し合えます。それが最大のメリットといえるでしょう」(伊藤)

実証だけでは終わらせない。インパクトを定量的に計測
ソーシャル・エックスが運営する逆プロポで実際にプロジェクトを成功させたのが、介護施設のオンラインサポートを提供するドクターメイトだ。
背景には、世の中の高齢化に伴い、医師が常駐しない介護施設では、現場スタッフの夜間緊急対応の負担が大きいという社会課題がある。その負担を軽減すべくドクターメイトが提供するのが、介護施設に代わって自社の看護師が夜間対応を行う「夜間オンコール代行サービス」だ。このサービスに介護領域の戦略特区に選定されている北九州市が興味を示し、逆プロポにエントリーしたのをきっかけに、プロジェクトがスタートした。
「スタートの時点での北九州市さんと私たちの共通認識は、アウトプットではなくアウトカムを出したいということでした。ただの実証で終わるのではなく、定量的にインパクトを出すためにはどうすればいいかをとことん話し合いました」
そう語るのは、ドクターメイト代表の青柳だ。両者で毎日のようにディスカッションを重ね、目的と役割分担を設定。出会いからわずか3週間後には、市内の17の特別養護老人ホームに『夜間オンコール代行™』が導入され、実証実験が始まった。
「介護領域には、介護団体、医師会、消防局など、多くのステークホルダーが存在します。その間の調整を一企業が行うのは、至難の業です。サービスを導入するにあたり、それらのステークホルダーとの調整を北九州市の担当者が率先して担っていただけたことに、大きな価値があります」(伊藤)
実証実験では、サービス導入によって「60%以上の夜勤スタッフの心理的な負担を減らした」という結果が得られた。また、減少を期待していた緊急搬送の数についてはインパクトのある数字こそ出なかったものの、検証期間がコロナ感染が拡大していた時期であったことを考慮すれば、十分な検証データが得られたという。
「プロジェクトを成功裡に終え、あらためて感じたのは、私たちにも自治体への偏見があったことです。照合データの取り寄せや、設計の見直しなど、熱量とスピード感を持ってご対応いただいたことで、行政への見方が大きく変わりました」(青柳)
「何よりも重要なのは、ビジョンの共有です。当初からディスカッションを重ね、介護現場を持続可能なものにしたいという北九州市さんとドクターメイトさんの思いをしっかり合致させられたことが、プロジェクトを成功に導いたのです」(伊藤)
「行政と企業の“思い込み”を解消するためにも、フラットな立場でお互いが思い描くビジョンを共有し、同じ社会課題の解決を目指す同志であるという認識を持つことが重要なプロセスだったと感じています」(青柳)
ドクターメイトは、いかにして、このプロジェクトの成果を今後の「成長(経済的リターン)」につなげていこうと考えているのだろうか。
「事業を拡大していく際、まだそれほど知名度が高くない私たちが社会課題を解決『したい』ではなく、『した』という実績は、ある意味では金銭よりも大きなインパクトになり得ます。行政と強固な信頼関係を築けたことも含め、その実績は今も成長を続ける事業の礎となっていると確信しています」(青柳)

事業の新たな可能性を引き出す環境へ
ソーシャル・エックスの伊藤は、ビジネスを通じて社会課題解決を目指す社会起業家・スタートアップ、自治体担当者、大企業等を対象とした「TOKYO Co-cial IMPACT」のエントリープログラムで講師を務めている。
「TOKYO Co-cial IMPACT」では、社会課題解決を目指すビジネスの起業・成長や、自治体等がそれらの企業と協働する際に必要な知識が学べる講義や実践的なワークショップなどを、目的に応じた3つのコースに分けて提供している。
伊藤はプログラムの意義や活用方法について、「講義から実践まで多彩なプログラムが用意されているので、起業を目指している人も事業を伸ばしたい人も、さまざまな形で役立てられる」と語る。
「これから起業を目指す人だけでなく、すでに起業したB to Bの事業において、実はインパクトの可能性を秘めているケースも少なくありません。このプログラムを利用することで、自分の想定とは違う形で事業を拡げられるかもしれないという気づきやチャンスを得ることも期待できます」(伊藤)
青柳自身もかつて、東京都のスタートアップ支援を利用した起業家の一人だった。
「ひと昔前なら、起業は、一世一代の大勝負だったかもしれません。今はどちらかというと、『選択肢の1つ』ととらえて、もし失敗したとしても、その経験を未来に生かすことができます。むしろ、社会がこれだけ多様化・複雑化した現代においては、チャレンジした実績をいかに多く積んでおくかが重要です。そのチャレンジの最初の一歩を踏み出すサポートを用意していただけるのなら、利用しない手はないのではないでしょうか」(青柳)
TOKYO Co-cial IMPACT
https://tokyo-co-cial-impact.metro.tokyo.lg.jp/
伊藤 大貴(いとう・ひろたか)◎2002年日経BPに入社。2007年から横浜市議会議員3期10年。議員在職時は公民連携の関連政策に積極的に取り組み、2017年に横浜市長選に立候補。その後、「逆プロポ」事業を立ち上げ、2021年にソーシャル・エックスを創業。著書に『ソーシャルX』『スマートシティ2025』『日本の未来2021-2030』(いずれも日経BP)など。博報堂フェロー(2019-2022)、世界銀行TDLCアドバイザー(2023-2024)。虎ノ門ヒルズインキュベーションセンターARCHメンター。ソーシャルXインパクトファンド投資責任者。
青柳 直樹(あおやぎ・なおき)◎2013年に千葉大学医学部卒業後、千葉市内の病院皮膚科医として臨床診察に従事。医師として従事する中で気づいた、介護業界の社会課題を解決すべく、2017年12月にドクターメイト株式会社を設立し、代表取締役・医師に就任。全体の経営と医療領域を管掌する。2019年、医療法人淳仁会理事長就任。土日に外来診察、介護施設への往診も行う。2023年2月に、福岡県北九州市との実証事業が、内閣府主催の地方創生SDGs官民連携取組事例の優良事例に選定された。