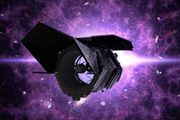過去の観測でどのくらいの光が塵によって遮られているか、そしてそれによってどのくらいの光が失われていたかが、今回の研究で明らかになったと、ヒーリーは指摘する。すなわち、より光度が低いRSGとこれまで考えられていたのは、実際は大量の塵に取り巻かれている高光度のRSGなのだと、ヒーリーは説明している。これにより、光度のより正確な測定値が得られるため、進化した大質量星の特性を正しく理解できるようになったという。
生き急いで早死にする星
今回の研究には参加していない米ビラノバ大学の天文学者エドワード・ガイナンは、取材に応じた電子メールで、赤色超巨星はスペクトル型OB型の大質量星から進化するが、OB型星は3000万年以内に燃料の水素を速やかに使い果たしてしまうと述べている。
水素が枯渇すると、中心核(コア)内でヘリウムの燃焼が始まる。
中心部でのヘリウム燃焼段階では、恒星の大きさが急速に増大し、膨張して温度が低下し、RSGになると、ガイナンは説明する。この時期の恒星からは、核融合反応でできたガスが大量の恒星風によって噴出する。これにより、核融合反応でできる炭素、窒素、酸素が星間媒質に供給されるという。
ガイナンによると、銀河系で最も大きくて高光度の恒星の1つである、おおいぬ座VY星(VY Cma)は、次に発生する裸眼で見える重力崩壊型超新星の有力候補とされる。
VY Cmaは、南天のおおいぬ座の方向約3800光年の距離にあり、崩壊して超新星になるために理論上必要な下限値の8太陽質量をすでに大きく上回っている。
ガイナンによると、このII型超新星は通常、太陽質量の数倍の電離ガスを星間媒質中に放出する。これによって衝撃波が発生して拡大することで、星形成の促進につながるという。
この問題に取り組む理由は何だろうか。
すべては、太陽系が属する銀河系内と遠方の銀河における恒星の生と死に端を発する。天体物理学者がRSGの進化から収集できる情報が増えれば増えるほど、地球が属する太陽系と他の同様の恒星系に関する理解がますます向上する可能性がある。
ヒーリーと研究チームが研究に使用したサンプル群のデータは、NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)とハッブル宇宙望遠鏡(HST)および欧州宇宙機関(ESA)のガイア宇宙望遠鏡(Gaia)の観測データから主に取得した。さらに、米ハワイ島にあるUK赤外線望遠鏡(UKIRT)の大規模サーベイ観測や、米国とチリで実施された近赤外線波長域での全天サーベイ観測プロジェクト2MASS(Two Micron All Sky Survey)などの地上サーベイ観測のデータも使用した。