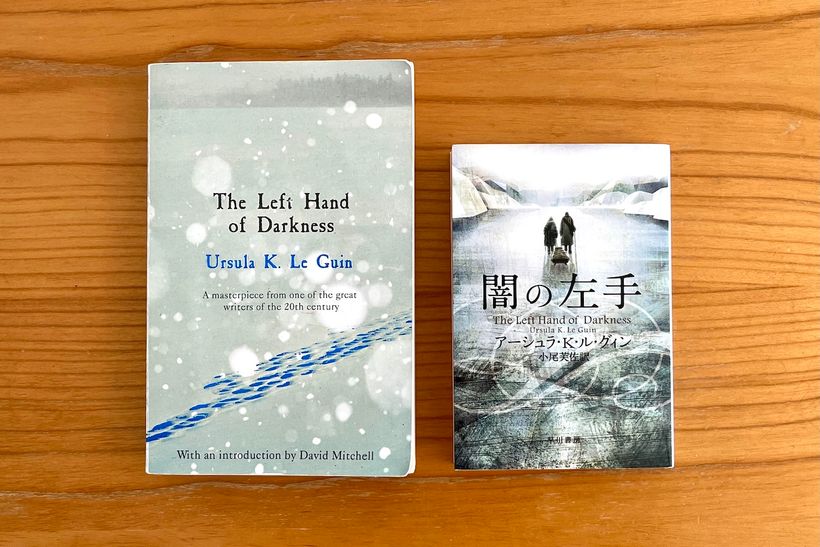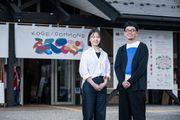安西さんに原稿をいただいた頃、私のソーシャルメディアのタイムラインでは、日本のアニメーション制作会社スタジオジブリの作風を模したAI生成画像で溢れかえっていました。
OpenAIがリリースした新モデル「GPT-4o」が画像生成機能を搭載したことで、発売直後から世界中の人たちが人気アニメ風に自分の写真を変換し、シェアするという現象が起きたのです。OpenAIによると、このモデル登場以降、アクティブユーザー数、アプリ内課金収入、アプリダウンロード数はいずれも過去最高を記録したといいます。
「アニメの世界のキャラクターになる」という生成画像を純粋に楽しむ人たちの顔が浮かぶ一方で、そもそもこの技術は必要だったのだろうかという疑問が拭えません。私の周りには、画家やイラストレーターなど、このような開発によって、より社会的に弱い立場に追いやられる人たちがいます。AIによって創作のスキルや表現力が開かれたものになる一方で、今その本当の恩恵を受ける人は誰なのか。見直すべき「特権」はもっと別の場所にあるのではないでしょうか。

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、3月末の来日講演で、AI開発競争への最大の懸念は「人間同士の信頼の崩壊」だと訴えました。AI技術の特徴は、自律的に判断を下す能力、つまり「代理人としての性質」であり、私たちがまだ十分に理解できていない存在であるAIに、逆説的にも信頼を置き始めていると指摘します。
たとえば戦争の現場では、「どこを爆撃するか」のような重要な判断をすでにAIが担い、人間の将校が何日もかけていたような決断が、今は数秒で行われているといいます。
こうした現象は日常生活にも及んでいます。いまや多くのサービスにおいて、カスタマーサポートの窓口のひとつに「チャットボット」が設けられていることが標準となり、私たちはあらゆる場面でAIと会話するようになりました。数年前までは会話のぎこちなさから、相手が人間かAIかが推測できましたが、今では「ボット」だと明示されていない限り、区別はほぼ不可能です。
ラグジュアリーブランドも例外ではなく、「よりパーソナライズされた体験が顧客満足度とエンゲージメントを高める」として、個々の行動や嗜好などに基づいた商品のレコメンデーションや接客をAI主導にするケースが増えています。“24時間・年中無休”で対応するAIが実質的な顧客担当者となりつつあるのです。
あらゆる決断をAIに委ねる未来が現実味を帯びているとすると、複雑で難しい選択を迫られる場面を自ら経験する機会をどんどん失っていくことになります。一見、快適で効率的な社会の実現を約束しているようですが、私たちが向かっているのは、個人の孤立を助長する脆弱な社会のような気がしてなりません。