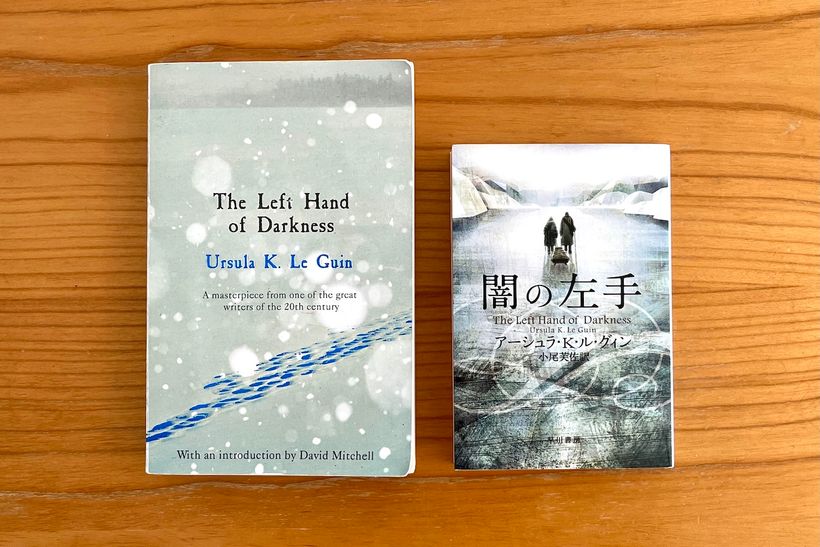それならわざわざ外国に行って不快になることもあるまいと考え、毎年、イタリア中部の農村にあるアグリツーリズモに滞在するようになったのです。この話をすると「同じ経験した」と聞くことがあるので、傾向としてまんざら的が外れているわけでもないでしょう。やはり、イタリアでは温かく接してくれる人が多い。殊に小さな子どもに対しては天使を見つめるが如くです。
ここから論を展開します。
自分の願望を実現するために短期的に情熱をかたむけられるのは大切な資質であり、往々にしてこのような人が“熱い人”と言われます。その熱さが他人へ向かい、それなりの頻度で発動すると暑っ苦しい人になります。このタイプが歓迎されることは稀で、「人は悪くないけれど」という注釈づきで距離をとられます。
ただし、「熱い思いや熱いものをもっている」は短期的ではなく継続的な姿勢を示しています。熱い人とは微妙に距離があります。
他方、温かい人にはバリエーションがない。あえて言葉を加えるとすれば、他人への寛容さを含んでおり、困っている近隣の人にも思わず助けられる人。手助けに信念を必要とするのが熱い人だとすれば、温かい人にはそのような信念とは無関係、という区別ができるかもしれません。
さらにいえば、人が助け合うような社会をシステムとしてつくろうと活動するには熱い人が活躍し、そのシステムを運営していくには温かい人が求められます。その観点を宮川さんに適用すれば、彼は熱い人であり、温かい人でもあります。しかし、人の印象としては、後者が強く残ります。

もちろん、きれいな表現に包まれた経験だけで長年に渡りイタリア生活ができるわけもありませんが、いまさらながらにして温かさがさまざまな場面で鍵であると感じるのです。
熱くなることは意識してやろうと思えばできる。多くの企業研修や自己啓発セミナーは言ってみれば、どうしたら熱くなれるか? が目標になりやすいです。動機の明確化との旗印のもとに前進できます。その意味で、実は、一見冷たいと思われる合理性と情熱は案外結びつきやすい。
しかし、温かさはそうした合理性とはまったく無縁な環境にあるものです。心の持ちようであるようでいながら、意思だけで温かい人にはなれません。こうして、ぼくはラグジュアリーと温かさが繋がるのではないかと考え始めました。
とても使い慣れた生成AIが人間以上の優しさで対応してくれ、それを温かいと思うシーンがあるとすれば、人間としての感覚がAIに接近したに違いありません。その時にAIとは距離のある感覚に引き戻してくれる人間の温かさが、ラグジュアリーと表現できるのではないかというのが、ぼくの仮説です。
結構、面食らう話題かもしれませんが、前澤さんなりに料理してみてください。