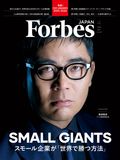「生活観察者」のスタンスで
昨年夏、インジナーシさんに会って以降、何度か話を聞く機会があった。彼にはいくつもの撮りたい題材があるのだが、その1つはモンゴル各地に住む子供たちで、とりわけ成長期や思春期を迎えた年代だという。

たとえば、草原の村に暮らす子供たちはどんな環境で育っているのか。どんな学校で学び、授業を受けているのか。子供たちにフォーカスすることで、現代モンゴルが見えてくるはずだと彼は話す。

実は、ゲル地区で育ったインジナーシさんは母子家庭で、10代半ばの頃、10歳以上年の離れた弟の世話をしながら学校に通っていたという。その当時、気晴らしで足を運んだのが「Focus On Kids」という写真教室だった。そこで彼は初めてカメラとモノクロフィルムを手にして、現像の仕方も学んだ。

インジナーシさんは、1990年代以降のモンゴルの民主化と資本主義化にともなう社会の変容とともに成長していった世代である。そんな彼に、いまモンゴルの若者世代は何を考えているのかについて尋ねたところ、こんな風に答えてくれた。
「いまの若い世代は、自分が10代だった頃に比べ、着ているものは見映えがいいし、垢ぬけていると思う。自分が撮影を始めた2000年代半ば頃から、街に高層ビルがどんどん建ち、SNSが普及することで人々の考え方や生活スタイルも大きく変わったが、インフレも激しく、格差が生まれてしまった。
昔より豊かになったはずなのに、いまの若い世代は明るい未来を描くのが難しくなっている。そのために、海外に出ていって働きたいという若者は増えていると思う」

筆者はモンゴルに対する専門的な知識や理解は乏しいが、興味深いのは、アジアの国々と同様に、この国でも高度経済期を迎えていく過程で経験する進歩や発展には、必ず矛盾や苦しみがともなうことだ。日本はもとより、それは東南アジアや中国でも見られたもので、多くの共通点がある一方、モンゴル固有の課題があるのは当然だろう。
ロシアと中国という権威主義的な大国に挟まれた人口わずか350万人ほどの小国でありながら、まがりなりにも民主的な社会を維持していくことはそれほどたやすいことではないからだ。政治家の汚職が起こるのはどこの国でも同じだが、民主的な体制になっても政治に対する失望があり、未来に展望を持てない若者の出国願望が高いこともそうだ。