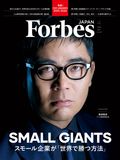気ままに通りをぶらつき、友人とクラブで酒を飲み語らう、なにげない瞬間にこそ、魅惑的なシャッターチャンスが潜んでいるからだ。
被写体となるのは、ライブハウスで出会ったパンク少年やDJ、ミュージシャンといった彼が好きな音楽業界の若者や同世代の友人たちの素顔であり、変転する都市に生きるさまざまなバックグランドを抱えた人物たち、荒涼たる大自然の秘境や草原に暮らす現代の遊牧民や子供たちである。

そんなインジナーシさんと彼の作品を理解するうえで、確認しておきたい2つのポイントがある。
まず、彼が1991年以前の社会主義時代のモンゴルの記憶を持たない世代であることだ。
以前、筆者は社会主義の時代と現在の民主化した社会の両方を知る1960年代生まれのモンゴル人女性に、今日のこの国の食文化のありようについて語ってもらい、「モンゴルだからこそ出会えるユーラシアの多国籍料理を食べ歩く」というコラムを書いた。そのなかで彼女は今日の経済発展を遂げた都市社会を生きる「いまの若い世代は社会主義のような苦難の時代を知らない」と話している。
その一方で、彼がゲル地区出身であることが、作品世界や社会に対するまなざしに大きな影響を与えていると思う。
ゲル地区とは、かつて草原に暮らしていた遊牧民が首都ウランバートルに大挙して移住して来たことなどで、同市周辺に無秩序に形成されたモンゴルの移動家屋であるゲルや簡易な家屋が密集する居住区のことだ。
ゲル地区には、一部しか上下水道システムが整備されておらず、市内の高層ビルや集合住宅が並ぶ整然としたエリアに比べ、決して良好とはいえない生活環境だ。
厳寒の冬には、この国の経済を支えている輸出資源でもある石炭を大量に使って暖をとるため、急速に進んだモータリゼーションの影響とともに、市内の大気汚染が深刻化しているといわれる。
ウランバートルにおけるこの2つの分離された異空間を往来するのは、ゲル地区の住人である。高層マンションの住人がゲル地区を訪れることはまずないからだ。
だが、こうした誰の目にも可視化された社会矛盾を抱えるゲル地区の住人こそ、ヒップホップをはじめとしたモンゴルのユニークなカルチャーシーンの担い手であることが多いという。写真家であるインジナーシさんも、その1人といえるだろう。