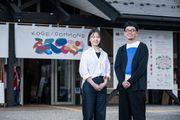——資金調達に関しては皆さん、苦労された経験があると思います。山野さんと岡井さん、後輩起業家たちにアドバイスはありますか。
山野:コロナ禍で、自分たちの取り組むビジネスのマーケットが消滅してしまいました。そんな中でもさまざまなVCが出資しているとSNSで発信していたので、藁にもすがる気持ちで相談に行ったのですが、結果的にはひとりも投資してくれませんでした。出資しているのは伸びているマーケットに対してで、本当に苦しんでいる人にはお金を出してくれないという現実を目の当たりにしましたね。VCの投資は、ボランティアではなくビジネスです。サポートを受けられるのは、ビジネスが伸びているという前提があってこそだというのを忘れてはいけないと感じました。
岡井:シードからシリーズAといった初期に投資してもらう投資家は、担当者で選ぶのがいいと思っています。上場などイグジットにたどり着くまでに10年かかるとすると、その間ずっと横にいるイメージがつくかどうか。お金はある程度集まるかもしれませんが、担当者は変えられません。いい担当者は、自分が困っているときも最後までついてきてくれますし、自分の見ている世界観も伝わりやすいと感じます。どんな担当者を選ぶかで、会社の格も決まります。いい人がいなかったら自己資本で事業をやったほうがいいと思うぐらい、担当者を見極めるのは大事ですね。

長尾:担当者が大事だというのは、本当にそのとおりだと思います。一方で、いい担当者を見抜くのは難しいとも感じます。そのため具体的な選び方のアドバイスはお伝えできないのですが、投資家とのコミュニケーションには周到な準備をしてから臨むことをおすすめします。自分たちの場合は、想定される質問を徹底的に洗い出して答えを用意し、資料も入念に揃えました。誠意を込めて提案すれば、数十社と面談する中で自分たちの取り組みに共感してくれる人が現れるはずです。
——続いて、成功について聞いていきます。西和田さんと佐渡島さんは、ピボットしたことが事業の成功に大きく貢献したそうですね。
西和田:再エネ特化の電力事業をやっていたと失敗談を話したのですが、そこから現在のクラウドサービスの提供へ舵を切りました。当時は株主や経営陣のなかでも意見が割れたのですが、リスクについての議論を経てピボットの意思を固め、電力事業の営業メンバーを一気にクラウド事業へ振り向けました。結果、いまは5000社以上で導入される日本一のサービスになったので、いい決断だったと思います。
佐渡島:最初はBtoCのビジネスモデルを考えていたのですが、途中でBtoBに切り替えました。先に失敗をどう乗り越えたかという話をしたのですが、ピボットに際して大きかったのは建設現場に足を運んだことです。お客さんの負を解消するために現場に張り付いてニーズを探りました。作業員の方がトイレに行くときもついていくなど、徹底的に現場での行動を調べました。そうして磨き上げたプロダクトがコロナ禍を機に建設業界で広まり、現在はARR(年間経常収益)の半分ほどを占めています。お客さんに密着してプロダクトを開発しきるのは大事だと思います。