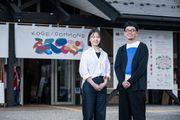とはいえ、被引用数が少ないことは、女性研究者のキャリアに影響を与える可能性が高い。研究者たちは論文で「引用数は採用や終身在職権といった重要なキャリア決定において大きな役割を果たし、そのキャリアの過程で研究者の名声に影響を与え続ける」と説明している。さらに、女性の研究が疎外されることは、科学にとっては悪いことだ。つまり多くの仕事が軽視され、ユニークな洞察や多様な視点を見逃している可能性があるのだ。
ここで、男性の研究が女性より質が高いから多く引用されているのではないことに注意することが大切だ。
テキサス大学オースティン校の教授であり、この研究の主著者であるヴェロニカ・ヤンは「男性の仕事の方が単に優れている、あるいは引用に値するという主張を支持する実証的証拠はほとんどありません。しかし学術界をはじめとして、判断や意思決定における性別バイアスの存在を示す実証的証拠は豊富にあります。私たちのデータから得られた希望の持てるメッセージは、女性にはバイアスが見られないということです。私たちが見つけたバイアスはいずれも男性によるものです。しかし、そのパターンは若い研究者ほど変化をしているようで、若い女性には逆のバイアスがかかっている例さえありました」と語る。
この研究は心理学の学者を調査したが、他の分野も同様の問題に直面している。たとえば、神経科学分野における性別による引用の不均衡は主に男性著者によって行われていることが研究で示されている。政治学では、この現象に名前さえ付けられている。高名な研究者がその高名ゆえにさらに注目を集める現象である「マタイ効果」は、ある分野で男性の研究が最も中心的で重要であるとみなされている場合に起こる。対照的に、女性の研究が男性のものよりも価値が低く見られたり、彼女たちのアイデアが男性の学者に帰属される現象には「マチルダ効果」という名前がついている。
ヤンは、この研究結果は学問の枠を超えて一般化できると考えている。「私たちのプロジェクトは、被引用数ギャップを調べる方法として始まりましたが、それは被引用数のギャップについてだけ語るものではありません。この結果は、卓越性について考えるとき、誰を思い浮かべるかという偏りを浮き彫りにしているのです。こうしたバイアスは、たとえば、講演に誰を招待するか、フェローシップや賞に誰を推薦するかを考える際に、誰を支援し、機会を与えるべきかの判断に影響を与える可能性があるのです」と彼女はいう。
さらにヤンは「10年後に振り返ってみるとおもしろいでしょう。どちらの方向にも性別の偏りがなくなっているのが理想ですね」と付け加えた。
(forbes.com 原文)