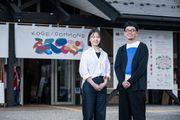AIによって広がるスポーツの楽しみ方
では、スポーツファンにとっては、AIはどのような利便性をもたらしているのだろうか? 一部の米アメフト・プロリーグのNFLで導入検討が始まっているのが、試合観戦中に、自分が贔屓にしている選手や監督にリアルタイムでインターネットを介してチャット機能で話しかけると、本人の返答を習熟したボット(AIによる対話型ロボット)から即返事が送られてくるサービスである。今後は、ディープフェイク技術で、ボットの返事を選手の音声で返してくることも可能になるため、観客はこれまでになかったリアルタイムな体験に関心を持つことは確実だろう。球団はボットサービスを有料サービスとして展開するか、もしくは無償で広告付きサービスとして広告収入を獲得し、選手に利益を分配することにより増益増収が図れる。こうした新たなサービスは、新たな収益ビジネスをスポーツ産業に組成させる機会を与えるに違いない。
そして試合会場におけるARやVRを利用した、試合中にビューアーや手元のスマホで、選手やプレイについてのデータ、リプレイ映像、自在に選択できる場内カメラ映像などを提供するサービスでも収益を図ることが可能になる。
こういったAI技術を使ったファン対応は、多くの球団や組織団体が導入を進めている。AI技術によってファンの属性の把握すること以外にも、彼らがスポーツの何に魅力を感じているのか、どの程度お金を使うのか、なんのSNSを使い、どのようなキーワードを頻繁に使用しているかなどを把握することで、個人的特性に寄り添ったメッセージを送ることができる。そうすることで、最大限の売り上げが期待できるため、欧米の多くのプロリーグと球団はAI導入を経営戦略に反映しているのである。
費用や情報管理などの課題
しかし、AIのスポーツ産業への導入には障壁や懸念も立ちはだかっている。まずAIの導入は未だ高額で、初期的な機能のものでも 1千万円程度、高度のものであれば 5,6千万円の初期費用が必要とされる。したがって、弱小球団などでの導入は、監督やコーチ、選手が個人ベースで、安価で利用できるサービスを自ら工夫して使っていくことが必要である。また、膨大な個人データを集積、分析するため、選手の個人情報の流出が危惧される。 フェアネスや透明性と言った倫理的な統制も、世界規模でのスタンダードは存在せず、国内でも法整備は後追い状態だ。AIやディープフェイクによる著作権のみならず、肖像権やパブリシティー権の侵害など、スポーツ選手に対してどのような法律が適用されるべきか確定していない。こうした間に、AIは急速に進化を遂げており、スポーツ産業は導入を余儀なくされているものの、選手の個人情報と権利に対して最大の留意を払いながらの展開を図るべきだろう。