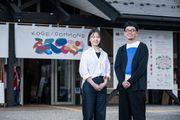ダンゴムシにもクリエイティビティがある!?
大学の研究者で、友人の森田先生、右田先生のダンゴムシの研究もとても面白いのでご紹介しますね。ダンゴムシは壁にぶつかると右に曲がって、次にぶつかると左、次にぶつかると右、と左右交互に曲がるという「交替制転向反応」という特性があります。
ダンゴムシは湿気が好きなので、土が乾いていると、「ヤバい」と思って必死で、湿気っているところに移動しようとしますが、できるだけ遠くへ離れていく一番合理的なアルゴリズムがこの左右交互に曲がることなんだそうです。
 この動きをロボットプログラミングで作るのは、すごく簡単です。壁にぶつかったら、体の向きを右、また次にぶつかったら「さっきと逆」とプログラムするだけでいい。ロボットの動きとしてはすごく単純なので、ダンゴムシのような虫もロボットみたいな単純ものなのかなとつい、思ってしまいますよね。ところが、それだけじゃない、ということに気づいて、しかもそれを本当に確かめた人たちがいるのです。
この動きをロボットプログラミングで作るのは、すごく簡単です。壁にぶつかったら、体の向きを右、また次にぶつかったら「さっきと逆」とプログラムするだけでいい。ロボットの動きとしてはすごく単純なので、ダンゴムシのような虫もロボットみたいな単純ものなのかなとつい、思ってしまいますよね。ところが、それだけじゃない、ということに気づいて、しかもそれを本当に確かめた人たちがいるのです。ダンゴムシもキレる?同じことばかりでない新しい可能性の芽生え
ここが重要なのですが、「ダンゴムシは本当にいつまでも右、左を繰り返すだろうか?」という疑問を持つ人は何人かはいますが、いざそれを本当に試す人はやはり少ない。それを本当に確かめる人は世界を探してもそんなに多くはなく、さらに、確かめて本当にその結果までたどりつける人はさらに少数です。ところが、ダンゴムシの交替性転向反応がいつまで続くのか、何十回も繰り返してみようと専用の装置を作って、本当にダンゴムシとにらめっこしながら、これを繰り返した人がいるのです。
彼らは、さすがのダンゴムシもキレる?とでも言いそうな、右にしか曲がらなくなるダンゴムシや、突然、上上上と壁を登りだすダンゴムシを発見したのです。プログラムされたロボットではぜったいにこうはならず、世界で初めて「ダンゴムシのクリエイティビティ」に関する論文(「動物行動における擬合理性のモデル化:オカダンゴムシの交替性転向反応における認知的側面のシミュレーション」として発表されました。
 虫は「単純なルールで動くロボットみたいなもの」と勝手にみんな思いこんでいましたが、実は、堪忍袋の緒が切れる。この「切れる」っていうのはすごいことで、「新しい行動規範を自分で生み出せる」可能性という意味で、クリエイティブな性質の証拠なんです。
虫は「単純なルールで動くロボットみたいなもの」と勝手にみんな思いこんでいましたが、実は、堪忍袋の緒が切れる。この「切れる」っていうのはすごいことで、「新しい行動規範を自分で生み出せる」可能性という意味で、クリエイティブな性質の証拠なんです。ダンゴムシみたいな虫ですら、予定調和でない新しい行動を生み出せるのだとしたら、人間みたいにもっと複雑な認知過程をもっているなら、すごい期待をしてしまいますよね。でもこの研究論文でも、徹底的に観察して、他の人があきれるくらいとことん続けることがすごく大切だと教えてくれているように思います。
とにかく自分で面白いな、不思議だなと思ったことがあれば、それをとことん集める、とことん続ける、それを繰り返す人たちがぼくの周りにはたくさんいるんです。「発見できるまではやめない」ことが、1番大事なコツでもあるのですが、ふつうはそんなチャンスがなかなかない。その意味では、バーバパパの学校では自分たちの中にある気づきをしっかり「待つ」ということをとても大切にしようという想いがあふれています。
他の学校ではなかなか待ってもらえないことでも、この学校なら、「やめない」をずっとやっていても待っていてくれる人がいっぱい見つかると思います。そういう意味で、みなさんはこの学校にいる間にぜひ、「やめない」「続ける」練習をたくさんしてもらいたいなと思っています。その力をつけられるような場所と時間は決して多くはありません。