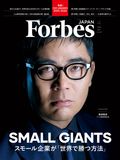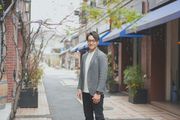行き詰まると電車に乗って考える
当時のロボット研究は、多くが「移動すること」や「ものをつかむこと」がテーマでした。しかし、視覚認識を研究していた石黒さんはそれとは異なった考えを持っていました。「ロボットがロボット自身の目で見て判断すれば、ロボットをもっと賢くできると思ったのです。人は外からの情報の90%を、見ることで得ている。そこでロボットにカメラを付けることを考えました」
では、人はどうやって目で見て判断しているのか。ただ見ているだけではダメで、経験値を蓄積しているから判断できることに石黒さんは気づきます。
「となると、ロボットが自分で見て、判断して、認識できるようにしないといけない。機械の性能をよくしようとプログラムを書いているだけでは、実はダメなのです」
これはいまのAI研究にも通じるところかもしれません。そして、コンピュータはコンピュータの形でいるのではなく、人間と同じように経験できる形、学習できる形が必要になるのだと考えたのです。
「その意味で、コンピュータにとってロボットは重要だと僕は感じました。そして、ロボットを知ることは人間を知ることにつながるとも」
これが石黒さんの博士課程のテーマとなりましたが、突破口はなかなか見つかりませんでした。
「実は、僕は行き詰まると電車に乗るクセがありまして(笑)。博士論文のアイデアが浮かんだときも、阪急宝塚線を何度も往復していました。そして浮かんだのが、360度周囲を見渡す全方位視覚をもつロボットの研究でした」
そしてここから、「より人間らしさをつくる」というテーマが生まれていきます。苦しみ抜いて1つの発見が生まれると、後は芋づる式にアイデアにつながっていきました。
「アンドロイドを開発すると聞いて、クレイジーだと思われることもあるようですが、僕にしてみればすごく自然なことなのです。研究の過程で、ごっそりと抜け落ちているものがあったのです。真剣に、信念を持って研究をしていれば、躊躇なくそこに取り組むでしょう。まわりから何を言われたとしても」
実際には、アンドロイド開発には驚きはあったものの、まわりからは反発の声はありませんでした。むしろ「よくやった」という声がほとんどだったそうです。
「ただ、これは研究者の話。一般の人はそうではない。特にキリスト教圏では。だから、最初に発表する地として選んだのは、国内ではなく、イタリアでした。キリスト教の総本山に近いところを選んだ。結果は絶賛でした」
実はイタリアには、人体解剖を世界で初めて行った大学(ボローニャ大学)もあります。総本山だけに、「人間とは何か」という探求心に対して、純粋だったのです。
「僕は人間を知りたい。そういう目的でやっている、と説明したら、ものすごく興味を持ってくれて。面白いからもっとやれと。ちゃんとした目的をもって研究していれば、反対される理由なんてないんです」
生活と研究のモチベーションは同じ
根本的な問題こそ大事。石黒さんは、そう語ります。そして、世の中の不思議「人間とは何か」を知る1つのツールとして、アンドロイドの開発はありました。「工学的に人間と同じものができれば、人間とは何かという説明になります。そして具体的な目標があれば、動きやすくなる。次に何をしないといけないのか、順番が決められるようになる」